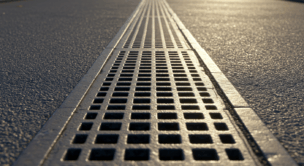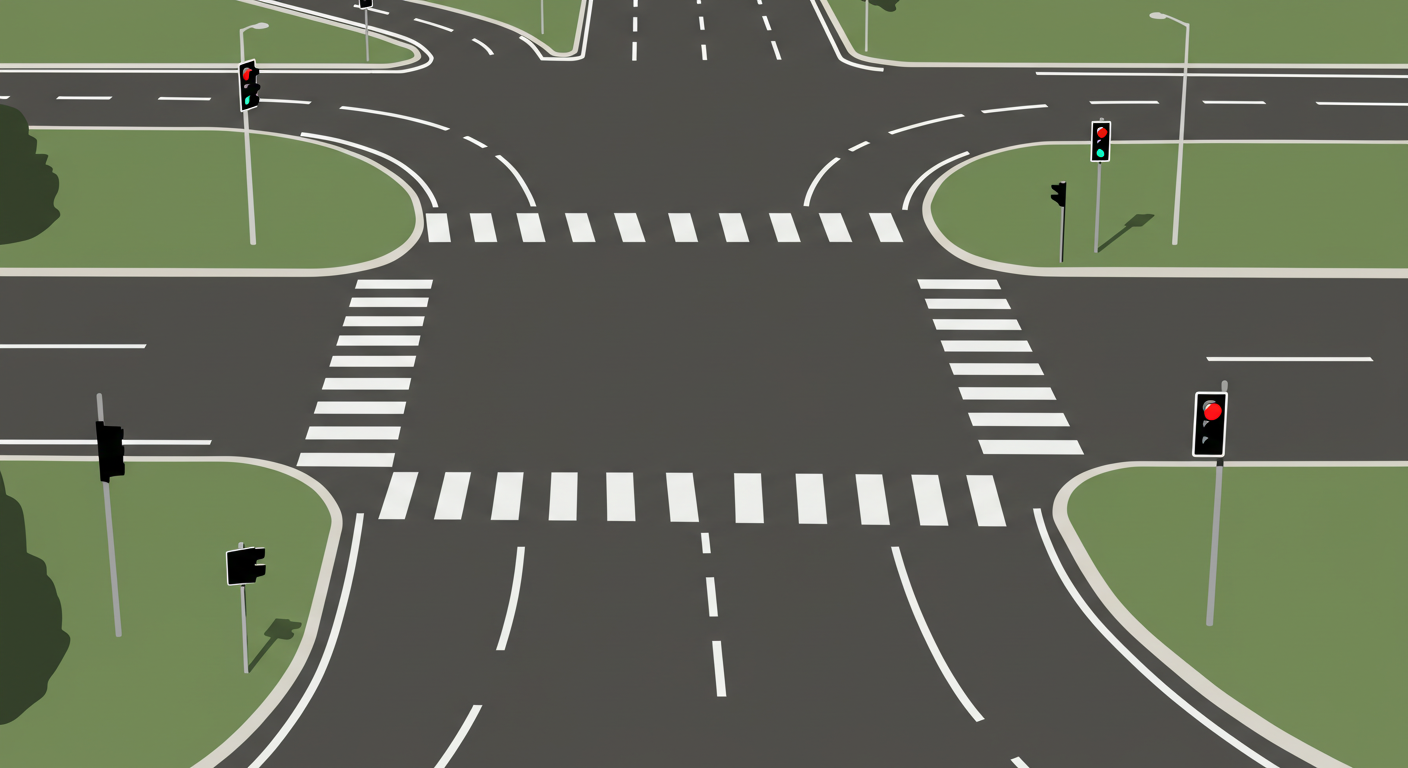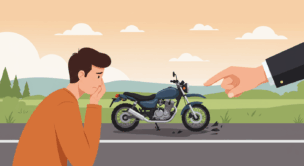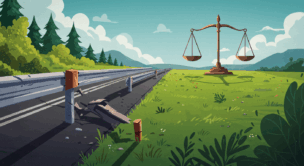高速道路を快適に走行中、突如「ピシッ」という鋭い音。多くのドライバーが経験する、この不快な瞬間が「飛び石事故」の始まりです。あなたの愛車のフロントガラスに刻まれた一本の傷は、単なる損害以上の、深い不公平感をもたらします。
「前のトラックから石が飛んできたのは間違いないのに、相手は知らんぷり…」
「ドライブレコーダーには先行車が映っている。これなら責任を追及して修理費用を請求できるはずだ!」
「相手から『お前の車間距離が近いからだ』と逆に言いがかりをつけられた…」
このような状況で、多くの方が警察への届出をためらい、「証明できないから」と泣き寝入りを選択してしまいます。しかし、その判断は本当に正しいのでしょうか?事故証明を取得し、法的な手続きを進める道は本当に閉ざされているのでしょうか?
この記事は、実際に裁判になった判例を徹底的に分析し、飛び石事故の責任の所在について詳しく解説するものです。
- ✔ なぜ飛び石の責任追及は困難なのか、その明確な法的理由(過失・因果関係の壁)
- ✔ 【勝訴判例に学ぶ】相手への損害賠償請求が認められるケースとは?
- ✔ 被害者・加害者になった時の具体的対応策と、ドライブレコーダーの本当の価値
- ✔ 車両保険を使うべきか否かの経済的判断基準と、保険金請求が棄却される危険なパターン
法的な現実を直視し、その上で最善の選択をするための知識を、この記事で手に入れてください。
続きを読む