
結論からいうと、慰謝料での「弁護士基準(裁判基準)」とは異なり、休業損害では、「弁護士基準」という言葉はあまり使いません。
しかし、休業損害を最大化して計算するために、弁護士が良く使う計算方法は存在します。これを「休業損害の弁護士基準」というかは別として(本記事では、便宜的に「弁護士基準」という言葉を使います。また、休業損害の計算方法について、任意保険会社が良く使う基準を、「任意保険基準」といいます。)、この記事では、交通事故における休業損害を弁護士基準で最大限受け取るための具体的な計算方法、請求のポイント、そして弁護士費用特約の活用法まで、詳しく解説します。休業損害計算ツールの紹介や、交通事故で休業補償の嘘をつくリスクについても触れていきます。
その他、「交通事故慰謝料と休業損害は別のもの?」、「交通事故の休業損害はいつまで請求できるの?」、「交通事故の休業損害の計算方法が複雑…」、「もし休業損害証明書の内容が違っていたらばれる?」、「そもそも交通事故の休業補償はいつもらえるの?」、「休業損害がなぜ90日で計算されるの?」といった疑問や不安をお持ちの方も多いでしょう。
特に、弁護士費用特約に加入されている方は、自己負担なく弁護士に依頼し、弁護士基準での請求を目指す絶好のチャンスです。この記事を読んで、正当な補償を受け取り、安心して治療に専念しましょう。
主要なポイント
- 交通事故の休業損害は、事故がなければ得られたはずの収入を補償するもの。
- 計算基準には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがあり、弁護士基準が最も高額になる可能性がある。
- 休業損害と慰謝料は別物であり、それぞれ請求できる。
- 休業損害は、原則として症状固定日までが補償対象期間となる。
- 職業(会社員、自営業、主婦(夫)など)によって計算方法が異なる。
- 弁護士費用特約があれば、費用負担なく弁護士に依頼し、弁護士基準での請求を目指せる。
- 虚偽の申告は重大なリスクを伴うため、絶対に避けるべき。
目次
1.交通事故の休業損害を弁護士基準で計算すべき理由
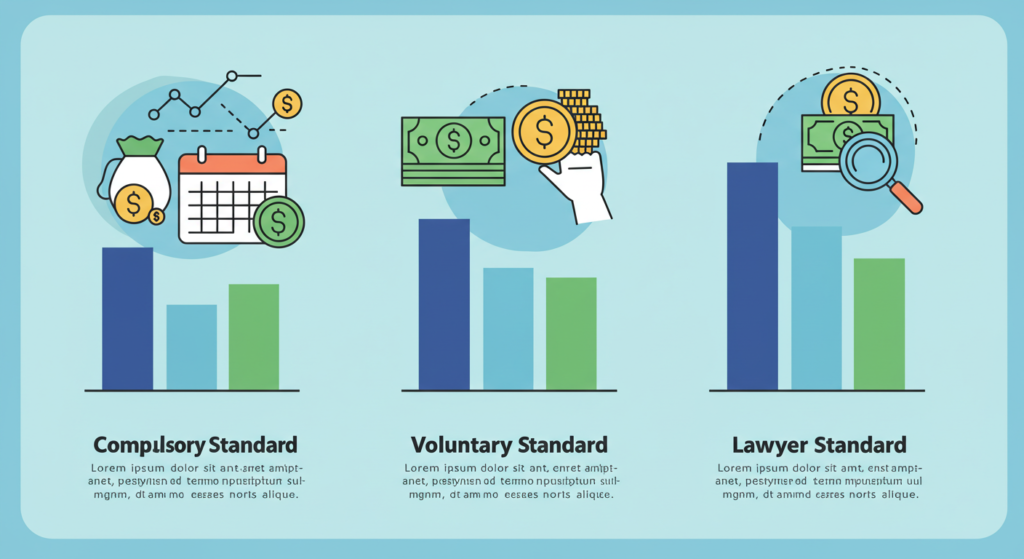
交通事故に遭い、治療のために仕事を休むことになった場合、収入が減ってしまうのは大きな不安です。ここでは、まず「交通事故の休業損害」とは具体的に何を指すのか、そしてなぜ「弁護士基準」で計算することが重要なのか、基本的な知識から分かりやすく解説していきます。保険会社から提示された金額に安易に同意する前に、ご自身の状況と照らし合わせて正しい知識を身につけましょう。
- 1-1. そもそも交通事故の休業損害とは?補償される収入の範囲
- 1-2. 休業損害の3つの算定基準:自賠責・任意保険・弁護士基準の違いと金額差
- 1-3. なぜ弁護士基準が重要?交通事故で損しないための休業損害請求
- 1-4. 「交通事故慰謝料と休業損害は別」!混同しやすいポイントと両方請求する重要性
- 1-5. 交通事故の休業損害はいつまで請求できる?症状固定までの期間
- 1-6. 休業損害はなぜ90日で計算することが多い?その理由と弁護士基準での例外
- 1-7. 有給休暇を使っても休業損害は請求できる?弁護士基準での考え方
1-1. そもそも交通事故の休業損害とは?補償される収入の範囲
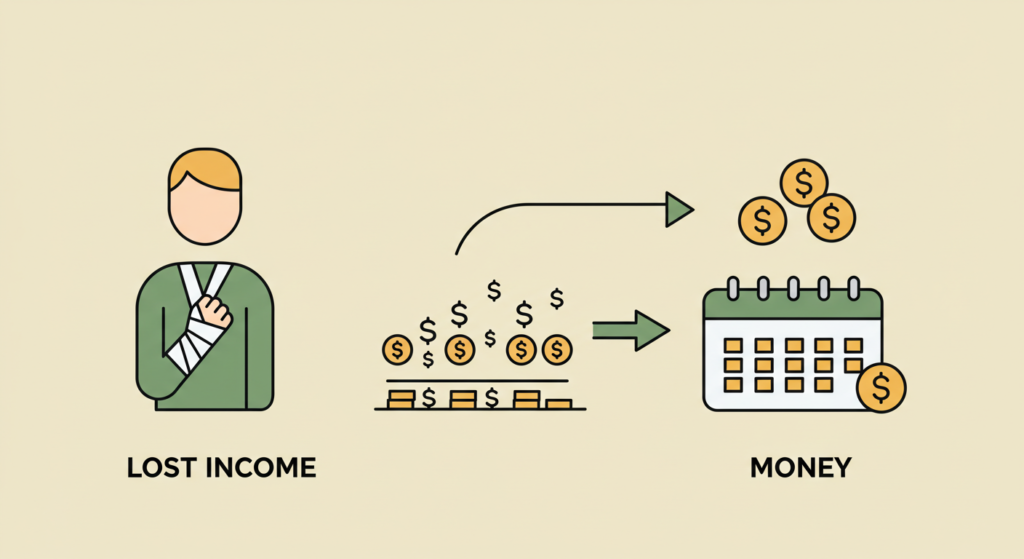
交通事故における「休業損害」とは、事故によるケガの治療のために仕事を休んだことで、本来得られるはずだった収入が減少したことに対する補償です。簡単に言えば、「事故がなければ得られたはずの収入」を補填するものです。
これは、治療費や通院交通費などの「積極損害」とは異なり、得られるはずだった利益が得られなくなった「消極損害」に分類されます。
補償される収入の範囲
休業損害として認められる収入は、単に基本給だけではありません。原則として、事故前の収入状況に基づいて、以下のようなものも含まれる可能性があります。
- 基本給: 月給や日給、時給など
- 付加給: 残業代、各種手当(通勤手当、住宅手当、役職手当など)、ボーナス(賞与)
- ※ボーナスについては、事故による休業が査定に影響し減額された場合などに認められることがあります。証拠としては、賞与減額証明書などを書いてもらう必要があります。
- 事業所得: 自営業者やフリーランスの場合、事故前の所得状況に基づき計算されます。
- 家事労働: 専業主婦(主夫)や、兼業で家事に従事している方も、家事労働に経済的な価値があるとして休業損害が認められます。
重要なのは、「事故が原因で、収入を得る機会が失われた」といえるかどうかです。どこまでが補償範囲に含まれるかは、具体的な状況や選択する計算基準(特に弁護士基準)によって判断が異なる場合があります。
1-2. 休業損害の3つの算定基準:自賠責・任意保険・弁護士基準の違いと金額差

交通事故の休業損害を計算する際には、主に以下の3つの基準が用いられます。どの基準を使うかによって、最終的に受け取れる金額が大きく変わるため、それぞれの特徴を理解しておくことが非常に重要です。
- 自賠責保険基準:
- 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)で用いられる基準です。自賠責保険は、交通事故被害者の最低限の救済を目的とした強制保険であり、補償額には上限があります(傷害に関する損害全体で120万円まで)。
- 休業損害の計算は、原則として1日あたり6,100円です(2020年4月1日以降の事故に適用。それ以前は5,700円)。
- ただし、立証資料(給与明細など)により1日6,100円を上回ると立証できる場合は、1日あたり19,000円を上限として実額が認められることもあります。
- 3つの基準の中では、基本的に最も低い金額になることが多いです。
- 任意保険基準:
- 加害者が加入している任意保険会社が、示談交渉の際に独自に設定している基準です。
- この基準は各保険会社によって異なり、公表されていません。
- 一般的には、自賠責保険基準よりはやや高いものの、次に説明する弁護士基準よりは低い金額になる傾向があります。
- 弁護士基準(裁判所基準):
- 過去の裁判例の積み重ねによって形成された基準で、弁護士が示談交渉や裁判を行う際に用います。
- 原則として、事故前の実際の収入(基礎収入)を基に計算します。収入を証明する資料があれば、実態に即した適切な金額を請求できます。
- 3つの基準の中で最も高額になる可能性が高い基準です(ただし、自賠責基準の方が高くなる場合もあります。複数の計算方法で金額を比較することが重要です)。
どの基準を用いるかで受け取れる金額に少なからぬ金額の差が生じます。
1-3. なぜ弁護士基準が重要?交通事故で損しないための休業損害請求

前項で見たように、交通事故の休業損害は、どの基準で計算するかによって金額が異なります。そして、被害者にとって最も有利な条件、つまり実態に見合った正当な補償額に近いのが弁護士基準です。
保険会社はなぜ低い基準を提示するのか?
加害者側の任意保険会社は、示談交渉の初期段階では、自賠責基準や、それに近い独自の任意保険基準に基づいて算出した休業損害額を提示してくることがほとんどです。
被害者自身が保険会社と交渉する場合、専門知識や交渉力が不足していると、保険会社の提示額が妥当なものか判断できず、低い金額で示談に応じてしまうリスクがあります。保険会社は交渉のプロであり、「これが通常の基準です」「裁判をしても変わりませんよ」といった説明で、被害者に不利な条件での合意を促すことも少なくありません。
弁護士基準で請求するメリット
弁護士に依頼し、弁護士基準に基づいて請求することには、以下のような大きなメリットがあります。
- 適正な金額の獲得: 事故前の実際の収入に基づき計算されるため、最も実態に合った、かつ高額な補償を受けられる可能性が高まります。特に収入が高い方ほど、その差は顕著になります。
- 対等な交渉: 法律と交渉の専門家である弁護士が介入することで、保険会社と対等な立場で交渉を進めることができます。保険会社のペースに乗せられることなく、被害者の正当な権利を主張できます。
- 法的な根拠に基づく主張: 弁護士は過去の裁判例や法的な根拠に基づいて主張を行うため、保険会社も無下に低い金額を提示し続けることが難しくなります。
- 精神的な負担の軽減: 煩雑でストレスの多い保険会社との交渉をすべて弁護士に任せられるため、被害者は家庭、仕事、治療に専念できます。
弁護士費用特約の活用
「弁護士に頼むと費用が高いのでは?」と心配される方もいるかもしれませんが、ご自身やご家族が加入している自動車保険などに弁護士費用特約が付帯していれば、多くの場合、弁護士費用(相談料・着手金・報酬金など)の自己負担が実質0円になります(通常、上限300万円程度まで補償)。
この特約を利用しても、保険の等級が下がったり、翌年の保険料が上がったりすることはありません。せっかく加入している特約を使わない手はありません。交通事故で休業損害が発生し、弁護士基準での請求を考えているなら、まずは弁護士費用特約の有無を確認し、積極的に弁護士への相談を検討しましょう。
1-4. 「交通事故慰謝料と休業損害は別」!混同しやすいポイントと両方請求する重要性

交通事故の損害賠償について話すとき、「慰謝料」と「休業損害」が混同されているケースがよく見受けられます。「ケガで仕事を休んだことに対する補償も込みで慰謝料が支払われるのでは?」と考えてしまう方もいます。
慰謝料と休業損害は全く別の損害項目であり、それぞれ別々に計算され、両方請求することができます。
- 慰謝料: 交通事故によって被った精神的苦痛に対する賠償金です。ケガをしたこと自体の苦痛、入通院を余儀なくされたことによる苦痛などが対象となります。
- 入通院慰謝料: ケガの治療のために入院や通院をした期間や日数に応じて支払われます。
- 後遺障害慰謝料: 治療を続けても症状が改善せず、後遺障害等級が認定された場合に、その等級に応じて支払われます。
- 死亡慰謝料: 被害者が死亡した場合に、被害者本人および遺族の精神的苦痛に対して支払われます。
- 休業損害: 交通事故によるケガの治療のために仕事を休んだことで失われた収入に対する補償です。「事故がなければ得られたはずの収入」を補填するものであり、経済的な損失(逸失利益)にあたります。
なぜ混同しやすいのか?
どちらも交通事故によるケガに関連して発生する損害であるため、区別がつきにくいと感じる方がいるかもしれません。また、保険会社との示談交渉では、様々な損害項目(治療費、慰謝料、休業損害、通院交通費など)をまとめて提示されることもあるため、個々の項目がどういう性質のものなのか分かりにくくなっている場合もあります。
両方請求する重要性
慰謝料と休業損害は、その性質も計算根拠も異なります。例えば、入通院慰謝料は主に治療期間や日数によって算定されますが、休業損害は事故前の収入額と休業日数によって算定されます。
例:入通院慰謝料と休業損害の比較(弁護士基準・むちうち等他覚所見なしの場合)
- 通院期間3ヶ月、実通院日数30日の場合
- 入通院慰謝料(弁護士基準・軽傷用):53万円
- 休業損害(日額1万円と計算される会社員が15日休業した場合):15万円
このように、慰謝料と休業損害はそれぞれ独立して計算され、合算して請求できます。もし、「慰謝料をもらうから休業損害は請求できない」とか「休業損害に慰謝料も含まれている」などと誤解してしまうと、本来受け取れるはずの賠償金の一部を受け取り損ねてしまうことになり、大きな損失につながります。
なお、通院慰謝料については、以下の計算機で簡単に計算できます。計算式も出力されますので、是非ご利用ください。
交通事故の被害に遭われた際は、慰謝料と休業損害は別物であるとしっかり認識し、それぞれについて弁護士基準に基づいた正当な金額を請求することが重要です。
1-5. 交通事故の休業損害はいつまで請求できる?症状固定までの期間
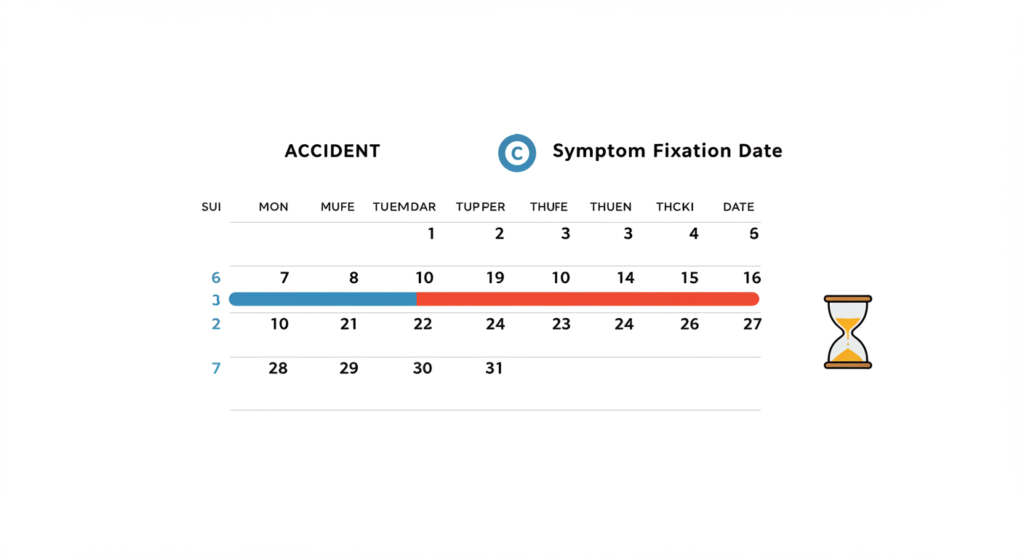
交通事故による休業損害は、いつまでも請求できるわけではありません。では、休業損害の賠償の対象となる期間はいつまででしょうか。
賠償の対象となる休業期間
「いつからいつまでの休業が損害賠償の対象となるのか」という問題があります。
- 原則: 事故発生日から症状固定日までの期間中に、治療のために必要かつ相当な範囲で休業した期間が対象となります。
- 症状固定: これ以上治療を続けても、症状の改善が見込めないと医師が判断した状態を指します。後遺障害が残る場合は、この症状固定日をもって後遺障害等級認定の申請手続きに進むことになります。
- 症状固定後の収入減少: 症状固定後も後遺障害の影響で労働能力が低下し、収入が減少する場合は、休業損害ではなく「後遺障害逸失利益」として別途請求することになります。これは、将来にわたって得られたはずの収入が失われたことに対する補償です。
休業の必要性と相当性
単に仕事を休んだというだけでは休業損害が認められず、「ケガの治療のために休業することが必要であり、その休業期間や日数が相当である」と認められる必要があります。
- 必要性: 医師が休業の必要性を認めているか(診断書に記載があるかなど)が重要な判断要素となります。
- 相当性: ケガの程度や内容、治療状況、仕事内容などを考慮して、休業期間が長すぎないか、本当に休業が必要だったのかが判断されます。例えば、軽微なむちうちで数ヶ月にわたる全休業が認められるかは、具体的な状況によります。
保険会社は、治療が長期化した場合などに、特に休業損害の内払いがなされていると、「もう休業の必要はない」「症状固定ではないか」と主張し、休業損害の支払いを打ち切ろうとすることがあります。
医師の診断や指示に基づき、治療のために必要な休業であることを適切に主張していくことが重要です。医学的な知見も踏まえ、休業の必要性・相当性を効果的に主張します。
1-6. 休業損害はなぜ90日で計算することが多い?その理由と弁護士基準での例外

交通事故の休業損害、特に給与所得者(会社員や公務員など)の1日あたりの基礎収入を計算する際、任意保険会社は、「事故前3ヶ月間の収入 ÷ 90日」という計算式がよく用います。なぜ90日(3ヶ月)なのでしょうか? これには主に以下のような理由があります。
90日(3ヶ月)で計算する主な理由
- 直近の収入実態を反映するため:
- 事故に遭う直前の収入状況が、事故がなければ得られたであろう収入を最も正確に反映していると考えられるためです。あまりに古い期間の収入だと、昇給や異動などにより現在の収入実態と乖離している可能性があります。直近3ヶ月という期間は、現在の収入状況を反映しつつ、一時的な変動をある程度平準化するのに適度な期間とされています。
- 収入の変動を平準化するため:
- 月によって残業時間や手当が変動し、収入にばらつきがある場合でも、3ヶ月間の平均を取ることで、特定の月の特殊な事情に左右されず、より安定した平均的な収入額を算出することができます。
- 裁判実務で確立された方法であるため:
- 過去の多くの裁判例を通じて、事故前3ヶ月間の収入を基礎とする計算方法が、実務上の一般的な基準として定着しています。弁護士基準(裁判所基準)も、この考え方を基本としています(ただし、後に述べるとおり、90日ではなく実稼働日数で計算すると有利になることが多いです)。
基礎収入の計算式(原則)
- 1日あたりの基礎収入 = 事故前3ヶ月間の収入合計額 ÷ 90日
- ※収入合計額には、基本給のほか、残業代や各種手当など、労働の対価として支払われるものが含まれます(税込)。
弁護士基準における例外
ただし、常に「90日」で計算するのが適切とは限りません。弁護士基準では、より実態に即した公平な算定を行うため、以下のような計算方法が用いられることがあります。
- 事故前3ヶ月間の収入合計額 ÷ 90日ではなく、実労働日数で割る:基本的にこちらの方が基礎収入が上がります。90日で割ってしまうと、休日も含んだ基礎収入になってしまいます。
- 収入の変動が大きい職種:
- 歩合給の割合が大きい営業職や、季節によって収入が大きく変動する職種(例:季節労働者)などの場合、直近3ヶ月だけでは実態を正確に反映できないことがあります。このような場合は、事故前6ヶ月間や1年間の収入を基に計算することがあります。
- 計算例: 1日あたりの基礎収入 = 事故前1年間の収入合計額 ÷ 365日
- 事故前3ヶ月間に特殊な事情があった場合:
- 例えば、事故前3ヶ月間にたまたま病気で長期欠勤していた、育児休業を取得していたなど、通常よりも収入が著しく低くなっていた特殊な事情がある場合は、その期間を除外したり、より長期間の平均収入を用いるなど、実態に合わせて柔軟に判断されます。
- 就職・転職直後の場合:
- 就職や転職をしてから3ヶ月経っていない場合は、その就労期間のみの収入を基に計算したり、雇用契約書などから予定される収入額を推定して計算したりします。
このように、弁護士基準では画一的に「90日」で計算するのではなく、個別の事情を考慮して、被害者の実収入を可能な限り正確に反映する計算方法が採用されます。保険会社が提示する計算方法に疑問がある場合は、弁護士に相談し、弁護士基準に基づいた適切な計算方法を確認することが重要です。
1-7. 有給休暇を使っても休業損害は請求できる?

交通事故によるケガの治療のために、やむを得ず有給休暇(年次有給休暇)を使って仕事を休んだ場合、「給料は減っていないから休業損害は請求できないのでは?」と考える方もいるかもしれません。
しかし、有給休暇を使って休んだ場合でも、原則として休業損害として請求できると考えられています。
なぜ有給休暇使用分も請求できるのか?
その理由は、有給休暇は労働者に与えられた権利であり、本来は労働者が自由な目的(リフレッシュ、私用など)のために利用できるものだからです。交通事故という、本来使う必要のなかった理由のために有給休暇を取得せざるを得なかったこと自体が、被害者の財産的利益(休暇を取得する権利)の侵害であり、損害にあたると考えられるのです。
- 事故がなければ、その有給休暇は別の目的で使えたはずです。
- 事故のために有給休暇を消費させられたことで、将来、他の目的で使えるはずだった休暇日数が失われたことになります。
したがって、たとえ有給休暇を使ったことで給与が支払われ、直接的な収入減少がなかったとしても、その日数分に相当する休業損害を請求することが認められています。
請求に必要な書類
有給休暇使用分の休業損害を請求するには、通常の休業損害証明書に会社に記入してもらえば大丈夫です(有給休暇を使用した場合の書き方に沿って、会社が書いてくれます)。
交通事故でやむなく有給休暇を使ってしまった場合でも、諦めずに休業損害として請求しましょう。保険会社が認めない場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
2.交通事故の休業損害を弁護士基準で最大限にするポイント

交通事故による休業損害の基本的な知識と、弁護士基準で請求する重要性をご理解いただけたでしょうか。ここからは、より実践的な内容として、職業別の具体的な休業損害計算方法(弁護士基準)、請求に必要な書類や注意点、そして弁護士費用特約を活用して専門家に依頼する流れなどを詳しく解説していきます。ご自身の状況に合った適切な対応を知り、正当な補償を受け取るための一歩を踏み出しましょう。
- 2-1. 【職業別】交通事故の休業損害計算方法(弁護士基準):会社員・自営業・主婦(主夫)・アルバイト
- 2-2. 【要注意】休業損害証明書は提出必須?虚偽申告(嘘)はばれるのかリスク解説
- 2-3. 交通事故の休業補償はいつもらえる?支払いタイミングと「内払い」の活用
- 2-4. 弁護士費用特約があれば実質0円!弁護士に依頼するメリットと依頼手順
- 2-5. 自分でできる?休業損害計算ツールの活用法と弁護士基準との比較
- 2-6. まとめ:交通事故の休業損害は弁護士基準での請求を検討
2-1. 【職業別】交通事故の休業損害計算方法(弁護士基準):会社員・自営業・主婦(主夫)・アルバイト

休業損害の計算方法は、被害者の職業や収入形態によって異なります。弁護士基準では、それぞれの実態に合わせてより公平な算定を目指します。ここでは主な職業別に、弁護士基準に基づいた交通事故の休業損害計算方法のポイントを解説します。
1. 会社員・公務員(給与所得者)
最も一般的なケースです。弁護士基準では、以下の計算式を基本とします。
- 休業損害額 = 1日あたりの基礎収入 × 休業日数
- 1日あたりの基礎収入:
- 原則: 事故発生前3ヶ月間の給与合計額 ÷ 90日
- 給与合計額: 基本給に加え、残業代、通勤手当、住宅手当、皆勤手当、役職手当などの各種手当(付加給)を含む、税金控除前の総支給額(いわゆる額面)です。
- 例外: 収入変動が大きい場合(例: 歩合給が多い)は6ヶ月や1年の平均を用いる、実労働日数で割る、などの調整があります(1-6参照)。
- 休業日数:
- 実際に治療のために仕事を休んだ日数(欠勤、遅刻、早退を含む)。
- 有給休暇を取得した日も原則として含まれます(1-7参照)。
- 土日祝日などの所定休日を含むかどうかは、基礎収入の計算方法(暦日数で割ったか、実労働日数で割ったか)によって扱いが変わることがあります。弁護士に確認するのが確実です。
- 1日あたりの基礎収入:
- ボーナス(賞与)の減額: 事故による欠勤や評価低下が原因でボーナスが減額された場合、その差額分も休業損害として請求できる可能性があります。事故と減額との因果関係を証明する必要があります(賞与減額証明書など)。
必要な書類: 休業損害証明書(勤務先作成)、事故前3ヶ月分の給与明細、源泉徴収票、賞与減額証明書など。
2. 自営業者・フリーランス・個人事業主
収入の証明が給与所得者より複雑になる場合がありますが、弁護士基準では実態に応じた請求が可能です。
- 休業損害額 = 1日あたりの基礎収入 × 休業日数
- 1日あたりの基礎収入:
- 原則: 事故発生前年の確定申告所得額 ÷ 365日
- 確定申告所得額: 通常、売上高から必要経費を差し引いた「所得金額」(青色申告特別控除前の金額)を用います。
- 固定経費: 休業中でも支出しなければならない家賃、損害保険料、減価償却費などの固定経費は、所得額に加算して基礎収入と認められる場合があります。
- 確定申告をしていない場合: 帳簿、請求書、領収書、通帳の記録などで収入を立証する必要があります。立証が難しい場合は、賃金センサス(後述)を用いることもあります。
- 所得を低く申告していた場合: 原則として申告額が基準となりますが、実際の収入がそれを上回ることを客観的な資料で証明できれば、増額が認められる可能性もあります。ただし、立証は容易ではありません。
- 休業日数: 実際に事業を休止した、または通常通りに事業を行えなかった日数。
- 1日あたりの基礎収入:
- 代替労働者の費用: 休業中に自身の代わりとなる人を雇った場合、その費用(人件費)が休業損害として認められることがあります。
必要な書類: 確定申告書(控)、収支内訳書または青色申告決算書、総勘定元帳、請求書・領収書控え、所得証明書(課税証明書)など。
なお、個人事業主(自営業者・事業所得者)の休業損害につきましては、以下の計算機で簡単に算出できます。
3. 主婦・主夫(家事従事者)
専業主婦(主夫)や、パートなどと兼業で家事を行っている方も、家事労働には経済的な価値があるとして休業損害が認められます。
- 休業損害額 = 1日あたりの基礎収入 × 休業日数
- 1日あたりの基礎収入:
- 原則: 賃金センサス(厚生労働省「賃金構造基本統計調査」)の女性労働者の全年齢平均賃金 ÷ 365日
- 令和4年賃金センサスに基づく女性労働者全年齢平均年収は3,943,500円であり、1日あたり約10,804円となります(年によって変動します)。
- 男性の主夫の場合も、通常はこの女性の平均賃金を用います。
- 自賠責基準では原則6100円/日ですが、弁護士基準では上記のように基礎収入としては高くなります。休業率との関係で、弁護士基準総額でどれだけ高くなるかは計算が必要です。
- 休業日数: 事故によるケガで家事(炊事、洗濯、掃除、育児、介護など)が行えなかった日数。医師の指示(安静加療など)や、家事への支障の程度を考慮して判断されます。
- 1日あたりの基礎収入:
- 兼業主婦(主夫)の場合: パート収入などがある場合は、実際の収入額と上記の賃金センサスに基づく基礎収入額を比較し、どちらか高い方を基礎収入として計算します。
必要な書類: 家族構成がわかる書類(住民票、家事従事者確認事項などと題する家族構成を申告する書類)、兼業の場合は収入証明書類。
なお、主婦(主夫)(家事従事者)の休業損害につきましては、以下の計算機で簡単に算出できます。
4. アルバイト・パートタイマー
基本的な考え方は会社員と同様ですが、勤務日数が不規則な場合があるため、基礎収入の計算に注意が必要です。
- 休業損害額 = 1日あたりの基礎収入 × 休業日数、又は、時給×休業時間
- 1日あたりの基礎収入:
- 事故前3ヶ月間の収入合計額 ÷ 実労働日数 で計算します。暦日(90日)で割ると低くなる可能性があります
- ただし、勤務状況によっては90日で割る場合もあります。どちらが適切かは弁護士にご相談ください。
- 休業日数: 実際に治療のために休んだシフト日数。事故がなければシフトに入っていた蓋然性が高い日数も含まれる可能性があります(シフト表、勤務実績などから証明)。
- 1日あたりの基礎収入:
- 昇給・増収の可能性: 事故がなければ昇給や正社員登用、シフト増が見込まれた場合、それを立証できれば基礎収入の増額が認められる可能性があります。
必要な書類: 休業損害証明書(勤務先作成)、事故前3ヶ月~6ヶ月程度の給与明細、雇用契約書、シフト表など。
5. 無職者・失業者
原則として、事故当時に収入がなければ休業損害は発生しません。ただし、以下のような場合は例外的に認められる可能性があります。
- 就職内定者: 事故がなければ就職して収入を得ていた蓋然性が高い場合、その予定されていた給与額を基に休業損害が認められることがあります(内定通知書などで証明)。
- 具体的な就職活動中: 事故により就職活動が妨げられ、就労開始が遅れた場合、その間の損害が認められる可能性がありますが、立証のハードルは高いです。
6. 会社役員
役員報酬は、労働の対価としての「労務提供部分」と、利益配当としての「利益配当部分」が混在していると考えられます。休業損害の対象となるのは、原則として労務提供部分のみです。
- 判断基準: 会社の規模、役員の職務内容、報酬額、他の従業員の給与水準などを考慮して、労務提供部分がいくらに相当するかを個別に判断します。判断が難しく、争いになりやすい部分です。
- 証明: 定款、役員報酬規程、職務内容を示す資料などが必要となります。
職業別の計算は複雑な場合も多いため、正確な休業損害額を知るためには、弁護士基準に詳しい弁護士に相談することが最も確実です。
2-2. 【要注意】休業損害証明書は提出必須?虚偽申告(嘘)はばれるのかリスク解説

交通事故の休業損害を請求する際、特に給与所得者の場合は「休業損害証明書」という書類が重要になります。これは、被害者が勤務先に作成を依頼し、事故による休業日数や事故前の収入額などを証明してもらうための書類です。
休業損害証明書の重要性と提出の要否
- 給与所得者の場合: 原則として提出が必須です。保険会社はこの書類に基づいて休業日数や基礎収入を確認し、休業損害を計算します。この書類がないと、保険会社は休業の事実や収入額を客観的に確認できず、支払いを拒否したり、大幅に低い金額しか認めなかったりする可能性が高いです。
- 自営業者・主婦(夫)の場合: 自営業者は確定申告書や帳簿、主婦(夫)は賃金センサスが基準となるため、勤務先が発行する休業損害証明書は通常不要です。ただし、相手方保険会社からは、いわゆる一人親方などの場合、実際に休業していたことの確認のため、元請けが記入した休業損害証明書の提出を求められることがあります。また、兼業主婦(夫)が家事従事者としても休業損害を請求する場合でも、パート先での休業損害証明書の提出を求められることがあります(パートを休業していたのであれば、家事にも制限が出ていたと言いやすいです)。
虚偽申告(嘘)のリスク:「ばれる」可能性は高い
「少しでも多く賠償金をもらいたい」という気持ちから、休業日数を水増ししたり、収入を偽ったりする虚偽申告(嘘)を考えてしまう人もいるかもしれませんが、これは絶対にやめてください。保険会社は不正請求がないか常にチェックしており、虚偽申告がばれる可能性は高いです。
なぜばれるのか?
- 保険会社の調査能力: 保険会社は損害調査のプロであり、様々な方法で情報の裏付けを取ります。
- 源泉徴収票との照合: 休業損害証明書に記載された収入額と、別途提出を求められる源泉徴収票の金額が整合するか確認します。
- 勤務先への照会: 保険会社が直接、勤務先に電話などで問い合わせ、休業損害証明書の記載内容(休業日数、給与額など)が正しいか確認することがあります。
- 医療記録との整合性: 診断書やカルテなどの医療記録と、申告された休業期間・日数が、ケガの程度や治療内容と照らして不自然でないか確認します。
- 過去の請求履歴: 過去にも同様の事故で請求がないかなどを調査する場合もあります。
虚偽申告がばれた場合の重大なリスク
もし休業損害に関して嘘の申告が発覚した場合、以下のような深刻な事態を招きます。
- 詐欺罪(刑法246条)に問われる可能性:
- 保険金をだまし取ろうとしたとして、刑事責任を問われる可能性があります。詐欺罪は「10年以下の懲役」という重い罰則が定められています。実際に逮捕・起訴されるケースもあります。
- 保険金の返還請求:
- すでに受け取っていた保険金の返還を求められます。場合によっては、遅延損害金も加算されます。
- 以後の示談交渉が著しく困難に:
- 嘘をついたという事実により、被害者側の信頼は完全に失われます。保険会社は態度を硬化させ、休業損害以外の正当な損害賠償請求(慰謝料、治療費、交通費など)についても、非常に厳しい目で見てくるようになり、示談交渉が極めて難航します。最悪の場合、示談交渉が決裂し、裁判を起こさざるを得なくなることもあります。
- 弁護士の辞任:
- 弁護士に依頼している場合、依頼者による虚偽申告が発覚すれば、信頼関係が破壊されたとして弁護士が辞任することもあります。
適切な対応
交通事故の休業損害請求においては、正直であることが何よりも重要です。
- 医師の診断に基づき、実際に治療のために必要だった休業日数のみを申告する。
- 収入は、給与明細や確定申告書などの客観的な資料に基づいて正確に申告する。
- 休業損害証明書は、勤務先に事実に基づいて正確に記載してもらう。
- 不明な点や不安な点があれば、安易な自己判断はせず、必ず弁護士に相談する。
目先の利益のために嘘をつくことは、最終的に自分自身をさらに苦しめる結果にしかなりません。誠実な対応を心がけましょう。休業損害のみならず、通院交通費についても同様です。
2-3. 交通事故の休業補償はいつもらえる?支払いタイミングと「内払い」の活用

交通事故で仕事を休み、収入が途絶えてしまうと、当面の生活費の心配が出てきます。「休業補償(休業損害)はいつ支払われるのか?」というのは、被害者にとって切実な問題です。
原則的な支払いタイミング:示談成立後の一括払い
交通事故の損害賠償金(慰謝料、治療費、休業損害などすべてを含む)は、原則として、すべての損害額が確定し、加害者側(任意保険会社)との間で示談が成立した後に、一括で支払われます。
損害額が確定するのは、通常、以下のいずれかのタイミングです。
- ケガが完治した場合: 治療が終了した時点
- 後遺障害が残った場合: 症状固定の診断を受け、後遺障害等級が確定した時点
つまり、治療が長引いたり、後遺障害の認定に時間がかかったりすると、最終的な賠償金を受け取るまでに数ヶ月、場合によっては1年以上かかることもあります。
治療中の生活費をどうするか?:「内払い」制度の活用
示談成立まで賠償金を受け取れないとなると、治療中の生活に困窮してしまう可能性があります。そこで活用したいのが、保険会社による「内払い(うちばらい)」または「仮払い(かりばらい)」という扱いです。
- 内払いとは:
- 示談成立前に、賠償金の一部を先行して支払ってもらう制度です。
- 治療費や通院交通費だけでなく、休業損害も内払いの対象となります。
- あくまで賠償金の前払いであり、最終的に示談で確定した総額から、内払いされた金額は差し引かれます。いわば、貯金を先に引きだすようなものです。
- 内払いのメリット:
- 示談成立を待たずに、当面の治療費の支払いや生活費の補填に充てることができます。経済的な不安を軽減し、安心して治療に専念しやすくなります。そもそも、交通事故に遭うなど誰も思っていませんから、生活が立ち行かなくなってしまう人も多いです。
- 内払いの手続き:
- 休業損害の内払いを希望する場合は、加害者側の任意保険会社にその旨を申し出ます。
- 通常、毎月(あるいは一定期間ごと)に、その期間の休業損害証明書や給与明細などを提出し、保険会社が内容を確認した上で、該当期間分の休業損害額が支払われます。
- 支払いまでには、書類提出後、通常1~2週間程度かかることが多いようです(保険会社や状況によります)。
内払いを受ける際の注意点
- 内払いは義務ではない: 保険会社に内払いの義務はありません。しかし、被害者の生活困窮を防ぐ観点から、多くの保険会社は要求すれば一定程度は対応してくれることが多いです。ただし、事故状況や過失割合に争いがある場合などは、支払いを拒否されたり、支払われる金額が減額されたりすることもあります。また、拒否されれば、当然内払いは行われません。
- 自賠責保険への被害者請求: 任意保険会社が内払いに応じない場合や、対応が遅い場合、被害者は自賠責保険に対して直接、損害賠償額(傷害部分の上限120万円まで)を請求することができます(被害者請求)。これを利用して、治療費や休業損害を受け取ることもできますが、被害者請求(本請求)の審査には1か月程度は見ておくべきです。
- 金額の確認: 内払いされる休業損害額が、どの基準(自賠責基準か任意保険基準か)で計算されているか確認しましょう。もし低い基準で計算されていても、最終的な示談交渉で弁護士基準との差額を請求することは可能です。むしろ、内払の段階では低い金額しか提示されません。
- 示談への影響: 内払を受けた分は、当然賠償額から控除されます。ただ、内払いを受けたからといって、必ずしもその保険会社の提示する最終的な示談額に同意しなければならないわけではありません。納得できない場合は、弁護士に相談して弁護士基準での交渉・解決を目指しましょう。
交通事故で休業損害が発生し、当面の生活に不安がある場合は、遠慮なく加害者側の保険会社に内払いの相談をしてみましょう。
スムーズに進まない場合や、提示される金額に疑問がある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
2-4. 弁護士費用特約があれば実質0円!弁護士に依頼するメリットと依頼手順

交通事故の休業損害を弁護士基準で請求したいと思っても、「弁護士に頼むと費用が高そう…」とためらってしまう方は少なくありません。しかし、ご自身やご家族が加入している自動車保険などに「弁護士費用特約」が付いていれば、その心配はほとんど不要になります。
弁護士費用特約とは?
- 自動車保険や火災保険、傷害保険などに付帯できるオプション(特約)の一つです。
- 交通事故の被害者になった場合に、相手方との示談交渉や訴訟などを弁護士に依頼する際の弁護士費用(法律相談料、着手金、報酬金、実費など)を保険会社が負担してくれる制度です。
- 補償上限額: 一般的に、弁護士費用は合計300万円まで、法律相談料は10万円まで補償されるプランが多いです。
- 個人の交通事故案件で弁護士費用が300万円を超えるケースは稀であり、多くの場合、自己負担なく弁護士に依頼することが可能です。
弁護士費用特約を使うメリット
- 弁護士費用の自己負担が実質0円: 最大のメリットです。費用の心配なく、専門家である弁護士に依頼できます。
- 保険の等級に影響しない: この特約を使っても、自動車保険の等級が下がったり、翌年の保険料が上がったりすることはありません。(※ただし、弁護士費用特約に加え、対物保険や車両保険を使用したことによって、等級に影響することはあります)
- 賠償金の大幅増額が期待できる: 弁護士が介入し、弁護士基準で交渉することで、保険会社提示額(自賠責基準や任意保険基準)から大幅に賠償金が増額するケースも珍しくありません。休業損害についても、適正な基礎収入や休業日数が認められやすくなります。
- 精神的・時間的負担の軽減: 煩雑でストレスの多い保険会社との交渉や、書類作成などをすべて弁護士に任せられます。被害者は治療や仕事復帰に専念できます。
- より有利な解決へ: 法律の専門家が、証拠収集、法的主張、交渉戦略などを駆使し、被害者にとって最も有利な解決を目指します。
利用できる範囲は?
弁護士費用特約は、保険契約者本人だけでなく、以下の範囲の人が利用できる場合があります(詳細はご自身の保険約款をご確認ください)。
- 記名被保険者(契約車両を主に運転する人)
- その配偶者
- 記名被保険者または配偶者の同居の親族
- 記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子
- 契約車両の搭乗者(友人・知人など)
- ※歩行中や自転車乗車中の事故でも利用できる場合があります。
弁護士費用特約を使って弁護士に依頼する手順
- 特約の有無と利用条件の確認:
- ご自身やご家族(配偶者、同居親族など)が加入している自動車保険、火災保険などの保険証券を確認し、弁護士費用特約が付帯しているか、利用条件(対象となる事故の種類など)を確認します。不明な場合は保険会社や代理店に問い合わせましょう。
- 弁護士を探して相談:
- 交通事故案件、特に休業損害や弁護士基準に詳しい弁護士を探し、法律相談を申し込みます。
- 相談の際には、「弁護士費用特約を利用したい」旨を明確に伝えてください。多くの弁護士事務所では、初回相談は無料で行っています。
- 委任契約の締結:
- 相談の結果、依頼したい弁護士が決まれば、委任契約を締結します。
- 契約書には、弁護士費用特約を利用する旨を明記してもらうこともできます。
- 保険会社への連絡:
- 弁護士に依頼したこと、および弁護士費用特約を利用することを、ご自身が加入している保険会社(特約が付いている保険の会社)に連絡します。通常、依頼した弁護士が代行して連絡してくれます。
- 保険会社から、特約利用に必要な書類(委任状、委任契約書の写しなど)の提出を求められる場合があります。
- 弁護士による交渉・解決:
- あとは弁護士が、加害者側の保険会社との示談交渉や、必要に応じて訴訟などの手続きを進めてくれます。
- 弁護士費用は、事件解決後に弁護士から保険会社へ直接請求され、支払われます(上限額の範囲内)。
特約がない場合でも諦めないで
もし弁護士費用特約に加入していなくても、諦める必要はありません。
- 着手金無料・成功報酬制: 初期費用である着手金を無料とし、賠償金が増額した場合にのみ、その増額分から報酬を支払う「成功報酬制」を採用している事務所もあります。これなら、手元にお金がなくても依頼しやすくなります。ただし、結局高くつくこともありますので、注意が必要です。
- 法テラスの利用: 資力の乏しい方は、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を利用して、弁護士費用の立替え払いを受けられる場合があります(利用には収入・資産要件あり)。
交通事故の休業損害で適正な補償を得るためには、弁護士への依頼が非常に有効です。弁護士費用特約があれば、費用負担なくそのメリットを最大限に享受できます。まずは特約の有無を確認し、専門家への相談を検討しましょう。
2-5. 自分でできる?休業損害計算ツールの活用法と弁護士基準との比較

最近では、インターネット上で交通事故の休業損害額を簡易的に計算できる「休業損害計算ツール」を提供しているウェブサイト(弁護士事務所や損害保険関連サイトなど)が見られます。こうしたツールは手軽に利用でき、おおよつの目安を知るのに役立ちます。
休業損害計算ツールのメリットと活用法
- 手軽さ: 職業、年収(または日額)、休業日数などの情報を入力するだけで、休業損害の概算額をすぐに知ることができます。
- 目安の把握: 保険会社から提示された金額が妥当なのか、あるいは弁護士基準で請求すればどれくらい増額しそうか、大まかな見当をつけるのに役立ちます。
- 基準比較: ツールによっては、自賠責基準、任意保険基準(推定)、弁護士基準それぞれの計算結果を比較表示してくれるものもあり、基準による金額差を視覚的に理解しやすくなっています。
当サイトでも自営業者と主婦(主夫)の休業損害の計算シミュレーターを作成していますので、再掲致します。
休業損害計算ツールは、交通事故の休業損害について大まかなイメージを掴むための第一歩としては有用です。
弁護士基準に基づいた正確な休業損害額を知り、保険会社に対して法的な根拠を持って請求するためには、必ず交通事故に詳しい弁護士に相談し、個別の状況に合わせた詳細な計算と評価を受けることが不可欠です。
特に、保険会社の提示額に疑問がある場合や、計算ツールでの概算額と大きく異なる場合は、早めに専門家の意見を聞くことを強くおすすめします。
2-6. まとめ:交通事故の休業損害は弁護士基準での請求を検討

交通事故によるケガで仕事を休まざるを得なくなった場合、その間の収入減を補償する「休業損害」は、被害者の生活を守る上で非常に重要です。しかし、その金額はどの基準で計算するかによって大きく左右されます。
本記事で解説してきた重要なポイントをまとめます。
- 休業損害は弁護士基準で請求すべき: 自賠責基準や任意保険基準に比べ、事故前の実収入に基づき計算される弁護士基準(裁判所基準)が最も高額になる可能性が高く、正当な補償額に近いです。
- 慰謝料とは別物: 休業損害(収入減の補填)と慰謝料(精神的苦痛への賠償)は異なる損害項目であり、それぞれ別々に請求できます。混同しないようにしましょう。
- 職業に応じた正確な計算が必要: 会社員、自営業者、主婦(夫)、アルバイトなど、職業や収入形態によって基礎収入の計算方法が異なります。弁護士基準では、それぞれの実態に合わせた計算を行います。
- 補償対象: 補償対象となるのは原則として症状固定日までの必要な休業期間です。
- 有給休暇使用分も請求可能: 事故のためにやむなく有給休暇を使った場合も、その日数分を休業損害として請求できます。
- 虚偽申告(嘘)は絶対NG: 休業日数や収入について嘘の申告をすると、詐欺罪に問われたり、賠償金全額の返還を求められたりするリスクがあります。正直な申告が鉄則です。
- 弁護士費用特約を活用しよう: 特約があれば、自己負担なく弁護士に依頼できます。保険等級にも影響しません。使わない手はありません。
- 迷ったら弁護士に相談を: 保険会社の提示額に疑問がある、計算方法がわからない、交渉がうまくいかないなど、交通事故の休業損害に関する悩みは、弁護士基準に詳しい専門家である弁護士に相談するのが最善の解決策です。
交通事故の被害に遭われた方が、休業損害で損をしないためには、弁護士基準の存在を知り、その基準に基づいて請求することが不可欠です。特に弁護士費用特約に加入されている方は、費用負担なく専門家のサポートを受けることができます。
一人で悩まず、まずは交通事故に強い弁護士の無料相談などを利用して、ご自身の状況における適切な休業損害額や今後の進め方についてアドバイスを受けてみてください。それが、正当な補償を獲得し、安心して治療と生活再建に専念するための第一歩となるはずです。














