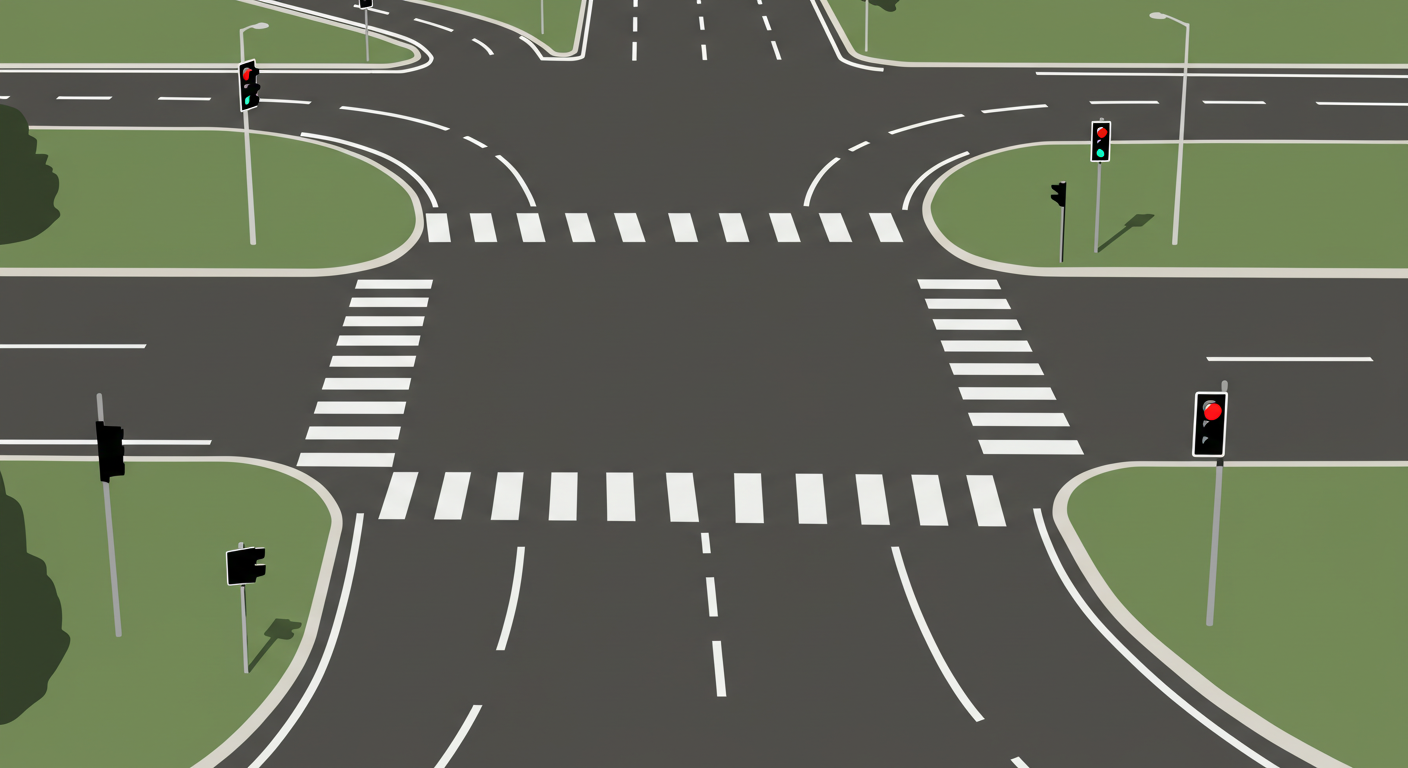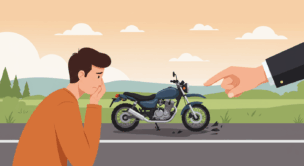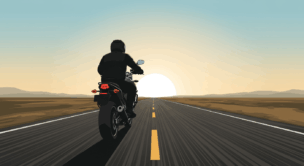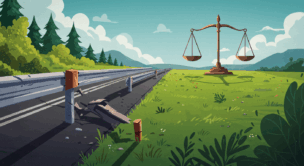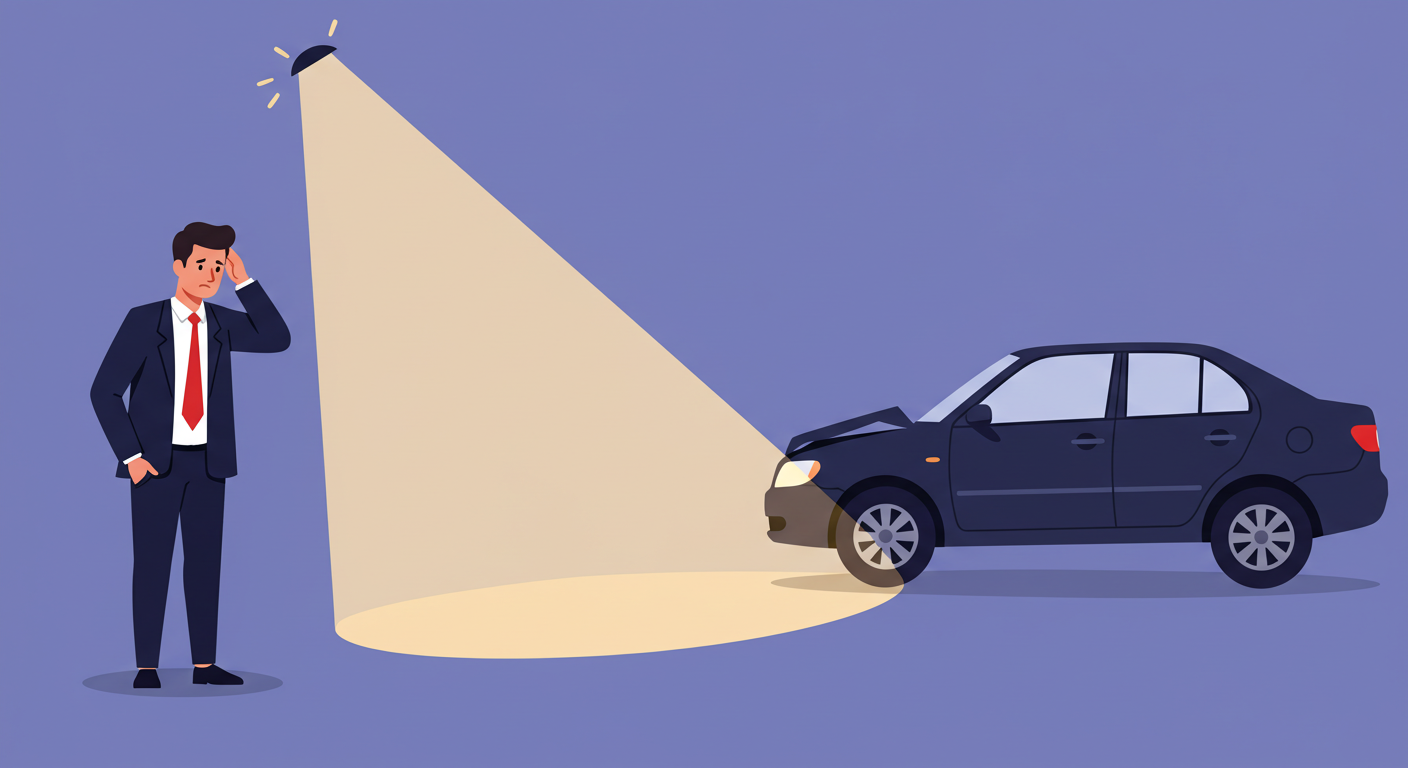「自動車保険の弁護士特約ってバイク事故にも使えるの?」「バイク保険に弁護士特約を付けるのは、いらないって本当?」「弁護士費用特約が重複している場合、違う保険会社や他社契約だとどうなるの?」など、車とバイク、両方をお持ちの方は、弁護士費用特約について様々な疑問をお持ちではないでしょうか。
特に、弁護士特約が車とバイクで重複している場合のメリットや、家族が違う車に乗っている場合の適用範囲、さらにはファミリーバイク特約との関係で弁護士特約が使えないケースがあるのか、バイク保険の弁護士特約はいくらくらいで、本当に必要かなど、気になる点は多いはずです。この記事では、そんなあなたの疑問を解消し、弁護士費用特約を賢く活用するための情報を分かりやすく解説します。
この記事の主要なポイント
- 弁護士費用特約の基本的な仕組みと、車とバイク両方における重要性
- 自動車保険の特約がバイク事故に使えるか
- 弁護士費用特約の家族への適用範囲と、重複加入のメリット・デメリット
- バイク保険における弁護士特約の必要性、費用、そして「いらない」と言われる理由の検証
- ファミリーバイク特約と弁護士費用特約の関係性、使えないケースの有無
- 弁護士費用特約が利用できない主なケースと、スムーズな利用のための注意点