
突然の交通事故、そして告げられた「過失割合は8対2です」。さらに追い打ちをかけるように、愛車は廃車レベルの損傷…。こんな時、「事故で廃車にされたのに、なぜ自分が2割も責任を負うの?」「事故で廃車になった場合、修理費も出ないって本当?」「事故の廃車でいくらもらえるんだろう…」「事故 8対2での買い替え費用はちゃんと補償されるの?」と、不安と疑問で頭がいっぱいになるのは当然です。
特に、相手の保険会社から提示される事故8対2の示談金 相場は、本当に適正なのか疑わしいと感じる方も多いでしょう。「事故で廃車になったのは相手が悪いのに、なぜこんなに少ない金額なの?」と納得いかない気持ちはよく分かります。
もしあなたが、事故で廃車となり買い替えを余儀なくされ、事故での廃車や、相手の保険会社との交渉にストレスを感じているなら、この記事は必読です。
特に、過失割合が事故10対0ではなく8対2とされた場合、適切な知識なく示談を進めると、本来受け取れるはずの賠償金よりも大幅に低い金額で合意してしまうリスクがあります。
この記事では、事故 8対2で廃車という困難な状況で、あなたが受け取るべき正当な賠償金を最大限に獲得するための具体的な方法を、弁護士監修のもと徹底解説します。
特に、多くの方が加入している「弁護士費用特約」を活用すれば、自己負担なく専門家である弁護士のサポートを受け、不利な状況を覆せる可能性も十分にあります。正しい知識を身につけ、あなたの権利を守りましょう。
この記事の主要なポイント
この記事を読むことで、以下の点が明確になります。
- 過失割合8対2の意味と影響: なぜ8対2になるのか、賠償金にどう影響するのか。
- 廃車の基準: 「物理的全損」と「経済的全損」の違い、あなたの車がどちらに該当するのか。
- 賠償金の相場と内訳: 8対2事故での示談金・慰謝料の相場、車両本体以外に請求できる費用(買替諸費用、代車費用など)。
- 請求できる項目: 廃車時に具体的に何をいくら請求できるのか。
- 10対0との違い: 8対2と10対0で賠償額がどれだけ変わるのか、10対0を主張できるケース。
- 保険会社の対応と交渉術: 相手保険会社からの提示にどう対応すべきか、交渉のポイント。
- 過失割合への対処法: 8対2の割合に納得できない場合に取るべき行動。
- 保険の活用法: 自分の車両保険と相手の対物保険、弁護士費用特約の効果的な使い方。
- 弁護士相談のメリット: なぜ弁護士に相談すべきなのか、依頼するタイミングと効果。
目次
1.事故8対2で廃車!基礎知識と交渉術

交通事故で保険会社から「過失割合8対2」、そして工場から「車は廃車にした方がいい」と告げられたら、多くの方は大きなショックを受けるでしょう。8対2という過失割合は、賠償金の額に大きな影響を与えます。このセクションでは、まず過失割合8対2の意味、廃車の判断基準、そして最も気になる賠償金の相場や請求できる項目について、基本的な知識を分かりやすく解説します。相手保険会社との交渉を有利に進めるためにも、まずはこれらの基礎をしっかり押さえましょう。
- 1-1: 過失割合8対2とは?事故におけるあなたの立場と権利
- 1-2: 事故で廃車と判断されるレベル:「物理的全損」と「経済的全損」の違い
- 1-3: 事故8対2での廃車:示談金相場といくらもらえるか
- 1-4: 事故で廃車・買い替えになった場合に請求できる損害賠償の項目
- 1-5: 事故8対2と10対0の違い:廃車時の賠償金はどれくらい変わる?
- 1-6: 「事故で廃車にされた!」相手の保険から最大限の補償を得る方法
- 1-7: 事故8対2の過失割合に納得できない場合の対処法
1-1: 過失割合8対2とは?事故におけるあなたの立場と権利
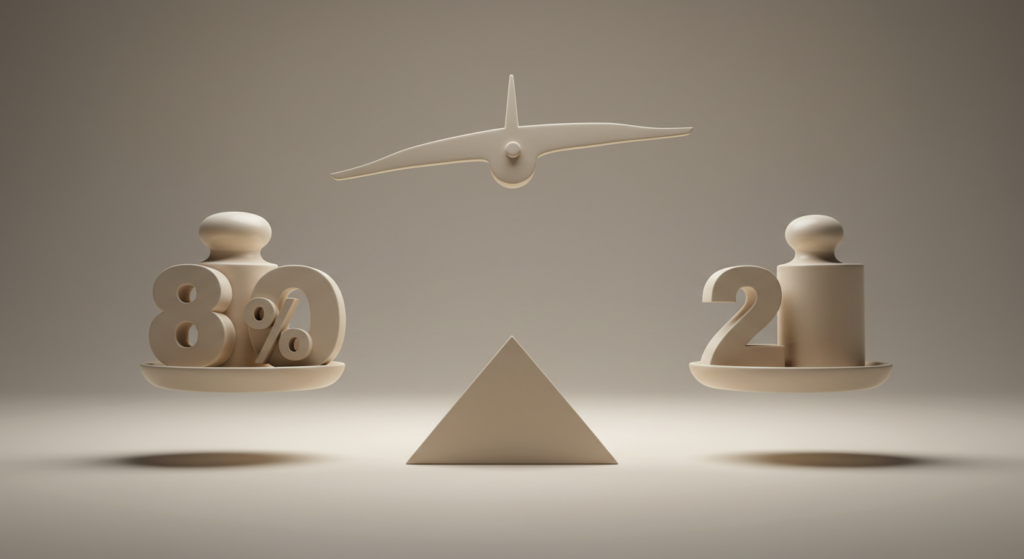
過失割合8対2の意味
過失割合「8対2」(こちらが8で、相手が2)とは、発生した交通事故の責任の割合が、加害者(相手方)に80%、被害者(あなた)に20%あると判断されることを意味します。これは、事故の状況において、あなたにも何らかの不注意(前方不注意など)があったとされた結果です。
賠償金への影響(過失相殺)
この8対2という割合は、損害賠償額を算定する上で非常に重要です。なぜなら、「過失相殺」というルールが適用されるからです。
- あなたの損害に対する補償: あなたが受けた損害(車の修理費や廃車費用、治療費、慰謝料など)の総額のうち、相手方が負担するのは80%となります。残りの20%は、あなた自身の過失分として自己負担、もしくはご自身の保険でカバーする必要があります。
- 相手の損害に対する負担: 同時に、相手方が受けた損害(相手車両の修理費など)の総額のうち、あなたは20%を負担する義務を負います(対人・対物保険があれば使うことができます)。
具体例:
- あなたの損害額合計:300万円
- 相手の損害額合計:100万円
この場合、
- あなたが相手から受け取れる金額:300万円 × 80% = 240万円
- あなたが相手に支払う金額:100万円 × 20% = 20万円
- 最終的にあなたが受け取れる金額(相殺後):240万円 – 20万円 = 220万円(相手の損害については、対人・対物保険で支払いこともできます)
このように、8対2の過失割合では、ご自身の損害が全額補償されないだけでなく、相手の損害の一部も負担する必要があるため、最終的に手元に残る金額は大きく減ってしまうのです。
あなたの権利
たとえ2割の過失があるとされても、あなたは加害者に対して損害賠償を請求する権利を持っています。重要なのは、提示された「8対2」という過失割合や損害額が本当に妥当なものかをしっかりと見極めることです。保険会社が提示する過失割合は、必ずしも絶対的なものではありません。納得できない場合は、客観的な証拠に基づいて交渉し、割合を変更できる可能性もあります。
1-2: 事故で廃車と判断されるレベル:「物理的全損」と「経済的全損」の違い

事故に遭った車が「廃車」と判断される場合、それは単に「もう乗れない」という状態だけでなく、保険金の支払いに関わる明確な基準に基づいています。廃車と判断される主なケースは「物理的全損」と「経済的全損」の2つです。どちらに該当するかによって、受け取れる賠償の内容が変わることもあります。
1. 物理的全損 (ぶつりてきぜんそん)
- 定義: 事故による損傷が激しく、自動車としての主要な骨格部分(フレームなど)が著しく変形・破損し、物理的・技術的に修理することが不可能な状態を指します。
- 具体例: 車が炎上した、水没した、車体がくしゃくしゃに潰れて原型をとどめていない、など。
- 特徴: 修理自体が不可能であるため、廃車にする以外の選択肢がほぼありません。
2. 経済的全損 (けいざいてきぜんそん)
- 定義: 車の損傷自体は修理可能であるものの、その修理費用が、事故発生時の車両の時価額(市場価値)と買替諸費用(車を買い替える際にかかる登録費用など)の合計額を上回ってしまう状態を指します。
- 具体例: 年式の古い車(時価額が低い)が事故に遭い、バンパー交換や板金塗装などの修理費用のほうが高くついてしまうケース。
- 特徴:
- 修理は可能だが、経済的な観点から見て「修理するよりも同等の車に買い替えた方が合理的」と判断されます。
- 保険会社(特に相手方の対物賠償保険)は、原則として車両の時価額+買替諸費用までしか賠償金を支払いません。たとえあなたが「愛着があるので修理したい」と希望しても、修理費全額が補償されるわけではない点に注意が必要です。
【全損の種類と判断基準・賠償の考え方】
| 種類 | 判断基準 | 賠償の考え方・上限 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 物理的全損 | 事故により、物理的・技術的に修理が不可能な状態。 | 原則として事故当時の車両時価額 + 買替諸費用が賠償上限。 | 車が完全に破壊されている状態。修理という選択肢がない。 |
| 経済的全損 | 修理費用が「車両の時価額 + 買替諸費用」を上回る状態。 | 原則として事故当時の車両時価額 + 買替諸費用が賠償上限。 | 修理は可能だが、経済合理性から見て買い替えた方が妥当と判断される状態。 |
| 分損(修理) | 修理費用が「車両の時価額 + 買替諸費用」を下回る状態。 | 原則として実際にかかった修理費用が賠償上限(ただし時価額が上限となる場合もある)。 | 修理して乗り続けることが経済的にも合理的と判断される状態。 |
「事故 廃車レベル」とは?
一般的に交通事故において、廃車レベルと言われるのは、上記の物理的全損または経済的全損に該当するほどの大きな損傷を負った状態を指します。特に経済的全損は、見た目の損傷がそれほど酷くなくても、車の価値によっては該当する可能性があるため注意が必要です。もちろん、経済的全損であっても、賠償が事故当時の車両時価額 + 買替諸費用の限度にとどまるだけであって、修理してもいいし、実際に廃車にする必要はありません。
保険会社から「経済的全損です」と言われた場合、その時価額の算定根拠や修理費用の見積もりが妥当なものかを確認することが重要になります。
1-3: 事故8対2での廃車:示談金相場といくらもらえるか

事故の過失割合が8対2で、かつ愛車が廃車になってしまった場合、受け取れる示談金(賠償金)の相場はいくらになるのでしょうか。ここでは、基本的な計算方法と具体例、そして慰謝料の考え方について解説します。
示談金の基本的な計算方法
過失割合が8対2の場合、相手方から受け取れる示談金(賠償金)の基本的な考え方は以下の通りです。
受け取れる金額 = (あなたの総損害額 × 相手の過失割合 80%) – (相手の総損害額 × あなたの過失割合 20%)
- あなたの総損害額: 廃車になった車両の損害(時価額+買替諸費用)、代車費用、レッカー代、治療費(人身事故の場合)、休業損害(人身事故の場合)、慰謝料(人身事故の場合)などを合計した金額。
- 相手の総損害額: 相手車両の修理費や治療費など。
具体例で計算してみよう
仮に以下のような状況だったとします。
- あなたの損害:
- 車両損害(時価額+買替諸費用):80万円
- 代車費用:15万円
- レッカー代:5万円
- (物損のみで人身損害はなしとする)
- あなたの総損害額合計:100万円
- 相手の損害:
- 車両修理費:50万円
- 相手の総損害額合計:50万円
- 過失割合: あなた:相手 = 2:8
この場合の計算は以下のようになります。
- 相手から受け取れる損害賠償額:
100万円 (あなたの損害) × 80% = 80万円 - あなたが相手に支払う損害賠償額:
50万円 (相手の損害) × 20% = 10万円 - 最終的に受け取れる示談金(相殺後):
80万円 – 10万円 = 70万円
つまり、このケースでは、あなたの損害は100万円発生していますが、過失割合8対2のため、最終的に受け取れる金額は70万円となります(ただし、これは相手の損害につき、対物保険を使わない場合です。対物保険を使う場合、相手に支払う10万円は自分の保険会社から支払われます。)。「事故 廃車 いくらもらえる?」という疑問に対しては、このように過失割合と双方の損害額によって大きく変動すると理解しておく必要があります。
慰謝料について(人身事故の場合)
上記の例は物損事故(車や物だけの損害)の場合ですが、もしあなたが事故で怪我をした場合(人身事故)は、慰謝料も請求できます。慰謝料には主に以下の種類があります。
- 入通院慰謝料: 怪我の治療のために入院や通院をしたことに対する精神的苦痛への賠償。
- 後遺障害慰謝料: 治療を続けても症状が改善せず、後遺障害等級が認定された場合の精神的苦痛への賠償。
- 死亡慰謝料: 被害者が亡くなられた場合の遺族の精神的苦痛への賠償。
これらの慰謝料も、過失割合8対2の場合は満額の80%しか受け取れません。例えば、弁護士(裁判)基準で算定した入通院慰謝料が100万円だったとしても、8対2の事故では80万円に減額されてしまいます。
【参考:弁護士基準による入通院慰謝料(むちうち等、軽傷の場合)の例】
| 通院期間 | 慰謝料額(過失0の場合) | 8対2事故の場合 (×80%) |
|---|---|---|
| 1ヶ月 | 19万円 | 15.2万円 |
| 3ヶ月 | 53万円 | 42.4万円 |
| 6ヶ月 | 89万円 | 71.2万円 |
※上記はあくまで目安であり、実際の通院日数や怪我の程度により変動します。
相場の注意点
保険会社が最初に提示してくる示談金の額は、上記の計算方法や弁護士基準よりも低い「任意保険基準」や「自賠責基準」で計算されていることが多く、特に慰謝料額は低く抑えられがちです。提示された金額が適正な「相場」なのかどうか、安易に鵜呑みにせず、専門家(弁護士)に相談することをお勧めします。
1-4: 事故で廃車・買い替えになった場合に請求できる損害賠償の項目

愛車が事故で廃車(全損)と判断された場合、加害者側(の保険会社)に対して具体的にどのような損害賠償を請求できるのでしょうか?車両本体の価値だけでなく、買い替えに伴う諸費用なども請求できる可能性があります。ただし、過失割合が8対2の場合は、請求できる総額から2割が減額(過失相殺)される点に注意が必要です。
主な請求項目
廃車(全損)の場合に請求できる主な損害項目は以下の通りです。
- 車両本体の損害(物損):
- 事故当時の車両時価額: 全損の場合、修理費ではなく、事故発生時点での車の市場価値(時価額)が賠償の基準となります。時価額は、同じ車種・年式・型式、同程度の走行距離や使用状況の車を中古車市場で取得するのに必要な価格(再調達価格)を参考に算定されます。一般的には、中古車情報誌「オートガイド自動車価格月報(レッドブック)」や、カーセンサー・グーネットでの市場価格などが基準とされますが、掲載されていない古い車種の場合は算定が難しくなることもあります。
- スクラップ代金(売却代金)の控除: 廃車にする場合でも、鉄くずとしての価値(スクラップ代)や、部品取りとしての価値が残っている場合があります。その場合、時価額からスクラップ代金等を差し引いた金額が賠償額となることがあります(損益相殺)。
- 買替諸費用:
- 定義: 廃車になった車と同等の車に買い替えるために、通常必要となる諸費用のことです。
- 具体的な費用例:
- 自動車取得税
- 自動車重量税(一部)
- 消費税(車両本体価格に含まれない部分)
- 登録、車庫証明、納車などの手続きにかかる法定費用やディーラー手数料(相当額)
- 廃車になった車の廃車費用
- 注意点: どこまでが「通常必要」と認められるかは、保険会社との交渉次第となる部分もあります。数万円~10万円程度になることも多く、請求しないのはもったいないです。なお、実際に買い替える必要はありません。見積だけでOKです。
- 代車費用:
- 定義: 車が使用不能になった期間(修理期間または買い替えに必要な相当期間)、代わりに利用したレンタカーなどの費用です。
- 認められる期間: 全損(廃車)の場合は、買い替えに必要な相当期間とされます。一般的には2週間程度とされることが多いですが、新車の納車待ちなど特別な事情があれば、それ以上の期間が認められる可能性もあります。ただし、漫然と長期間借り続けることは認められません。
- 注意点: 公共交通機関で代替可能な場合や、他に利用できる車がある場合などは、請求が認められないこともあります。また、借りる車種も、事故車両と同等クラスのものに限られるのが原則です。
- レッカー代・保管料など:
- 事故現場から修理工場や保管場所までのレッカー移動費用。
- 車両を一時的に保管するための費用(必要かつ相当な範囲に限る)。
- 積載物の損害:
- 事故によって車に積んでいた物が壊れた場合、その物の時価額相当額。ただし、高額品や事業用の物品などは別途証明が必要になることがあります。
- 評価損(格落ち損害):
- これは主に分損の場合に問題となる損害です。
- その他:
- 休車損害(事業用車両の場合)
- 弁護士費用(弁護士に依頼した場合の着手金・報酬金の一部)など。ただし、訴訟まで行かないと困難です。
請求のポイント(8対2の場合)
上記の項目を合計したものが「あなたの総損害額」となりますが、過失割合が8対2の場合、相手に請求できるのはこの総額の80%です。残りの20%は自己負担となります。
「事故 廃車 いくらもらえるか」を正確に把握するためには、これらの請求可能な項目を漏れなくリストアップし、それぞれの金額(特に時価額や買替諸費用)の根拠を明確にしておくことが重要です。保険会社は、買替諸費用を積極的に案内してくることはありません。保険会社から提示された金額に納得できない場合は、その算定根拠を詳しく確認し、必要であれば反論や交渉を行う必要があります。
1-5: 事故8対2と10対0の違い:廃車時の賠償金はどれくらい変わる?
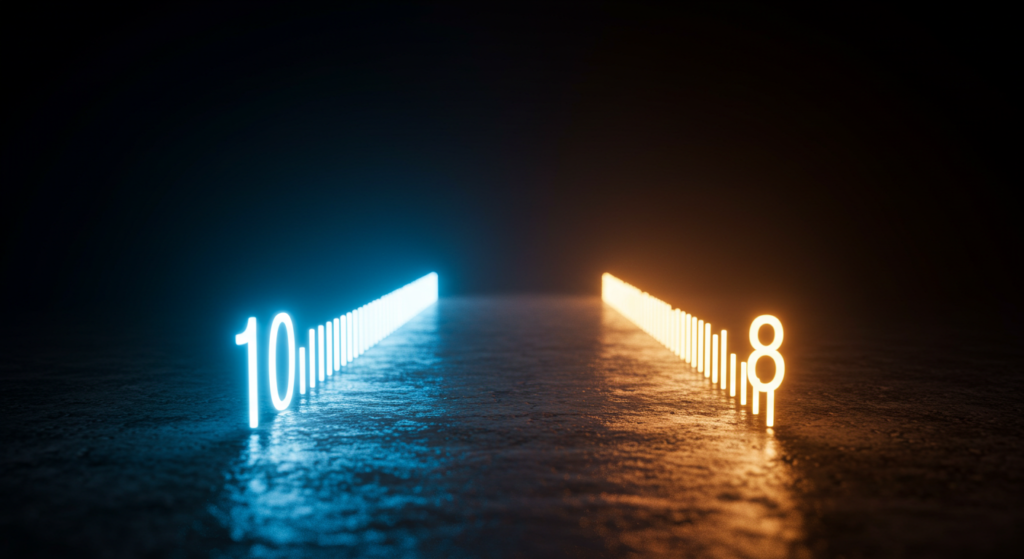
交通事故の過失割合は、賠償金の額に直接的な影響を与えます。特に「8対2」と「10対0(ゼロ)」では、受け取れる金額に大きな差が出ます。愛車が廃車になったケースで、具体的にどれくらい変わるのかを見ていきましょう。
過失割合10対0とは?
過失割合10対0とは、交通事故の責任が100%相手方にあると判断されるケースです。つまり、被害者であるあなたには全く過失(不注意)がない状況を指します。
10対0になりやすい代表的なケース
- 停車中の追突: 信号待ちや渋滞で完全に停車しているところに、後ろから追突された場合。
- センターラインオーバー: 相手車両がセンターラインをはみ出してきて衝突した場合。
- 赤信号無視: あなたが青信号で交差点に進入したところ、赤信号を無視した相手車両に衝突された場合。
- 相手の一方的な逆走
これらのケースでは、通常、被害者側は事故を避けることが極めて困難であるため、過失がない(0%)と判断される可能性が高いです。
賠償金額の差:8対2 vs 10対0
過失割合が違うと、賠償金の計算方法(特に過失相殺)が異なるため、最終的に受け取れる金額が変わってきます。
【設例】
- あなたの損害額合計(車両時価額+買替諸費用+代車費用など):200万円
- 相手の損害額合計(相手車両修理費など):50万円
ケース1:過失割合 8対2 (あなた 2割、相手 8割)
- あなたが相手から受け取れる金額:200万円 × 80% = 160万円
- あなたが相手に支払う金額:50万円 × 20% = 10万円
- 最終的な受取額(相殺後):160万円 – 10万円 = 150万円
ケース2:過失割合 10対0 (あなた 0割、相手 10割)
- あなたが相手から受け取れる金額:200万円 × 100% = 200万円
- あなたが相手に支払う金額:50万円 × 0% = 0円
- 最終的な受取額:200万円 – 0円 = 200万円
比較結果
| 過失割合 | あなたの受取額 (相手から) | あなたの支払額 (相手へ) | 最終的な受取額 |
|---|---|---|---|
| 8対2 | 160万円 | 10万円 | 150万円 |
| 10対0 | 200万円 | 0円 | 200万円 |
| 差額 | -40万円 | +10万円 | -50万円 |
この設例では、過失割合が8対2か10対0かで、最終的に受け取れる賠償金額に50万円もの差が出ることがわかります。
なぜ差が出るのか?
- 過失相殺の有無: 10対0の場合は過失相殺がないため、自身の損害額全額を受け取れます。8対2では自身の損害額の8割しか受け取れません。
- 相手損害の負担有無: 10対0の場合は相手の損害を負担する必要がありません。8対2では相手損害の2割を負担する必要があります。
ポイント
保険会社から最初に「8対2です」と提示されても、事故状況によっては「10対0」を主張できる可能性があります。もし「自分には全く過失がないはずだ」と感じる場合は、安易に8対2を受け入れず、ドライブレコーダーの映像や客観的な証拠をもとに、10対0(またはより有利な過失割合)を主張・交渉することが、正当な賠償金を得るために非常に重要になります。
1-6: 「事故で廃車にされた!」相手の保険から最大限の補償を得る方法

「事故で廃車にされた!」「事故 廃車 相手が悪いのに、十分な補償が受けられないのはおかしい!」―― このような憤りを感じるのは当然です。相手に大きな過失がある(例えば8対2の「8」の部分)にも関わらず、相手の保険会社(任意保険の対物賠償保険)からの提示額が予想外に低いことがあります。ここでは、事故で廃車になった際に、相手の保険から最大限の補償を引き出すためのポイントを解説します。
1. 相手の保険(対物賠償保険)の基本
- 補償範囲: 相手の対物賠償保険は、あなたの車の損害(修理費または時価額)、代車費用、休車損害などを、相手の過失割合に応じて補償します。
- 支払いの上限:
- 分損の場合: 原則として修理費用が上限です。
- 廃車(全損)の場合: 原則として事故当時の車両時価額+買替諸費用が上限となります。たとえ修理費用が時価額を上回っても(経済的全損)、通常は時価額+買替諸費用までしか支払われません。
2. なぜ提示額が低くなることがあるのか?
相手保険会社からの提示額が低い場合、以下のような理由が考えられます。
- 時価額の低すぎる算定: 特に古い車や希少車の場合、レッドブックや減価償却等を根拠に、市場の実勢価格よりも低い時価額を提示されることがあります。
- 買替諸費用の過小評価: 認められるべき諸費用の一部が含まれていなかったり、金額が低く見積もられたりするケースです。
- 過失割合の主張: あなたの過失割合を不当に高く見積もることで、支払う賠償額を減らそうとする場合があります(例:本当は9対1なのに8対2と主張する)。
- 保険会社の基準: 弁護士基準や裁判基準ではなく、保険会社独自の低い支払基準で算定している場合があります。
3. 最大限の補償を得るための交渉ポイント
相手保険会社との交渉において、以下の点を意識しましょう。
- 時価額の妥当性を争う:
- 買替諸費用を漏れなく請求する:
- 請求できる可能性のある諸費用(登録費用、車庫証明費用、納車費用、消費税、環境性能割など)をリストアップし、具体的な金額とともに要求します。
- 保険会社が一部しか認めない場合は、なぜ必要な費用なのかを根拠とともに説明します。
- 過失割合を再検討する:
- 提示された8対2の過失割合に納得できない場合は、事故状況を示す証拠(ドライブレコーダー映像、事故証明書、実況見分調書、目撃者の証言など)を揃え、より有利な割合(可能であれば10対0)を主張します。
- 相手の「対物超過修理費用特約」を確認する:
- これは相手方の保険契約に付帯されている特約です。もし相手がこの特約に加入していれば、経済的全損の場合でも、時価額を超えた修理費用(通常は時価額+50万円が上限)が支払われる可能性があります。廃車ではなく修理を強く希望する場合などは、この特約の有無を確認する価値があります。ただし、この特約を使用するかは相手の自由です。
- 安易に示談しない:
- 提示額に納得できない場合は、焦って示談書にサインしないことが重要です。一度サインすると、原則として後から覆すことはできません。
- 弁護士に相談する:
- 交渉が難航する場合や、提示額・過失割合に大きな不満がある場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談するのが最も効果的です。弁護士は法的な根拠に基づき、適正な賠償額を算定し、あなたに代わって保険会社と交渉してくれます。弁護士費用特約があれば、費用負担の心配も少なく依頼できます。
「事故で廃車にされた」という状況では、感情的になりがちですが、冷静に、かつ粘り強く交渉することが重要です。適切な知識と準備をもって臨み、正当な権利を主張しましょう。
1-7:事故8対2の過失割合に納得できない場合の対処法

保険会社から「今回の事故の過失割合は8対2です」と一方的に告げられ、納得できないと感じるケースは少なくありません。「自分はもっと注意していたはずだ」「相手の不注意の方が大きかったはずだ」と思うのは自然なことです。ここでは、提示された8対2の過失割合に納得がいかない場合に、どのように対処すべきかを解説します。
1. なぜ納得できないのか?理由を明確にする
まず、なぜ8対2という割合に納得できないのか、具体的な理由を整理しましょう。
- 事故状況の認識の違い: 保険会社が把握している事故状況と、あなたの認識が異なっている。
- 相手の主張のみに基づいている可能性: 相手方の言い分だけが強く反映されていると感じる。
- 自分には避けようがなかった: 相手の危険な運転(急な割り込み、指示器なしの右左折など)が原因で、自分には回避の余地がなかったと考えている。
- 証拠の不足: ドライブレコーダーがない、目撃者がいないなどで、自分の正当性を証明する材料が手元に少ない。
2. 証拠を集め、客観的に事故状況を再検証する
過失割合は、事故の客観的な状況に基づいて判断されます。納得できない場合は、以下の証拠を集め、事故状況を詳細に再検証することが重要です。
- ドライブレコーダーの映像: 最も強力な証拠の一つです。事故前後の状況、双方の車の動き、信号の色などが記録されていれば、過失割合を覆す決め手になることがあります。自分の車だけでなく、相手の車や周辺車両のドラレコ映像も入手できないか確認しましょう。
- 事故現場の写真: 事故直後の車両の位置関係、損傷箇所、ブレーキ痕、道路標識、信号機の状況などを多角的に撮影した写真は重要です。
- 実況見分調書・供述調書: 警察が作成した書類です。事故状況の詳細な記録や当事者の供述が記載されています。後日、検察庁や弁護士を通じて入手できる場合があります(ただし、刑事事件になっていない場合は、「物件事故報告書」という簡易な図面になることもあります)。
- 目撃者の証言: 第三者である目撃者の証言は、証拠として有効です。事故直後に連絡先を交換しておきましょう。
- 車両の損傷状況: 車両のどこにどのような傷や凹みがついているかは、衝突時の角度や速度を推測する手がかりになります。修理前に写真を撮っておきましょう。
3. 保険会社に根拠を問い、交渉する
集めた証拠をもとに、保険会社の担当者に対して、なぜ8対2と判断したのか、具体的な根拠(どの判例を参考にしているのか、事故状況のどの点を重視したのか等)を詳しく説明するよう求めましょう。そして、あなたの認識や証拠に基づき、過失割合の見直しを具体的に主張・交渉します。
交渉のポイント:
- 感情的にならず、冷静に、客観的な事実に基づいて主張する。
- 類似の事故に関する過去の判例(判例タイムズなど)を調べ、有利な判例があれば提示する。
- 電話だけでなく、書面で主張を伝えることも有効。
4. 示談あっせん機関を利用する
当事者同士や保険会社との交渉で解決しない場合、以下のような中立的な第三者機関に相談し、示談のあっせんを依頼する方法もあります。
- 日弁連交通事故相談センター: 無料で弁護士による法律相談や示談あっせんを受けられます。
- 交通事故紛争処理センター: 無料で法律相談や和解のあっせん、審査を受けられます。
これらの機関は、専門家が間に入ってくれるため、話し合いが進展する可能性があります。
5. 弁護士に相談・依頼する
上記の手段でも解決しない場合や、最初から専門家のサポートを受けたい場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談・依頼するのが最も確実な方法です。
弁護士に依頼するメリット:
- 専門的な分析: 事故状況や証拠を法的な観点から分析し、適正な過失割合を判断してくれます。
- 有利な証拠収集のアドバイス: どのような証拠が有効か、どうやって入手すればよいかアドバイスを受けられます。
- 保険会社との対等な交渉: あなたに代わって、専門知識を駆使して保険会社と対等に交渉してくれます。保険会社側も、弁護士が出てくると態度を変え、譲歩してくるケースも少なくありません。
- 訴訟への移行: 交渉で合意に至らない場合は、訴訟(裁判)を起こして裁判所に最終的な判断を仰ぐことも可能です。
特に弁護士費用特約に加入していれば、費用面の心配なく弁護士に依頼できます。過失割合は賠償金額に直結する重要な要素ですので、納得できない場合は諦めずに、適切な手段を講じることが大切です。
2.事故8対2で廃車になった場合の対応と弁護士活用

さて、過失割合8対2で愛車が廃車になってしまった場合、具体的にどのように対応を進めていけばよいのでしょうか?事故直後の初動から、保険会社とのやり取り、そして最終的な示談に至るまで、適切なステップを踏むことが重要です。また、廃車後の車の買い替えや、自分の保険の活用、そして何より強力な味方となる弁護士の活用(特に弁護士費用特約がある場合)についても解説します。不利な状況を少しでも有利に進めるための実践的な知識を身につけましょう。
- 2-1: 事故8対2で廃車になった場合の対応ステップ:事故直後から示談まで
- 2-2: 廃車後の買い替え:事故8対2でもスムーズに進めるための注意点
- 2-3: 自分の車両保険は使うべき?事故廃車での相手の保険との使い分け
- 2-4: 新車が事故8対2で廃車に…特別なケースでの対応策と新車特約
- 2-5: 弁護士費用特約を徹底活用!事故8対2で廃車になった際の賢い使い方
- 2-6: 弁護士依頼で賠償金増額?事故8対2廃車ケースでの成功事例
- 2-7: まとめ:事故8対2で廃車になったら弁護士に相談!正当な賠償金を得るために
2-1: 事故8対2で廃車になった場合の対応ステップ:事故直後から示談まで
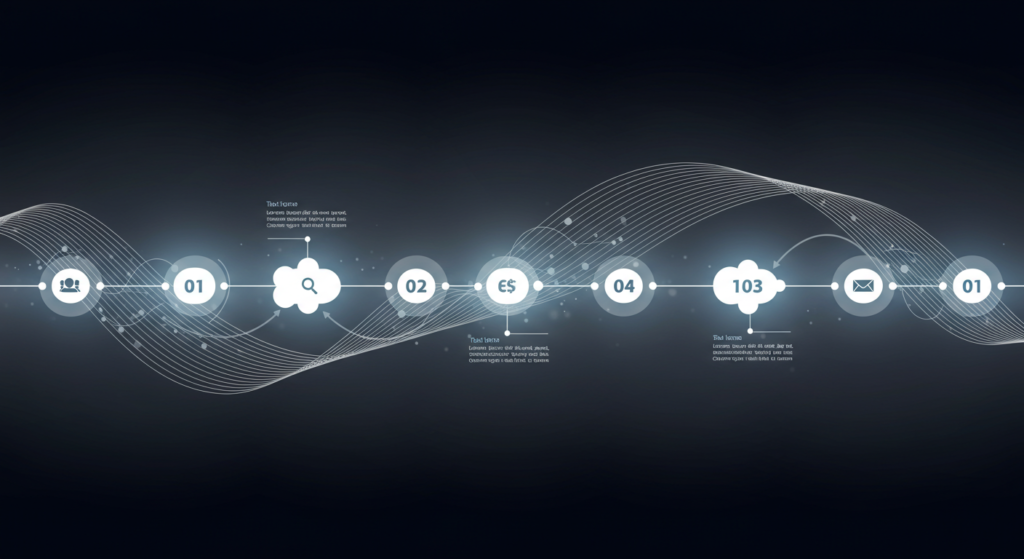
事故で廃車になった場合、冷静さを失わず、順序立てて対応することが、後の賠償交渉を有利に進める上で非常に重要です。特に過失割合が8対2とされる可能性がある事故では、初動対応と証拠保全が鍵となります。
【事故対応の基本的な流れ(ステップ)】
事故発生から解決までの流れは、大きく以下のフェーズに分けられます。各ステップを確実に実行することが重要です。
《フェーズ1:事故直後》~冷静な初動対応と証拠保全~
- 安全確保と負傷者の救護: まずは二次被害を防ぎ、人命を最優先に行動します(ハザード、安全な場所への移動、119番通報)。
- 警察への連絡 (110番): 必ず警察に届け出て、「交通事故証明書」が発行されるようにします。
- 相手方の情報確認: 氏名、連絡先、車両情報などを正確に確認します。
- 事故状況の記録・証拠保全: 記憶が新しいうちに状況をメモし、現場や車両の写真を多角的に撮影。ドラレコ映像は確実に保存し、目撃者がいれば協力を依頼します。
《フェーズ2:事故後~交渉準備》~保険会社連絡と損害把握~
- 自身の保険会社への連絡: 速やかに事故報告し、今後の対応のアドバイスを受け、利用できる保険(車両保険、弁護士費用特約など)を確認します。
- 医療機関の受診: 体に少しでも異変があれば、必ず早期に受診し、診断書を取得します(人身事故の場合)。
- 相手方保険会社とのやり取り開始: 担当者を確認し、相手方の主張を鵜呑みにせず、自身の認識を伝えます。
- 修理工場への連絡・見積もり取得: 車の損傷状況を確認し、修理見積もりまたは全損(時価額査定含む)の判断を受けます。
《フェーズ3:示談交渉~解決》~賠償額の確定と合意~
- 損害額の確定と過失割合の交渉: 車両損害(時価額+買替諸費用)、代車費用、治療費、慰謝料など全ての損害を算出し、相手保険会社と過失割合・賠償額について交渉します。人損と物損では別の担当者がついて、別々に交渉が行われるのが通常です。 ※この段階で弁護士相談・依頼を検討するのが効果的です。
- 示談交渉: 全ての損害が確定した後(特に人身事故は治療終了後)、賠償条件について最終的な合意を目指します。
- 示談成立・示談書の作成: 合意内容を書面化し、内容を十分に確認した上で署名・捺印します。
- 賠償金の受け取り: 示談書に基づき、定められた期日までに賠償金が支払われます。
- (交渉不調の場合)ADR機関・訴訟: 交渉で合意できない場合は、交通事故紛争処理センターなどのADR機関を利用するか、訴訟(裁判)によって解決を図ります。
このステップを確実に踏むことで、事故 8対2で廃車という不利な状況でも、ご自身の権利を守り、適切な賠償を受けるための土台を築くことができます。
2-2: 廃車後の買い替え:事故8対2でもスムーズに進めるための注意点

事故 8対2で愛車が廃車となり、買い替えを余儀なくされた場合、経済的な負担はもちろん、手続き面でも様々な注意点があります。スムーズに買い替えを進めるために、以下のポイントを押さえておきましょう。
1. 買い替え費用の補償範囲を理解する
- 相手保険から支払われるもの:
- 車両本体の時価相当額: 事故時点での車の価値が基本です。
- 買替諸費用: 登録費用、車庫証明費用、納車費用など、買い替えに通常必要となる費用の一部。
- ただし、8対2の過失割合のため、上記合計額の80% しか支払われません。残りの20%と、時価額を超えた購入費用は自己負担となります。
- 自分の車両保険を使う場合:
- 契約内容によりますが、全損の場合、車両保険金が支払われます。保険金額が時価額より高く設定されていれば、自己負担を減らせる可能性があります。
- 「車両新価保険特約(新車特約)」などがあれば、新車価格相当額が補償されることもあります(後述)。
- ただし、車両保険を使うと等級が下がり、翌年以降の保険料が上がる点に注意が必要です。
2. 買い替えのタイミング
- 示談成立前でも買い替えは可能か?: 可能です。車がないと生活に支障が出る場合、示談交渉を待たずに次の車を購入する必要があるでしょう。
- 注意点:
- 事故車両の処分: 保険会社との損害額の確認が終わる前に、事故車両を勝手に処分(売却、解体)しないようにしましょう。損害額の立証資料が失われ、交渉が不利になる可能性があります。保険会社の担当者や修理工場と相談し、写真撮影や現車確認が終わった後で処分するようにしてください。
- 資金繰り: 示談金が支払われるのは示談成立後なので、それまでは購入費用を立て替える必要があります。
3. 新しい車の選び方
- 予算: 相手保険からの賠償金(時価額+買替諸費用の80%)、自分の車両保険金、自己資金を合わせて、無理のない予算を立てましょう。
- 車種: 基本的に、どのような車に買い替えるかは自由です。ただし、代車費用が認められるのは「買い替えに必要な相当期間」なので、納車に時間がかかりすぎる特殊な車種を選ぶ場合は注意が必要です。
4. 買替諸費用の証拠を保管する
相手保険会社に買替諸費用を請求するためには、見積や、実際に支払ったことを証明する書類が必要です。実際に買替をしなくても、新しい車の見積だけあれば買替諸費用は請求可能です。
- 保管すべき書類:
- 新しい車の見積書、注文書、契約書
- 登録費用、車庫証明費用、納車費用などの領収書
- 自動車税、環境性能割、重量税などの納税証明書(または領収書)
- 廃車にした車の解体証明書や登録抹消証明書など
これらの書類を整理して保管し、保険会社に提出できるようにしておきましょう。
5. 廃車手続きと納車手続き
- 廃車手続き: 事故車両を廃車にする場合、解体業者への依頼や陸運局での抹消登録手続きが必要です。通常は購入先のディーラーや中古車販売店、または廃車買取業者に代行を依頼できます。
- 納車手続き: 新しい車の登録、車庫証明取得、納車などの手続きも、販売店に任せるのが一般的です。
6. 代車の確保
買い替え期間中に車が必要な場合、代車を手配します。
- 相手保険で認められる範囲: 前述の通り、期間(通常2週間程度)や車種クラスに制限があります。8対2の場合は費用も8割負担です。
- 自己負担: 相手保険でカバーされない期間や費用は自己負担になります。自分の保険に代車費用特約が付いていれば、それを利用することも検討しましょう。
事故 8対2での買い替えは、金銭的な負担増が避けられないことが多いです。だからこそ、請求できる費用を漏れなく請求し、保険を賢く利用することが重要になります。不明な点や不安な点は、保険会社や弁護士に相談しながら進めましょう。
2-3: 自分の車両保険は使うべき?事故廃車での相手の保険との使い分け

事故で廃車になった場合、相手がいる事故(特に8対2など過失がある場合)では、「相手の保険(対物賠償保険)を使うべきか」「自分の車両保険を使うべきか」で悩むことがあります。どちらを使うか、あるいは両方をどう使い分けるかは、状況によって最適な選択が異なります。
基本的な考え方
- 相手の保険(対物賠償保険): 相手に過失がある場合、相手の保険から相手の過失割合に応じた賠償金(時価額+買替諸費用など)が支払われます。8対2なら損害額の80%です。
- 自分の車両保険: 自分の車の損害を補償する保険です。契約内容に応じて、車両保険金額を上限として保険金が支払われます。全損の場合、過失割合に関係なく(※免責金額が設定されている場合を除く)保険金を受け取れるのが一般的です。
自分の車両保険を使うメリット
- 早期に保険金を受け取れる: 相手との示談交渉が長引いても、自分の保険会社との手続きが済めば、比較的早く保険金を受け取れます。これにより、車の買い替え資金を早く確保できます。
- 過失割合に関係なく補償される(全損の場合): 8対2事故のように自分にも過失がある場合でも、車両保険金額の満額(免責金額がなければ)を受け取れる可能性があります。相手保険から80%しか補償されない部分をカバーできます。
- 時価額以上の補償の可能性: 車両保険金額が実際の時価額よりも高く設定されていた場合、時価額以上の保険金を受け取れる可能性があります(ただし、契約内容によります)。
自分の車両保険を使うデメリット
- 保険等級が下がり、保険料が上がる: 車両保険を使うと、通常3等級ダウンし、さらに事故有係数が適用されるため、翌年以降の保険料が大幅に上がります。数年間の保険料アップ分を考えると、トータルでは損になる可能性もあります。
- 免責金額(自己負担額)がある場合がある: 契約によっては、保険金支払い時に自己負担額(例:5万円、10万円など)が差し引かれる場合があります。
使い分けの判断基準
以下の点を考慮して、どちらを使うか、あるいはどう組み合わせるかを判断しましょう。
- 過失割合:
- 10対0(相手が100%悪い): 基本的に相手の保険で全額賠償されるべきなので、自分の車両保険を使うメリットは少ないです(保険料が上がるだけ)。ただし、相手が無保険の場合や支払いを拒否している場合は、自分の車両保険(車両無過失事故に関する特約があれば等級ダウンなしの可能性も)を使うことを検討します。
- 8対2など自分にも過失がある: ここが最も悩ましいケースです。
- 相手保険(80%) + 自己負担(20%) で賄えるか?
- 車両保険を使って満額もらった方が、保険料アップ分を考慮しても得か?
- 車両保険金額と時価額の関係:
- 車両保険金額 ≧ 時価額: 車両保険を使った方が多くの補償を受けられる可能性があります。
- 車両保険金額 < 時価額: 相手保険からの賠償(時価額の80%)の方が多い可能性があります。ただし、早期に資金が必要な場合は車両保険利用も選択肢に。
- 保険料の値上がり幅: 等級ダウンによる保険料アップがどれくらいになるか、保険会社に試算してもらいましょう。数万円程度の差であれば、保険を使わずに自己負担した方が長期的に見て得な場合もあります。
- 相手保険会社の対応: 相手保険会社の支払い提示が極端に低い、交渉が難航している、などの場合は、先に自分の車両保険で補償を受け、その後の相手への請求(求償)を自分の保険会社に任せるという方法もあります(保険会社が対応してくれるか要確認)。
【どちらを使うか?判断のポイント】
- 相手に過失があるか? → Yesなら次へ / No(自損事故)なら自分の車両保険を検討
- 過失割合は?
- 10対0 → 基本は相手保険で請求。相手が無保険等なら自分の車両保険を検討。
- 8対2など自分にも過失あり → 次の点を比較検討。
- 「相手保険(8割) + 自己負担(2割)」と「自分の車両保険金(満額)- 保険料UP分」を比較。
- 早期資金が必要か? 車両保険金額は時価額より高いか?
- 比較して車両保険が有利なら利用を検討。そうでなければ相手保険+自己負担で対応。
結論
事故 8対2で廃車になった場合、まずは相手の保険会社に請求するのが基本です。しかし、提示された時価額や過失割合に納得がいかない場合や、早期に買い替え資金が必要な場合、あるいは車両保険金額の方が有利な場合には、自分の車両保険の利用を検討します。その際は、必ず保険料の値上がりデメリットと比較検討しましょう。判断に迷う場合は、自分の保険会社の担当者や弁護士に相談することをお勧めします。
2-4: 新車が事故8対2で廃車に…特別なケースでの対応策と新車特約
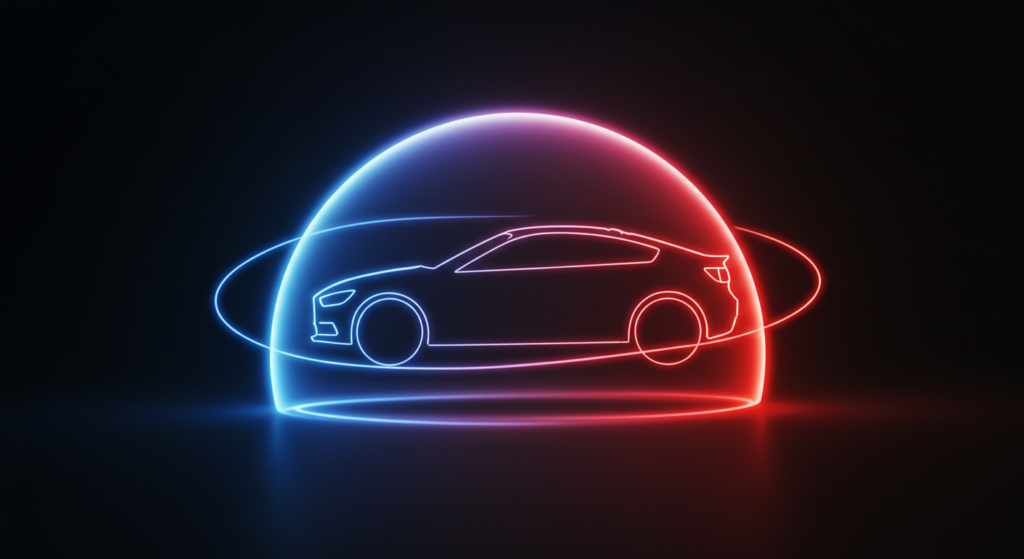
購入したばかりの新車が、事故 8対2の過失割合で廃車になってしまった… これは経済的にも精神的にも非常に大きなダメージです。「新車価格で弁償してほしい!」と思うのが人情ですが、通常の賠償ルールではそう簡単にはいきません。ここでは、新車が廃車になった場合の特別な対応策と、「新車特約」の重要性について解説します。
通常の賠償ルール:原則は「時価額」
残念ながら、たとえ新車であっても、交通事故の損害賠償の原則は「事故発生時点での車両の時価額」です。新車登録後、わずか数日や数週間しか経っていなくても、中古車市場に出れば理論上は価値が下がるため、購入価格そのものが時価額とは認められないことが多いのです。
- 時価額の算定: 新車に近い状態であれば、購入価格に近い金額が時価額として認められる可能性はありますが、それでも諸費用などを含めた支払総額全額が認められるとは限りません。
- 8対2の影響: さらに過失割合が8対2の場合、算出された時価額の80%しか相手からは支払われません。
つまり、通常のルールだけでは、新車を再度購入するための費用を全額カバーすることは難しいのが現実です。
特別な対応策:「評価損」の請求
新車や登録から期間が浅い車の場合、「評価損(格落ち損害)」を請求できる可能性があります。評価損とは、事故歴がついたことによる車両価値の下落分のことです。
- 全損(廃車)の場合: 通常、全損の場合は「時価額」が賠償されるため、評価損は別途認められにくいとされています。なぜなら、時価額賠償によって価値下落分も填補されていると考えられるからです。
- しかし、新車の場合: 購入直後の事故で全損となった場合など、極めて限定的なケースでは、時価額賠償に加えて評価損(新車価格と時価額の差額の一部など)が認められる可能性もゼロではありません。ただし、これは法的に争いになることが多く、認められるハードルは高いです。
「車両新価保険特約(新車特約)」
新車が廃車になった場合に最も頼りになるのが、自分の自動車保険に付帯できる「車両新価保険特約(新車特約)」です。
- 特約の内容: この特約が付いていれば、事故によって車が全損になった場合や、修理費が新車価格相当額の50%以上となった場合に、新たに同等の新車を購入するための費用(車両本体価格+付属品+消費税+登録諸費用など)が保険金として支払われます。
- メリット:
- 時価額ではなく新車価格相当額が補償されるため、自己負担なく新しい車に買い替えることが可能です。
- 過失割合に関係なく(自分の車両保険の一部なので)、保険金を受け取れます(免責金額が適用される場合はあります)。
- 加入条件: 通常、新車登録時から一定期間内(例:1年~3年以内など、保険会社により異なる)の車しか加入できません。
- 注意点: この特約を付けていないと、新車が事故で廃車になっても新車価格での補償は受けられません。
もし新車特約がなかったら?
新車特約に加入しておらず、相手保険からの賠償(時価額の80%)と自分の車両保険(時価額ベース)だけでは新車購入費用に足りない場合、差額は自己負担となります。この場合、弁護士に相談し、評価損の請求など、少しでも賠償額を上積みできないか検討する価値はあります。
まとめ
新車が事故8対2で廃車になった場合、通常の時価額賠償だけでは大きな自己負担が発生する可能性が高いです。万が一に備え、新車購入時には車両新価保険特約(新車特約)への加入を検討しても良いでしょう。もし特約がなく事故に遭ってしまった場合は、諦めずに最善策を探ることが重要です。
2-5: 弁護士費用特約を徹底活用!事故8対2で廃車になった際の賢い使い方
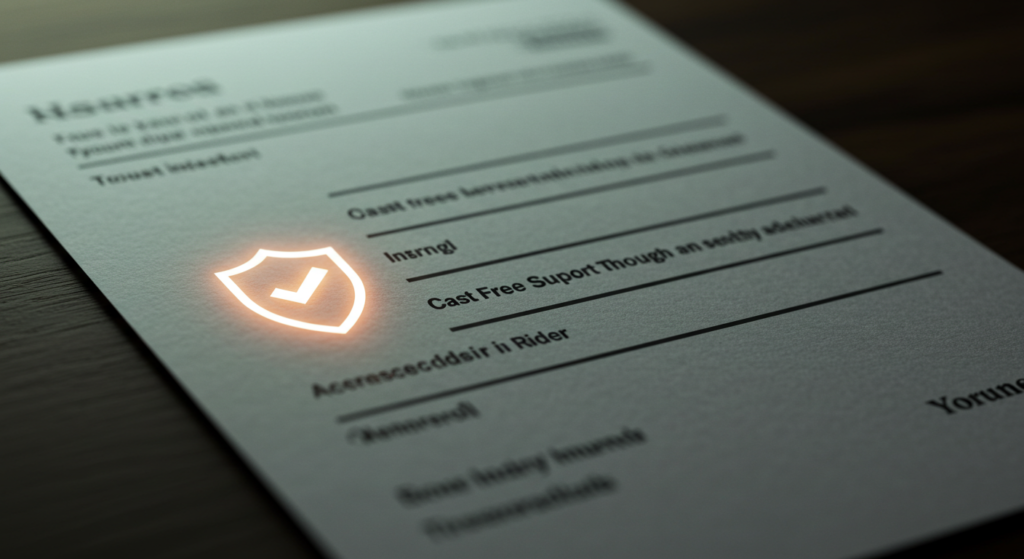
事故 8対2で廃車という状況は、賠償金の交渉が複雑になりがちです。相手保険会社の提示額に納得がいかない、過失割合がおかしいと感じる…そんな時、専門家である弁護士に依頼するのが有効な解決策ですが、気になるのが弁護士費用です。そこで非常に役立つのが「弁護士費用特約」です。この特約を賢く活用する方法を知っておきましょう。
弁護士費用特約とは?
- 概要: 自動車保険や火災保険などに付帯できる特約の一つで、交通事故(または日常生活での事故)の被害に遭い、相手方に損害賠償請求を行う際に必要となる弁護士費用や法律相談費用を保険会社が補償してくれる制度です。
- 補償上限額: 一般的に、法律相談費用は1事故につき10万円まで、弁護士費用(着手金・報酬金・実費など)は1事故につき300万円までというプランが多いです。ほとんどの交通事故案件は、この範囲内で収まります。
- 利用しても等級は下がらない: この特約を使っても、自動車保険の等級は下がりません。そのため、保険料が上がる心配なく利用できます。
- 誰が使える?: 契約者本人だけでなく、その配偶者、同居の親族、別居の未婚の子なども利用できる場合があります。また、契約車両に乗っていなかった場合の事故(歩行中や自転車での事故など)でも使えることが多いです。ご自身の保険契約内容を確認してみましょう。
なぜ8対2廃車事故で弁護士費用特約が有効なのか?
過失割合が8対2で廃車というケースは、以下のような点で揉めやすく、弁護士のサポートが特に有効です。
- 過失割合の妥当性: 8対2という割合自体に納得がいかず、見直しを求めたい場合。
- 時価額算定の妥当性: 廃車となった車両の時価額が低く見積もられている場合。
- 買替諸費用の範囲: どこまでの諸費用が賠償対象となるかで争いがある場合。
- 保険会社の担当者との相性: 過失割合が8対2であれば、自分の保険会社の対物担当者があなたの窓口になるはずですが、担当者との相性が悪く、交渉がスムーズに進まない場合。
- 精神的負担: 事故対応や交渉によるストレスが大きい場合。
これらの問題に対し、弁護士は法的根拠に基づき、適正な過失割合や賠償額を主張し、あなたに代わって粘り強く交渉してくれます。弁護士費用特約があれば、実質的な自己負担なく、こうした専門家のサポートを受けられるのです。
弁護士費用特約の賢い使い方ステップ
- 加入状況の確認: まず、ご自身やご家族が加入している自動車保険、火災保険、傷害保険などに弁護士費用特約が付帯されているか確認します。保険証券や契約内容の案内を確認するか、保険会社に直接問い合わせましょう。
- 保険会社への事前連絡: 特約を利用したい旨を、必ず弁護士に相談・依頼する前に、保険会社に連絡し、承認を得る必要があります。無断で依頼を進めると、後で費用が支払われない可能性があるので注意が必要です。
- 弁護士を探す: 保険会社によっては提携弁護士を紹介されることもありますが、自分で弁護士を選ぶことも可能です。交通事故案件の実績が豊富な弁護士を選ぶことが重要です。インターネット検索や、法テラス、弁護士会の紹介などを利用しましょう。
- 法律相談: 選んだ弁護士に連絡を取り、法律相談の予約をします。相談時には、事故の状況、保険会社の提示内容、弁護士費用特約を利用したい旨などを伝えましょう。初回相談は無料としている事務所も多いです。
- 委任契約: 相談の結果、弁護士に依頼することを決めたら、委任契約を結びます。契約内容(費用体系、業務範囲など)をしっかり確認しましょう。弁護士費用特約を使う場合、弁護士費用の請求は弁護士から保険会社へ直接行われることが多いです。
- 弁護士による交渉開始: 委任後は、弁護士があなたに代わって相手保険会社との交渉や必要な手続きを進めてくれます。あなたは弁護士からの報告を受け、重要な判断を行うことになります。
注意点
- 全ての弁護士費用が補償されるわけではありません(上限額を超える場合など)。
- 相手への請求が全く認められないような案件では、特約が使えない場合もあります。
- 弁護士の選定は慎重に行いましょう。
弁護士費用特約は、交通事故被害者にとって非常に心強い味方です。事故 8対2で廃車という困難な状況だからこそ、この特約を最大限に活用し、専門家の力を借りて正当な権利を実現しましょう。
2-6: 弁護士依頼で賠償金増額?事故8対2廃車ケースでの成功事例

「事故 8対2で廃車になったけど、弁護士に頼んだら本当に賠償金が増えるの?」と疑問に思う方もいるでしょう。結論から言うと、弁護士に依頼することで、賠償金が大幅に増額するケースは少なくありません。ここでは、具体的な事例のパターンを見ていきましょう。
増額が期待できるポイント
弁護士が介入することで、主に以下の点で増額が期待できます。
- 過失割合の見直し: 保険会社提示の「8対2」が、弁護士の交渉により「9対1」や「10対0」など、被害者有利な割合に変更されるケース。これにより、過失相殺される割合が減り、受け取れる金額が増えます。
- 車両時価額の増額: 保険会社が低く見積もった車両の時価額を、市場価格や車両の状態を根拠に、より適正な金額まで引き上げるケース。
- 買替諸費用の適切な請求: 認められるべき諸費用を漏れなく請求し、満額に近い金額を獲得するケース。
- 慰謝料の増額(人身事故の場合): 保険会社が提示する「任意保険基準」ではなく、より高額な「弁護士基準(裁判基準)」で慰謝料を算定・請求し、増額を実現するケース。
- 後遺障害等級の獲得・異議申し立て(人身事故の場合): 適切な後遺障害等級を獲得したり、低い等級認定に対して異議申し立てを行い、より上位の等級を認めさせ、後遺障害慰謝料や逸失利益を増額させるケース。
成功事例のパターン(8対2廃車ケース)
- 事例1:過失割合が変更され増額
- 状況: 交差点での右直事故。被害者(直進車)は相手保険会社から過失割合8対2(被害者2割)と提示され、廃車となった車両の賠償額も低く見積もられていた。被害者はドライブレコーダー映像をもとに自身の過失は低いと主張。
- 弁護士の対応: 弁護士がドラレコ映像を詳細に分析し、相手(右折車)の早期右折や速度超過を指摘。類似の裁判例も提示し、過失割合は9対1(被害者1割)が妥当であると強く交渉。
- 結果: 保険会社が譲歩し、過失割合が9対1に変更。さらに、車両時価額についても市場価格に基づき増額され、当初提示額からの増額に成功。
- 事例2:車両時価額が見直され増額
- 状況: 少し古い年式の人気車種が事故で経済的全損(廃車扱い)。相手保険会社はレッドブックのみを参考に低い時価額を提示(8対2の過失相殺後)。被害者は同車種の中古車市場価格がもっと高いと主張。
- 弁護士の対応: 弁護士が中古車情報サイトで市場価格を調査し、同等車両の実際の取引価格データを複数収集。車両の状態が良かった点も主張し、保険会社に時価額の再算定を要求。
- 結果: 保険会社が市場実勢価格を認め、車両時価額が当初提示より増額。過失相殺後の受取額も大幅にアップ。
- 事例3:人身損害(慰謝料)も合わせて増額
- 状況: 事故8対2で車は廃車、被害者はむちうちで6ヶ月通院。相手保険会社は、物損(車両)の賠償に加え、慰謝料等を自賠責基準に近い低い金額で提示。
- 弁護士の対応: 弁護士が介入し、物損については時価額や買替諸費用を精査して増額交渉。人身損害については、通院実績に基づき弁護士基準(裁判基準)で入通院慰謝料や休業損害を算定し直し、請求。
- 結果: 物損・人身損害合わせて、当初の保険会社提示額から増額で示談成立。
なぜ弁護士が介入すると増額しやすいのか?
- 専門知識と交渉力: 弁護士は法律、判例、保険実務に精通しており、保険会社に対して法的根拠に基づいた説得力のある主張・交渉ができます。
- 「弁護士基準」の適用: 特に慰謝料など人身損害部分では、弁護士が介入することで最も高額な「弁護士基準(裁判基準)」での請求が可能になります。
- 訴訟も辞さない姿勢: 保険会社側も、弁護士が相手となると「交渉が決裂すれば訴訟になる可能性がある」と考えるため、譲歩しやすくなる傾向があります。
もちろん、全てのケースで必ず増額するとは限りませんが、事故 8対2で廃車という複雑な状況においては、弁護士に依頼することで、より適正で有利な条件を引き出せる可能性は格段に高まります。弁護士費用特約があれば、費用負担を気にせず依頼できるため、まずは一度相談してみることを強くお勧めします。
2-7: まとめ:事故8対2で廃車になったら弁護士に相談!正当な賠償金を得るために
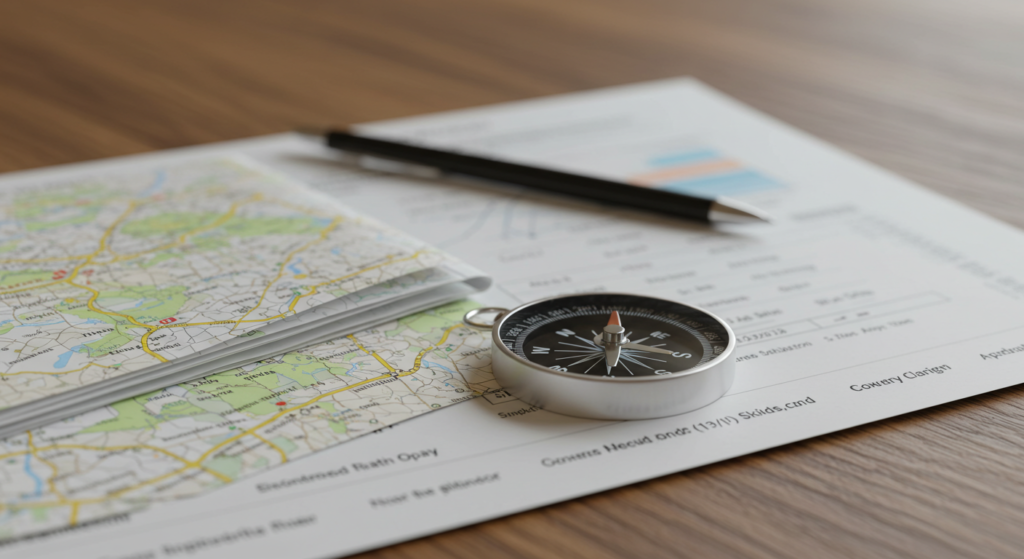
交通事故で過失割合8対2とされ、愛車が廃車になってしまった場合、精神的なショックに加え、賠償金の交渉という大きな課題に直面します。相手保険会社の提示額は本当に妥当なのか、自分の権利はどこまで主張できるのか、不安は尽きないでしょう。
この記事で解説してきたポイントを、最後にまとめます。
- 8対2の意味を理解する: あなたの損害の8割しか補償されず、相手の損害の2割を負担する必要があります。
- 廃車の基準を知る: 物理的全損か経済的全損かを確認し、特に経済的全損の場合は時価額の算定根拠をしっかり確認しましょう。
- 請求できる項目を把握する: 車両時価額だけでなく、買替諸費用、代車費用なども請求可能です。漏れなくリストアップしましょう。
- 過失割合に疑問を持とう: 保険会社の提示する8対2が絶対ではありません。ドラレコ映像などの証拠があれば、見直しを交渉する価値があります。10対0との差は大きいです。
- 安易に示談しない: 保険会社の提示額に納得できない場合は、焦ってサインせず、交渉を続けましょう。
- 保険を賢く使う: 相手の保険だけでなく、自分の車両保険や、特に「弁護士費用特約」の活用を検討しましょう。
- 弁護士は強い味方: 過失割合、時価額、慰謝料など、専門的な知識であなたをサポートし、賠償金増額の可能性を高めてくれます。
事故 8対2で廃車という状況は、被害者にとって非常に不利に感じられるかもしれません。しかし、正しい知識を持ち、適切な対応をとることで、状況を改善し、受け取るべき正当な賠償金を獲得することは十分に可能です。
特に、弁護士費用特約に加入している場合は、費用負担の心配なく専門家である弁護士に相談・依頼できます。これは非常に大きなアドバンテージです。
もしあなたが今、事故 8対2で廃車になり、相手保険会社との交渉に悩んでいるなら、決して一人で抱え込まず、できるだけ早い段階で交通事故に強い弁護士に相談することをお勧めします。それが、あなたの正当な権利を守り、最大限の賠償金を得るための最も確実な一歩となるでしょう。














