
交通事故に遭われた方、示談金がいつ振り込まれるのか、不安に思っていませんか? 「交通事故示談金 いつ 振り込まれる 知恵袋」 などで検索しても、情報が断片的でよくわからない…そんな経験はありませんか?
特に、10対0の事故で示談金はいつもらえるのか、交通事故で通院終了がしてから支払いはいつになるのか、弁護士に依頼した場合、示談金の振込の流れはどうなっているのか、など、具体的な疑問は尽きないでしょう。
さらに、損保ジャパンでの示談金の振込はいつか 、三井住友海上の事故慰謝料の振込はいつかなど、保険会社によって振込までの期間が異なるのかも気になるところです。
もし、示談金が振り込まれないとき、弁護士に相談すべきか迷っているなら、この記事がきっとお役に立ちます。弁護士費用特約があれば、費用を気にせず弁護士に依頼できる可能性も!
この記事では、交通事故の示談金が振り込まれるまでの流れや、弁護士に依頼するメリット、さらには弁護士費用特約の活用方法まで、詳しく解説します。示談金の振り込み日数が気になる方、必見です!
主要なポイント
- 交通事故の示談金は、通常、示談成立後1~2週間で振り込まれます。
- 弁護士に依頼することで、示談交渉がスムーズに進み、早期の振込みが期待できます。
- 弁護士費用特約を利用すれば、自己負担なしで弁護士に依頼できる場合があります。
- 示談金が振り込まれない場合は、弁護士に相談して適切な対処法を検討しましょう。
- 保険会社によって、示談金振込みまでの期間や対応が異なる場合があります。
目次
1. 交通事故の示談金はいつ振り込み?弁護士依頼で早期解決&増額!

交通事故に遭ってしまった…ただでさえ大変な状況なのに、示談金がいつ振り込まれるのか、不安でいっぱいですよね。
一般的に示談金は示談成立後1~2週間で振り込まれると言われていますが、場合によっては遅れることもあります。
そんな時、弁護士に依頼することで、示談交渉がスムーズに進み、示談金が早期に振り込まれる可能性が高まります。
また、弁護士に依頼することで、慰謝料などの示談金が増額されるケースも少なくありません。
この章では、交通事故の示談金が振り込まれるまでの流れや、弁護士に依頼するメリットについて詳しく解説していきます。
1-1. 交通事故の示談金振込みはいつ?一般的な流れと期間を解説

交通事故の示談金は、示談が成立してから振り込まれるのが一般的です。しかし、具体的にいつ振り込まれるのか、どのような流れで手続きが進むのか、不安に感じる方も多いでしょう。ここでは、示談金振込みまでの一般的な流れと期間について解説します。
示談金振込みまでの流れ(概要)
- 事故発生・警察への連絡: 交通事故が発生したら、まずは警察に連絡しましょう。
- 治療: 病院で適切な治療を受けます。
- 症状固定または治癒: 医師から症状固定(これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態)または治癒の診断を受けます。
- 後遺障害等級認定(該当する場合): 症状固定後、後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定の申請を行います。
- 示談交渉: 保険会社と示談交渉を開始します。
- 示談成立: 示談内容に合意し、示談書に署名・捺印します。
- 示談書返送: 保険会社に示談書を返送します。
- 示談金振込み: 保険会社が示談書を受領後、通常1~2週間程度で指定口座に示談金が振り込まれます。
示談金振込みまでの期間
示談成立から示談金が振り込まれるまでの期間は、通常1~2週間程度が目安です。ただし、これはあくまで目安であり、保険会社や個別の事情によって異なる場合があります。
- 早ければ3営業日程度で振り込まれることもあります。
- 書類に不備があったり、保険会社の内部手続きに時間がかかったりする場合は、2週間以上かかることもあります。
- 年末年始や大型連休などを挟む場合は、さらに時間がかかることがあります。
振込までの期間を左右する要素
- 示談成立までの期間
- 提出書類の不備の有無
- 保険会社側の事情
- そもそも過失割合や損害額に合意できていないか、争いがある
示談金振込みが遅れる主な原因
- 示談書の不備: 署名・捺印漏れ、記載ミスなどがあると、保険会社から差し戻され、手続きが遅れます。
- 保険会社の内部処理の遅延: 担当者の多忙、決裁の遅れなど、保険会社側の事情で処理が遅れることがあります。
- 振込先口座情報の誤り: 口座番号や名義の間違いがあると、振込みができません。
- 加害者が任意保険未加入: 加害者本人が示談金を支払う場合、支払いが遅れることがあります。
示談金振込みまでの流れと期間について、一般的なケースを解説しました。
次に、より具体的な期間について掘り下げていきます。
1-2. 示談成立から振込みまでの標準期間は1~2週間

前の項目で、示談金振込みまでの一般的な流れと期間について解説しました。ここでは、「示談成立から振込みまでの標準期間」に焦点を当て、さらに詳しく見ていきましょう。
標準期間は1~2週間
多くの保険会社では、示談成立後、示談書が保険会社に到着してから1~2週間程度で示談金が振り込まれるのが一般的です。これは、保険会社が示談書の内容を確認し、社内での支払い手続きを行うために必要な期間です。
- 迅速な対応を心がけている保険会社では、示談書到着後、3営業日~1週間程度で振り込まれることもあります。
- ただし、これはあくまで目安であり、個別の状況や保険会社によって異なることを理解しておく必要があります。
なぜ1~2週間かかるのか?
保険会社は、示談書を受け取った後、以下のようないくつかの手続きを行います。
- 示談書の内容確認: 示談内容に誤りがないか、署名・捺印は適切かなどを確認します。
- 社内決裁: 支払い担当者だけでなく、上長や決裁権限を持つ部署の承認を得ます。
- 振込手続き: 経理部門が指定口座への振込手続きを行います。
これらの手続きには、一定の時間を要するため、示談成立後すぐに振り込まれるわけではありません。なお、受け取りが弁護士の口座の場合、弁護士費用や実費を清算して、依頼者の口座に支払われることもあるので、その分、時間が余計にかかることもあります。
弁護士に依頼した場合
弁護士に示談交渉を依頼した場合、示談成立までの期間が短縮されるだけでなく、示談金振込みまでの期間も早まる可能性があります。これは、弁護士が以下のような役割を果たすためです。
- 示談書の不備チェック: 弁護士が事前に示談書の内容をチェックするため、不備による差し戻しを防ぐことができます。
- 保険会社との交渉: 弁護士が保険会社と交渉することで、スムーズな示談成立を促し、結果的に振込みまでの期間短縮につながります。
- 振込状況の確認: 弁護士が保険会社に振込状況を確認し、遅延している場合は催促することも可能です。
示談成立後の振込みまでの期間について、標準的な期間と、弁護士に依頼した場合のメリットについて解説しました。
続いて、示談金振込みまでのより具体的なステップをみていきましょう。
1-3. 示談金振込みまでの具体的な流れ9ステップ
ここでは、交通事故発生から示談金が振り込まれるまでの流れを、9つのステップに分けて具体的に解説します。弁護士に依頼した場合のメリットにも触れながら、各ステップを詳しく見ていきましょう。
- 1. 交通事故発生・警察への連絡
交通事故が発生したら、まずは警察に連絡しましょう。これは、法律上の義務であると同時に、事故状況を客観的に記録するためにも重要です。
警察への連絡を怠ると、保険金の請求に必要な「交通事故証明書」が発行されず、示談交渉に支障をきたす可能性があります。 - 2. 治療
事故によって負傷した場合は、必ず病院で適切な治療を受けましょう。
自己判断で通院を中断したり、適切な治療を受けなかったりすると、後遺症が残ったり、示談金が減額されたりする可能性があります。
医師の指示に従い、症状が改善するまでしっかりと治療を続けることが大切です。 - 3. 症状固定または治癒
医師から「症状固定」または「治癒」の診断を受けます。- 症状固定: これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態。
- 治癒: 交通事故による怪我が治った状態(症状固定の状態を「治癒」ということもあります)。
症状固定の診断を受けると、後遺障害の有無に応じて、後遺障害等級認定の手続きに進むことになります。
- 4. 後遺障害等級認定(該当する場合)
症状固定後、後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定の申請を行います。
後遺障害等級は、後遺症の程度に応じて1級から14級までの等級が定められており、認定された等級によって、後遺障害慰謝料や逸失利益の金額が大きく変わります。
後遺障害等級認定は、専門的な知識が必要となるため、弁護士に相談することをおすすめします。 - 5. 示談交渉
症状固定または治癒後、保険会社と示談交渉を開始します。
保険会社から提示される示談金額は、必ずしも適正とは限りません。
特に、後遺障害が残った場合や、過失割合に争いがある場合は、弁護士に依頼して示談交渉を進めることを強くおすすめします。 - 6. 示談成立
保険会社との示談交渉の結果、示談内容に合意したら、示談書に署名・捺印します。
示談書は、示談内容を証明する重要な書類ですので、内容をよく確認し、不明な点があれば必ず質問してから署名・捺印しましょう。 - 7. 示談書返送
署名・捺印した示談書を、保険会社に返送します。
返送方法については、保険会社から指示がありますので、それに従いましょう。 - 8. 示談金振込み
保険会社が示談書を受領後、通常1~2週間程度で、指定した口座に示談金が振り込まれます。
振込が完了したら、保険会社から振込完了の連絡がある場合と、ない場合があります。 - 9. 示談金振込みの確認
指定口座への着金を確認します。着金が確認できない場合は、保険会社に連絡して確認しましょう。
弁護士に依頼するメリット(各ステップにおいて)
- ステップ1: 事故直後の対応についてアドバイスを受けられる。
- ステップ2: 適切な治療を受けるためのサポートを受けられる。
- ステップ3: 症状固定の時期や、後遺障害等級認定の申請についてアドバイスを受けられる。
- ステップ4: 後遺障害等級認定の申請手続きを代行してもらえる。
- ステップ5: 示談交渉を有利に進めてもらえる。
- ステップ6: 示談書の内容をチェックしてもらえる。
- ステップ7: 示談書の返送手続きを代行してもらえる。
- ステップ8: 示談金振込みまでの期間を短縮できる可能性がある。
- ステップ9: 示談金が振り込まれない場合の対応を任せられる。
このように、弁護士に依頼することで、交通事故発生から示談金振込みまでのすべてのステップにおいて、サポートを受けることができます。
示談金振込みまでの具体的な流れを9つのステップに分けて解説しました。
次に、弁護士に依頼することで示談金振込みが早まる理由について、詳しく見ていきましょう。
1-4. なぜ弁護士に依頼すると示談金振込みが早まる?

前の項目で、示談金振込みまでの具体的な流れを9つのステップで解説しました。ここでは、「なぜ弁護士に依頼すると示談金振込みが早まるのか」という点について、さらに詳しく掘り下げていきます。
弁護士依頼で示談金振込みが早まる理由
弁護士に依頼すると、示談金振込みが早まる主な理由は、以下の3点です。
- 1. 示談交渉の迅速化:
- 弁護士は、法律の専門知識や交渉スキルを駆使して、保険会社と対等に交渉を進めます。
- 被害者自身が交渉する場合に比べて、スムーズに示談が成立する可能性が高まります。
- 示談交渉が長引くほど、示談金振込みも遅れるため、交渉の迅速化は振込みの早期化に直結します。
- 2. 示談書の不備防止:
- 弁護士は、示談書の内容を詳細にチェックし、署名・捺印の不備や記載漏れがないかを確認します。
- 不備があれば、保険会社から示談書が差し戻され、振込みが遅れる原因となります。
- 弁護士が事前にチェックすることで、不備による遅延を防ぐことができます。
- 3. 保険会社へのプレッシャー:
- 弁護士が介入することで、保険会社は「早期に解決しなければ訴訟に発展する可能性がある」と認識します。
- 保険会社は、訴訟を避けるために、示談交渉や支払い手続きを迅速に進める傾向があります。
- 弁護士からの連絡は、保険会社に対して、より強いプレッシャーを与えることになります。
弁護士費用は?
弁護士に依頼すると、当然ながら弁護士費用が発生します。しかし、弁護士費用特約に加入していれば、自己負担なしで弁護士に依頼できる場合があります。
弁護士費用特約については、次の項目で詳しく解説します。
弁護士に依頼することで示談金振込みが早まる理由について解説しました。
次は、多くの方が気になる「弁護士費用特約」について掘り下げていきます。
1-5. 弁護士費用特約で自己負担0円!
前の項目で、弁護士に依頼すると示談金振込みが早まる可能性があること、そして弁護士費用が発生することについて触れました。ここでは、「弁護士費用特約」について詳しく解説し、自己負担なしで弁護士に依頼できる可能性について説明します。
弁護士費用特約とは?
弁護士費用特約とは、自動車保険や火災保険などに付帯できる特約の一つで、交通事故などのトラブルで弁護士に相談・依頼する際の費用を、保険会社が負担してくれるというものです。
- 保険会社が負担する費用:
- 法律相談料: 弁護士に法律相談をする際の費用。
- 着手金: 弁護士に事件を依頼する際に支払う費用。
- 報酬金: 事件が解決した際に、弁護士に支払う費用。
- 実費: 交通費、郵便代、裁判所に納める費用など。
- 保険金の限度額:
- 多くの保険会社では、1つの事故につき、300万円程度を限度額としています。
- 法律相談料については、10万円程度を限度額としていることが多いです。
弁護士費用特約のメリット
- 自己負担を軽減できる: 弁護士費用を気にせず、弁護士に相談・依頼できます。
- 泣き寝入りを防げる: 弁護士費用の負担を心配して、費用倒れによる泣き寝入りしてしまうことを防げます。
- より良い解決が期待できる: 弁護士のサポートにより、より有利な条件で示談を成立させられる可能性が高まります。
弁護士費用特約の注意点
- 保険会社への事前連絡が必要: 弁護士に依頼する前に、必ず保険会社に連絡し、特約を利用する旨を伝えましょう。
- 保険会社が弁護士を紹介してくれる場合もある: 自分で弁護士を探す手間が省けますが、必ずしも自分に合った弁護士とは限りません。
- すべてのケースで利用できるわけではない:
- 被害者側に100%過失がある事故など、特約の利用対象外となるケースもあります。
- 保険契約の内容によっては、利用できる範囲が限定されている場合があります。
弁護士費用特約の確認方法
- 保険証券を確認する: 加入している保険の証券に、「弁護士費用特約」の記載があるか確認しましょう。
- 保険会社に問い合わせる: 保険証券が見当たらない場合や、特約の内容がよくわからない場合は、保険会社(または代理店)に問い合わせて確認しましょう。
弁護士費用特約がない場合
弁護士費用特約がない場合でも、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を利用できる可能性があります。
民事法律扶助制度とは、経済的に余裕がない方を対象に、弁護士費用の立て替えなどを行う制度です。
利用には収入や資産などの条件がありますので、法テラスに相談してみましょう。
弁護士費用特約について詳しく解説しました。
次は、交通事故慰謝料支払いまでの期間を短縮する方法についてです。
1-6. 交通事故慰謝料支払いまでの期間を短縮する方法
前の項目では、弁護士費用特約について解説しました。ここでは、交通事故の慰謝料(示談金の一部)支払いまでの期間を短縮する方法について、具体的に見ていきましょう。
慰謝料支払いまでの期間を短縮する方法
慰謝料支払いまでの期間を短縮するためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
- 1. 早期の治療開始と継続:
- 交通事故に遭ったら、すぐに病院で適切な治療を受けましょう。
- 医師の指示に従い、症状が改善するまでしっかりと治療を続けましょう。
- 自己判断で通院を中断すると、治療期間が長引くだけでなく、慰謝料の減額や、後遺障害等級認定に影響が出る可能性があります。
- 2. 適切な後遺障害等級認定の申請:
- 症状固定後、後遺症が残った場合は、適切な後遺障害等級認定を受けることが重要です。
- 後遺障害等級は、慰謝料額に大きく影響するため、専門家(弁護士など)に相談しながら、適切な等級認定を目指しましょう。
- 申請手続きが遅れると、慰謝料支払いも遅れるため、迅速な対応が必要です。
- 3. 弁護士への依頼:
- 弁護士に示談交渉を依頼することで、交渉がスムーズに進み、早期の示談成立が期待できます。
- 弁護士は、示談書の不備チェックや、保険会社との交渉、振込状況の確認など、様々なサポートを提供してくれます。
- 弁護士費用特約を利用すれば、自己負担なしで弁護士に依頼できる場合があります。
- 4. 必要書類の迅速な準備:
- 保険会社から求められる書類(診断書、診療報酬明細書、休業損害証明書など)は、速やかに準備し、提出しましょう。
- 書類に不備があると、手続きが遅れる原因となります。
- 必要書類について、あらかじめ保険会社に確認をしておきましょう
- 5. 保険会社との円滑なコミュニケーション:
- 保険会社の担当者からの連絡には、迅速かつ丁寧に対応しましょう。
- 不明な点や疑問点があれば、遠慮せずに質問しましょう。
- 感情的にならず、冷静に対応することが大切です。
- 6.示談内容の早期合意:
- 提示された示談内容に納得できない場合も、感情的に拒否するのではなく、弁護士と相談しながら、早期の合意を目指して交渉を進めていきましょう。
- 示談交渉が長引くほど、慰謝料支払いも遅れます。
早期解決のメリット
慰謝料支払いまでの期間を短縮することは、被害者にとって以下のようなメリットがあります。
- 経済的な不安の軽減: 早く慰謝料を受け取ることで、治療費や生活費の心配を減らすことができます。
- 精神的な負担の軽減: 示談交渉が長引くと、精神的な負担も大きくなります。早期解決は、精神的な安定にもつながります。
- 次のステップに進める: 慰謝料を受け取り、示談が成立することで、気持ちを切り替えて、次のステップに進むことができます。
交通事故慰謝料支払いまでの期間を短縮する方法について解説しました。
次は、「10対0の事故でも油断禁物!示談金受け取りの注意点」です。
1-7. 10対0の事故でも油断禁物!示談金受け取りの注意点【10対0 事故 示談金 いつもらえる】

ここでは、被害者に過失がない「10対0の事故」の場合でも、示談金受け取りにおいて注意すべき点について解説します。
10対0の事故とは?
10対0の事故とは、交通事故の当事者の一方に100%の過失があり、もう一方には全く過失がない事故のことです。
例えば、信号待ちで停車中に後方から追突された場合などが、典型的な10対0の事故です。
10対0の事故で示談金がもらえるまでの流れ
10対0の事故の場合でも、示談金がもらえるまでの基本的な流れは、他の事故の場合と大きく変わりません。
- 1.事故発生・警察への連絡
- 2.治療
- 3.症状固定または治癒
- 4.後遺障害等級認定(該当する場合)
- 5.示談交渉
- 6.示談成立
- 7.示談書返送
- 8.示談金振込み
10対0の事故で注意すべき点
被害者に過失がない10対0の事故では、「相手の保険会社がすべて対応してくれるから安心」と思いがちですが、以下のような点に注意が必要です。
- 1. 自分の保険会社は示談交渉を代行できない:
- 被害者に過失がない場合、被害者側の保険会社は示談交渉を代行することができません。これは、弁護士法72条(非弁行為の禁止)に抵触する可能性があるためです。
- したがって、被害者は自分で加害者側の保険会社と交渉する必要があります。
- 2. 加害者側の保険会社は、必ずしも被害者の味方ではない:
- 加害者側の保険会社は、あくまで加害者のために示談交渉を行います。
- 示談金を低く抑えようとする可能性があるため、提示された示談金額が適正かどうか、慎重に判断する必要があります。
- 3. 過失割合が0にならないケースもある:
- 事故状況によっては、被害者にもわずかな過失(例えば10対0ではなく、9対1など)が認められる場合があります。
- 過失割合が少しでも変わると、示談金が減額される可能性があります。
- 4. 弁護士費用特約の確認:
被害者に過失がない事故の場合でも、弁護士費用特約が使えることがあります。
弁護士費用特約を使って弁護士に依頼することで、より有利な条件で示談を成立させることができるでしょう
10対0の事故で弁護士に依頼するメリット
- 示談交渉の代行: 被害者に代わって、加害者側の保険会社と交渉してくれます。
- 適正な示談金の獲得: 法律の専門知識に基づいて、適正な示談金を請求してくれます。
- 精神的な負担の軽減: 保険会社との交渉を任せられるため、精神的な負担が軽くなります。
10対0の事故でも油断せず、示談金受け取りにおいて注意すべき点を解説しました。
次は、「通院終了から示談金支払いまでの流れと期間」です。
1-8. 通院終了から示談金支払いまでの流れと期間
ここでは、交通事故の治療が終了(通院終了)してから、示談金が支払われるまでの流れと期間について詳しく解説します。
通院終了とは?
交通事故における「通院終了」とは、以下のいずれかの状態を指します。
- 1. 治癒: 交通事故による怪我が完全に治った状態。
- 2. 症状固定: これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態。
通院終了の判断は、医師が行います。自己判断で通院を中断することは、絶対にやめましょう。
通院終了から示談金支払いまでの流れ
- 1. 通院終了(治癒または症状固定): 医師から治癒または症状固定の診断を受けます。
- 2. 後遺障害等級認定(該当する場合): 症状固定後、後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定の申請を行います。
- 3. 損害額の確定: 治療費、休業損害、慰謝料など、損害額を確定します。
- 治療費: 実際に支払った治療費、通院交通費、入院雑費など。
- 休業損害: 交通事故によって仕事を休んだことによる収入の減少分。
- 慰謝料: 交通事故によって被った精神的苦痛に対する補償。
- 入通院慰謝料: 入院や通院の期間・回数に応じて算定。
- 後遺障害慰謝料: 後遺障害等級に応じて算定。
- 4. 示談交渉: 保険会社と示談交渉を開始します。
- 5. 示談成立: 示談内容に合意し、示談書に署名・捺印します。
- 6. 示談書返送: 保険会社に示談書を返送します。
- 7. 示談金振込み: 保険会社が示談書を受領後、通常1~2週間程度で指定口座に示談金が振り込まれます。
通院終了から示談金支払いまでの期間
通院終了から示談金支払いまでの期間は、ケースバイケースです。
以下に、期間の目安と、期間を左右する要素を示します。
- 目安:
- 治癒の場合: 1~3ヶ月程度
- 症状固定の場合: 3~6ヶ月程度(後遺障害等級認定の申請・審査期間を含む)
- 後遺障害等級認定で争いがある場合: 6ヶ月以上かかることも
- 期間を左右する要素:
- 後遺障害の有無・程度: 後遺障害がある場合は、等級認定の手続きに時間がかかるため、期間が長くなる傾向があります。
- 過失割合: 過失割合に争いがある場合は、示談交渉が長引く可能性があります。
- 保険会社の対応: 保険会社の担当者や、社内体制によって、対応のスピードが異なる場合があります。
- 弁護士の介入: 弁護士に依頼することで、示談交渉がスムーズに進み、期間が短縮される可能性があります。
通院終了後の注意点
- 医師の指示に従う: 通院終了後も、医師から指示されたリハビリや自宅でのケアを続けましょう。
- 示談交渉は慎重に: 保険会社から提示された示談金額が適正かどうか、慎重に判断しましょう。
- 不明な点は専門家に相談: 示談交渉や後遺障害等級認定について、不明な点や疑問点があれば、弁護士などの専門家に相談しましょう。
通院終了から示談金支払いまでの流れと期間について解説しました。
次は、「症状固定とは?後遺障害等級認定と示談金への影響」です。
1-9. 症状固定とは?後遺障害等級認定と示談金への影響
前の項目では、「通院終了」の定義として「治癒」と「症状固定」があることを説明しました。
ここでは、「症状固定」と、それに続く「後遺障害等級認定」、そしてそれが示談金にどのような影響を与えるのかを詳しく解説します。
症状固定とは?
症状固定とは、交通事故による怪我について、「これ以上治療を続けても、症状の改善が見込めない状態」 を指します。
症状固定の判断は、医師が行います。
重要なのは、症状固定は「完治」とは異なるということです。
症状固定後も、痛みやしびれなどの症状が残ることがあります。
後遺障害等級認定とは?
症状固定後、後遺症が残った場合に、その後遺症の程度に応じて、1級から14級までの等級を認定する制度です。
後遺障害等級は、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の基準に基づいて認定されます。
後遺障害等級認定の流れ
- 1. 症状固定: 医師から症状固定の診断を受けます。
- 2. 後遺障害診断書の作成: 医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。
- 3. 申請: 保険会社(または自賠責保険会社)に後遺障害等級認定の申請を行います。
- 4. 審査: 損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)が、提出された書類に基づいて審査を行います。
- 5. 結果通知: 申請者(被害者)に、認定結果が通知されます。
後遺障害等級認定と示談金への影響
後遺障害等級が認定されると、「後遺障害慰謝料」 と 「後遺障害逸失利益」 を請求できるようになります。
- 後遺障害慰謝料: 後遺症が残ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料。等級に応じて金額が定められています。
- 後遺障害逸失利益: 後遺症によって労働能力が低下し、将来得られるはずだった収入が減少することに対する補償。等級や年齢、収入などに応じて算定されます。
後遺障害等級が認定されるかどうか、そして何級に認定されるかによって、示談金(特に慰謝料)の金額が大きく変わる可能性があります。
適切な後遺障害等級認定を受けるために
- 医師との連携: 症状固定の時期や、後遺症の内容について、医師とよく相談しましょう。
- 後遺障害診断書の記載内容: 医師に作成してもらう後遺障害診断書は、非常に重要な書類です。症状が正確に反映されているか、よく確認しましょう。
- 弁護士への相談: 後遺障害等級認定は、専門的な知識が必要となるため、弁護士に相談することをおすすめします。
症状固定、後遺障害等級認定、そしてそれが示談金に与える影響について解説しました。
次は、「保険会社別!示談金振込みタイミングと特徴」です。
1-10. 保険会社別!示談金振込みタイミングと特徴

ここでは、主要な保険会社ごとに、示談金振込みのタイミングや特徴について解説します。
ただし、保険会社によって、また個別の事案によって、対応は異なる可能性があることをご承知おきください。
損保ジャパン
- 示談金振込みタイミング: 示談書到着後、1~2週間程度が目安。
- 特徴:
- 迅速な対応が期待できる。
- 振込予定日を伝えてくれるケースが多い。
三井住友海上
- 示談金振込みタイミング: 示談書到着後、1~2週間程度が目安。
- 特徴:
- 迅速な対応が特徴。
- 示談成立後、振込予定日を伝えてくれるケースが多い。
- 担当者によっては、振込完了後に連絡をくれる場合もある。
東京海上日動
- 示談金振込みタイミング: 示談書到着後、1~2週間程度が目安。
- 特徴:
- 迅速な対応が期待できる。
- 担当者によって、対応に差がある場合がある。
- 着金予定日を教えてくれる場合がある。
あいおいニッセイ同和損保
- 示談金振込みタイミング: 示談書到着後、1~2週間程度が目安。
- 特徴:
- 迅速な対応が特徴。
- 示談成立後、振込予定日を伝えてくれるケースが多い。
- 担当者によっては、振込完了後に連絡をくれる場合もある。
保険会社別の対応の違い(まとめ)
- 振込までの期間: 多くの保険会社で、示談書到着後1~2週間程度が目安ですが、どちらかといえば、保険会社間の差というよりは、担当者の対応によると思われます。
- 振込予定日の連絡: 示談成立後、振込予定日を伝えてくれるケースが多いです。また、聞けば教えてくれるはずです。
- 振込完了の連絡: 保険会社や担当者によって、振込完了後に連絡がある場合と、ない場合があります。
- 問い合わせ窓口: 問い合わせ窓口を設けている保険会社もあります。
振込が遅いと感じたら
示談書を返送してから2週間以上経っても示談金が振り込まれない場合は、以下の方法で確認しましょう。
- 1. 保険会社の担当者に連絡: まずは、保険会社の担当者に連絡し、振込状況を確認しましょう。
- 2. 示談書の到着確認: 保険会社に示談書が届いているか確認しましょう。
- 3. 振込先口座情報の確認: 自分の口座情報(口座番号や名義)に誤りがないか確認しましょう。
保険会社別の示談金振込みタイミングと特徴について解説しました。
2. 交通事故の示談金の振り込みがまだ!弁護士に相談すべきケースと対処法

示談が成立したのに、示談金がなかなか振り込まれない…。
そんな時、どうすれば良いのか、途方に暮れてしまいますよね。
もしかしたら、示談書に不備があったのかもしれないし、保険会社の事情で遅れているのかもしれません。
あるいは、加害者が任意保険に未加入で、支払いに応じないというケースも考えられます。
この章では、示談金が振り込まれない場合の原因や対処法、そして弁護士に相談すべきケースについて詳しく解説していきます。
2-1. 示談金が振り込まれない…よくある原因と対処法

ここでは、示談金が予定通りに振り込まれない場合、どのような原因が考えられるのか、そして、それぞれの原因に対してどのように対処すれば良いのかを解説します。
示談金が振り込まれない主な原因
- 1. 示談書の不備:
- 原因: 署名・捺印漏れ、記入ミス、必要書類の不足など。
- 対処法: 保険会社から連絡があった場合は、指示に従い、速やかに修正・再提出しましょう。弁護士に依頼している場合は、弁護士が対応してくれます。
- 2. 保険会社の内部処理の遅延:
- 原因: 担当者の多忙、決裁の遅れ、システムトラブルなど、保険会社側の事情。
- 対処法: 保険会社の担当者に連絡し、状況を確認しましょう。あまりにも遅い場合は、弁護士に相談することも検討しましょう。
- 3. 振込先口座情報の誤り:
- 原因: 口座番号や名義の間違い。
- 対処法: 保険会社に正しい口座情報を伝え、再度振込手続きを依頼しましょう。
- 4. 加害者が任意保険未加入:
- 原因: 加害者が任意保険に加入していないため、又は保険を使わないため、加害者本人が示談金を支払う必要がある。
- 対処法: 加害者本人に支払いを請求する、または弁護士に相談して、法的な手続き(支払督促、訴訟など)を検討しましょう。
- 5. 加害者の支払い能力不足:
- 原因: 加害者に示談金を支払うだけの経済力がない。
- 対処法: 分割払いの交渉、弁護士に相談して、法的な手続き(強制執行など)を検討しましょう。
- 6. 保険会社の支払い拒否:
- 原因: 保険会社が、事故状況や過失割合などを理由に、示談金の支払いを拒否する。
- 対処法: 弁護士に相談して、交渉や訴訟を検討しましょう。
- 7. やむを得ない事情(大規模災害)などによる遅延
- 原因:地震、台風、津波などの大規模災害により、保険会社の業務が滞る
- 対処法:保険会社からの連絡を待ち、状況を確認しましょう。
原因別の対処法(まとめ)
| 原因 | 対処法 |
|---|---|
| 示談書の不備 | 保険会社の指示に従い、速やかに修正・再提出 |
| 保険会社の内部処理の遅延 | 保険会社の担当者に連絡し、状況を確認。弁護士に相談も検討 |
| 振込先口座情報の誤り | 保険会社に正しい口座情報を伝え、再度振込手続きを依頼 |
| 加害者が任意保険未加入・保険使用なし | 加害者本人に支払いを請求、または弁護士に相談して法的手続きを検討 |
| 加害者の支払い能力不足 | 分割払いの交渉、弁護士に相談して法的手続きを検討 |
| 保険会社の支払い拒否 | 弁護士に相談して、交渉や訴訟を検討 |
| やむを得ない事情による遅延 | 保険会社からの連絡を待ち、状況を確認する |
示談金が振り込まれない場合の原因と対処法について解説しました。
次は、「示談書の内容に不備はないか?確認すべきポイント」です。
2-2. 示談書の内容に不備はないか?確認すべきポイント

示談金が振り込まれない原因の一つとして、「示談書の不備」が挙げられます。ここでは、示談書の内容に不備がないか確認すべきポイントを具体的に解説します。
示談書とは?
示談書とは、交通事故の当事者間で示談が成立したことを証明する書類です。示談書には、示談金額や支払い方法、過失割合など、示談内容に関する重要な事項が記載されます。
確認すべきポイント
- 1. 署名・捺印:
- 示談書の当事者の署名・捺印があるか確認しましょう。
- 免責証書・承諾書では通常、被害者のみです。
- 署名・捺印がない場合、示談金は支払われません。
- 2. 示談金額:
- 示談金額が、合意した金額と一致しているか確認しましょう。
- 金額に誤りがある場合、示談金が正しく支払われない可能性があります。
- 3. 支払い方法:
- 示談金の支払い方法(一括払い、分割払いなど)が、合意した内容と一致しているか確認しましょう。
- 振込先口座情報が記載されている場合は、口座番号や名義に誤りがないか確認しましょう。
- 4. 過失割合:
- 過失割合が記載されている場合、合意した割合と一致しているか確認しましょう。
- 過失割合に誤りがある場合、示談金額が変更される可能性があります。
- 5. 事故発生状況:
- 事故発生日時、場所、状況などが、正確に記載されているか確認しましょう。
- 事故を特定できない場合、再度書式を作成する必要があります。
- 6. 当事者の情報:
- 当事者の氏名、住所、連絡先などが、正確に記載されているか確認しましょう。
- 情報に誤りがある場合、示談金の支払いが遅れる可能性があります。
- 7. 後遺障害に関する記載(該当する場合):
- 後遺障害等級、労働能力喪失率などに基づいて、賠償額が正確に記載されているか確認しましょう。
- そもそも計算根拠に誤りがある場合、安易に示談書に署名押印してはいけません。
- 8. 清算条項:
- 「本示談書に定めるもののほか、一切の請求をしない」という清算条項が記載されているか確認しましょう。
- 「後遺障害については別途協議する」などの留保条項が設けられることもあります。
- 9. その他:
- 示談書に記載されている内容で、不明な点や疑問点がないか確認しましょう。
- 不明な点や疑問点がある場合は、保険会社や弁護士に質問しましょう。
示談書に不備があった場合
示談書に不備があった場合は、保険会社から連絡があります。
保険会社の指示に従い、速やかに修正・再提出しましょう。
弁護士に依頼している場合は、弁護士が対応してくれます。
示談書の内容に不備がないか確認すべきポイントを解説しました。
次は、「振込先口座情報に誤りはないか?再確認の方法」です。
2-3. 振込先口座情報に誤りはないか?再確認の方法
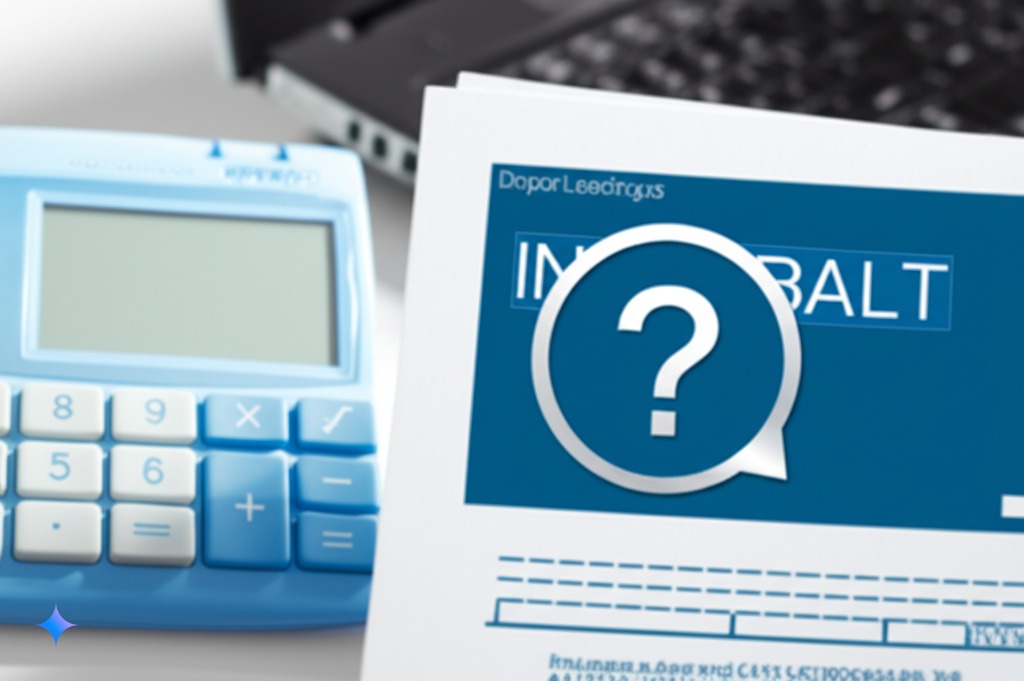
示談金が振り込まれない原因として、示談書の内容の不備のほかに、「振込先口座情報の誤り」も考えられます。ここでは、振込先口座情報に誤りがないか再確認する方法と、誤りがあった場合の対処法について解説します。
振込先口座情報とは?
示談金の振込先として指定した、銀行名、支店名、口座種類(普通・当座など)、口座番号、口座名義(カタカナ)のことです。
再確認の方法
- 1. 示談書の控えを確認:
- 示談書の控えに記載されている振込先口座情報と、通帳やキャッシュカードに記載されている情報を照らし合わせ、誤りがないか確認しましょう。
- 2. 保険会社に連絡:
- 保険会社の担当者に連絡し、示談書に記載した振込先口座情報を再度伝え、誤りがないか確認してもらいましょう。
- 3. 銀行に問い合わせ(必要な場合):
- 口座名義の表記(カタカナ)が正しいか不安な場合は、銀行に問い合わせて確認しましょう。
- 特に、旧姓から新姓に変更した場合や、結婚などで姓が変わった場合は、注意が必要です。
よくある間違い
- 口座番号の入力ミス: 一桁間違えただけでも、振込みはできません。
- 口座名義の入力ミス:
- カタカナ表記が間違っている。(例: ヤマダ タロウ → ヤマダ タロー)
- 旧姓のままになっている。
- 株式会社を(株)と略している。
- 屋号付き口座で、屋号部分を省略している。
- 支店名の入力ミス
- 支店番号の入力ミス
振込先口座情報に誤りがあった場合
振込先口座情報に誤りがあった場合は、速やかに保険会社の担当者に連絡し、正しい情報を伝えましょう。
保険会社は、正しい情報に基づいて、再度振込手続きを行います。
振込先口座情報を変更したい場合
示談書を提出した後で、振込先口座情報を変更したい場合は、速やかに保険会社の担当者に連絡し、変更手続きについて相談しましょう。
保険会社によっては、変更手続きに時間がかかる場合や、変更できない場合があります。
振込先口座情報に誤りがないか再確認する方法と、誤りがあった場合の対処法について解説しました。
次は、「保険会社の担当者に連絡!確認すべきことリスト」です。
2-4. 保険会社の担当者に連絡!確認すべきことリスト

示談金が予定通りに振り込まれない場合、まずは保険会社の担当者に連絡し、状況を確認することが大切です。ここでは、保険会社の担当者に連絡する際に確認すべきこと、そして連絡する際の注意点について解説します。
確認すべきことリスト
- 1. 示談金の振込状況:
- 示談金がいつ振り込まれる予定なのか、具体的な日付を確認しましょう。
- すでに振込手続きが完了しているのか、まだ手続き中なのかを確認しましょう。
- 2. 示談書の到着確認:
- 保険会社に示談書が届いているか確認しましょう。
- いつ届いたのか、具体的な日付を確認しましょう。
- 3. 示談書の内容確認:
- 示談書の内容に不備がないか確認しましょう。
- 不備があった場合は、どのように修正すれば良いのか確認しましょう。
- 4. 振込先口座情報の確認:
- 示談書に記載した振込先口座情報に誤りがないか確認しましょう。
- 誤りがあった場合は、正しい情報を伝えましょう。
- 5. 遅延理由の確認:
- 示談金の振込みが遅れている場合は、その理由を確認しましょう。
- 保険会社側の事情なのか、それとも他に原因があるのかを確認しましょう。
- 6. 今後の対応
- いつまでに振り込まれるのか、具体的な目途を確認しましょう。
- 今後、何か必要な手続きがあるか確認しましょう。
連絡する際の注意点
- 冷静に対応する: 感情的にならず、冷静に状況を確認しましょう。
- 担当者の名前を確認する: 担当者の名前を確認し、記録しておきましょう。
- 確認した内容をメモする: 確認した内容や、担当者から指示されたことなどをメモしておきましょう。
- 言った・言わないのトラブルを防ぐ: 重要な内容は、メールや書面など、記録に残る形でやり取りしましょう。
- 弁護士に相談する: 状況が改善しない場合や、保険会社の対応に不満がある場合は、弁護士に相談することも検討しましょう。
連絡手段
- 電話: 最も一般的な連絡手段です。
- メール: 記録に残るため、言った・言わないのトラブルを防ぐことができます。
- FAX: 書面でやり取りしたい場合に利用します。
- 郵送: 重要書類を送付する際に利用します。
保険会社の担当者に連絡する際に確認すべきこと、そして連絡する際の注意点について解説しました。
次は、「示談金振込みの遅延…弁護士に相談するメリット」です。
2-5. 示談金振込みの遅延…弁護士に相談するメリット

示談金が予定通りに振り込まれない場合、保険会社の担当者に連絡しても状況が改善しない、あるいは保険会社の対応に不満があるといった場合には、弁護士に相談することを検討しましょう。ここでは、示談金振込みの遅延に関して弁護士に相談するメリットを解説します。
弁護士に相談するメリット
- 1. 原因究明のサポート:
- 弁護士は、法律の専門知識に基づいて、示談金振込みが遅延している原因を特定するためのサポートをしてくれます。
- 示談書の内容、保険会社とのやり取り、加害者の状況など、様々な角度から原因を分析します。
- 2. 保険会社との交渉代行:
- 弁護士は、被害者に代わって保険会社と交渉し、示談金の早期振込みを促します。
- 保険会社は、弁護士からの連絡を無視したり、不誠実な対応をしたりすることは難しくなります。
- 3. 法的手続きの検討:
- 保険会社が示談金の支払いに応じない場合、弁護士は、法的手続き(支払督促、訴訟など)を検討し、被害者の権利を守るための最善の方法を提案します。
- 4. 加害者本人への請求:
- 加害者が任意保険に未加入の場合、弁護士は、加害者本人に対して示談金の支払いを請求します。
- 加害者が支払いに応じない場合は、法的手続きを検討します。
- 5. 精神的な負担の軽減:
- 示談金振込みの遅延は、被害者にとって大きなストレスとなります。
- 弁護士に相談することで、精神的な負担を軽減し、安心して問題解決に取り組むことができます。
- 6. 証拠収集のサポート:
- 訴訟になった場合に備えて、弁護士は必要な証拠(事故現場の写真、診断書、診療報酬明細書など)の収集をサポートします。
弁護士に相談するタイミング
- 示談成立後、2週間以上経過しても示談金が振り込まれない場合
- 保険会社の担当者に連絡しても、状況が改善しない場合
- 保険会社の対応に不満がある場合
- 加害者が任意保険に未加入の場合
- 加害者が示談金の支払いに応じない場合
- 示談交渉が難航している場合
弁護士費用の心配
弁護士に相談・依頼すると、弁護士費用が発生しますが、弁護士費用特約に加入していれば、自己負担なしで弁護士に依頼できる場合があります。
まずは、加入している保険の契約内容を確認し、弁護士費用特約が利用できるかどうか確認しましょう。
示談金振込みの遅延に関して弁護士に相談するメリットを解説しました。
次は、「弁護士に依頼して解決できる振込み問題とは?」です。
2-6. 弁護士に依頼して解決できる振込み問題とは?
前の項目では、示談金振込みの遅延について弁護士に相談するメリットを解説しました。ここでは、具体的にどのような振込み問題を弁護士に依頼することで解決できるのか、詳しく見ていきましょう。
弁護士に依頼して解決できる主な振込み問題
- 1. 保険会社が示談金の支払いを遅延している:
- 弁護士が保険会社に連絡し、支払いを促します。
- 必要に応じて、法的手続き(支払督促、訴訟など)を検討します。
- 2. 保険会社が示談金の支払いを拒否している:
- 弁護士が保険会社と交渉し、支払いを求めます。
- 交渉がうまくいかない場合は、訴訟を提起して、裁判所に支払いを命じてもらうことも可能です。
- 3. 示談書の内容に不備がある:
- 弁護士が示談書の内容をチェックし、不備があれば修正を求めます。
- 被害者にとって不利な条項があれば、修正を交渉します。
- 4. 加害者が任意保険に未加入:
- 弁護士が加害者本人に示談金の支払いを請求します。
- 加害者が支払いに応じない場合は、法的手続き(支払督促、訴訟、強制執行など)を検討します。
- 5. 加害者に支払い能力がない:
- 弁護士が加害者の財産状況を調査し、回収可能な財産があるか確認します。
- 分割払いの交渉や、強制執行などの手続きを検討します。
- 6. 過失割合に争いがある:
- 弁護士が事故状況を詳しく調査し、証拠を集めて、適切な過失割合を主張します。
- 過失割合が有利になれば、示談金が増額される可能性があります。
- 7. 後遺障害等級認定に不服がある:
- 弁護士が異議申し立ての手続きをサポートし、適切な等級認定を求めます。
- 後遺障害等級が上がれば、示談金が増額される可能性があります。
- 8. 示談金額が低いと感じる:
示談金額について、弁護士が、法的な視点から金額の妥当性を判断します。
金額が妥当でないと判断した場合は、増額請求をします。
弁護士に依頼する際の注意点
- 弁護士費用: 弁護士に依頼すると、費用が発生します。弁護士費用特約の有無を確認しましょう。
- 弁護士との相性: 弁護士との相性も重要です。信頼できる弁護士を選びましょう。
- 解決の見込み: 弁護士に相談しても、必ずしも希望通りの結果になるとは限りません。事前に、解決の見込みについて、弁護士とよく相談しましょう。
弁護士に依頼することで解決できる振込み問題について解説しました。
次は、「弁護士基準で慰謝料増額!」です。
2-7. 弁護士基準で慰謝料増額!
交通事故の慰謝料には、いくつかの算定基準があり、どの基準を用いるかによって金額が大きく変わることがあります。ここでは、「弁護士基準」で慰謝料を請求することのメリットと、増額の可能性について解説します。
慰謝料の算定基準
交通事故の慰謝料には、主に以下の3つの算定基準があります。
- 1. 自賠責基準:
- 自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)で定められている基準。
- 最低限の補償を目的としているため、3つの基準の中で最も低い金額になる。
- 2. 任意保険基準:
- 各保険会社が独自に設定している基準。
- 自賠責基準よりは高いが、弁護士基準よりは低い金額になることが多い。
- 3. 弁護士基準(裁判基準):
- 過去の裁判例に基づいて設定されている基準。
- 3つの基準の中で最も高い金額になる。
- 弁護士に依頼した場合、この基準で慰謝料を請求することが可能。
弁護士基準で慰謝料を請求するメリット
- 慰謝料が増額される可能性が高い: 弁護士基準は、他の基準よりも高額な慰謝料を算定できるため、示談金が増額される可能性が高まります。
- 適切な賠償を受けられる: 弁護士基準は、被害者が被った精神的苦痛をより適切に評価した金額と言えます。
- 保険会社との交渉を有利に進められる: 弁護士が介入することで、保険会社は弁護士基準を前提とした交渉に応じざるを得なくなる場合があります。
弁護士基準で慰謝料を請求する際の注意点
- 必ずしも増額されるとは限らない: 弁護士基準で請求しても、必ずしも示談金が増額されるとは限りません。
- 弁護士費用がかかる: 弁護士に依頼すると、費用が発生します。弁護士費用特約の有無を確認しましょう。
弁護士基準で慰謝料を請求することのメリットと、増額の可能性について解説しました。
次は、「慰謝料・示談金が増額される主なケースとは」です。
2-8. 慰謝料・示談金が増額される主なケースとは

ここでは、具体的にどのようなケースで慰謝料や示談金が増額される可能性があるのか、詳しく見ていきましょう。
慰謝料・示談金が増額される主なケース
- 1. 弁護士に依頼した場合:
- 弁護士は、弁護士基準(裁判基準)で慰謝料を請求するため、自賠責基準や任意保険基準で算定された金額よりも高くなる可能性があります。
- 専門知識や交渉スキルを駆使して、保険会社と対等に交渉するため、増額の可能性が高まります。
- 2. 後遺障害等級が認定された場合:
- 後遺症が残り、後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できます。
- 後遺障害の程度が重いほど、慰謝料や逸失利益の金額は高くなります。
- 3. 適切な後遺障害等級に認定された場合:
- 後遺障害等級が、実際の症状よりも低く認定された場合、異議申し立てを行うことで、より適切な等級に認定される可能性があります。
- 等級が上がれば、慰謝料や逸失利益が増額されます。
- 4. 過失割合が有利になった場合:
- 過失割合に争いがある場合、弁護士が事故状況を詳しく調査し、証拠を集めて、被害者側の過失割合を減らす、または無くすことができれば、示談金が増額されます。
- 5. 休業損害が適切に算定された場合:
- 休業損害は、交通事故によって仕事を休んだことによる収入の減少分です。
- 休業日数や基礎収入が適切に算定されれば、休業損害が増額され、結果として示談金も増額されます。
- 6. 入通院期間が長い場合:
- 入通院慰謝料は、入通院期間や通院頻度に応じて算定されます。
- 入通院期間が長ければ長いほど、慰謝料は高くなります。
- 7. 重傷を負った場合:
- 骨折、脱臼、神経損傷など、重傷を負った場合は、慰謝料が高くなる傾向があります。
- 8. 死亡事故の場合:
- 死亡事故の場合、死亡慰謝料(本人分、近親者分)や死亡逸失利益が請求できます。
- これらの金額は高額になるため、示談金も高額になります。
- 9. その他:
- 主婦(主夫)や学生、無職の方でも、休業損害や逸失利益が認められる場合があります。
- 事故によって、将来の介護費用が必要になった場合、その費用も請求できます。
増額の可能性を高めるために
- 弁護士に相談する: 示談金増額の可能性について、専門的なアドバイスを受けられます。
- 証拠を集める: 事故状況に関する証拠(事故現場の写真、診断書、診療報酬明細書など)を集めましょう。
- 適切な治療を受ける: 医師の指示に従い、症状が改善するまでしっかりと治療を受けましょう。
- 後遺障害等級認定の申請: 後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定の申請を行いましょう。
慰謝料・示談金が増額される主なケースについて解説しました。
次は、「事故示談金振込みに関するよくある質問」です。
2-9. Q&A 交通事故示談金振込みに関するよくある質問

ここでは、交通事故の示談金振込みに関して、よくある質問とその回答をQ&A形式でまとめます。
Q1: 示談金はいつ振り込まれますか?
A1: 通常、示談成立後、示談書が保険会社に到着してから1~2週間程度で振り込まれます。ただし、保険会社や個別の状況によって異なる場合があります。
Q2: 示談金が振り込まれない場合はどうすれば良いですか?
A2: まずは、保険会社の担当者に連絡し、状況を確認しましょう。それでも解決しない場合は、弁護士に相談することを検討しましょう。
Q3: 示談書に不備があった場合はどうなりますか?
A3: 保険会社から連絡がありますので、指示に従い、速やかに修正・再提出しましょう。
Q4: 振込先口座情報を間違えてしまった場合はどうすれば良いですか?
A4: 速やかに保険会社の担当者に連絡し、正しい情報を伝えましょう。
Q5: 弁護士に依頼すると、示談金は必ず増額されますか?
A5: 必ずしも増額されるとは限りませんが、弁護士基準で慰謝料を請求できるため、増額される可能性は高まります。
Q6: 弁護士費用特約とは何ですか?
A6: 自動車保険などに付帯できる特約で、交通事故のトラブルで弁護士に相談・依頼する際の費用を、保険会社が負担してくれるものです。
Q7: 弁護士費用特約がない場合、弁護士に依頼できませんか?
A7: 弁護士費用特約がなくても、弁護士に依頼することは可能です。その場合、弁護士費用は自己負担となります。法テラスの民事法律扶助制度を利用できる場合もあります。
Q8: 10対0の事故の場合、自分の保険会社は示談交渉をしてくれますか?
A8: 被害者に過失がない場合、被害者側の保険会社は示談交渉を代行できません。
Q9: 症状固定とは何ですか?
A9: これ以上治療を続けても、症状の改善が見込めない状態のことです。
Q10: 後遺障害等級認定とは何ですか?
A10: 症状固定後、後遺症が残った場合に、その後遺症の程度に応じて、1級から14級までの等級を認定する制度です。
Q11:加害者が任意保険に未加入の場合、示談金はもらえないのですか?
A11:いいえ、加害者が任意保険に未加入でも、示談金をもらうことは可能です。加害者本人に直接請求するか、自賠責保険に被害者請求を行う方法があります。弁護士に相談することをおすすめします。
Q&A形式で、交通事故示談金振込みに関するよくある質問とその回答をまとめました。
2-11. まとめ:交通事故の示談金振込みは弁護士に依頼してスムーズ&確実に!
この記事では、交通事故の示談金がいつ振り込まれるのか、振込みまでの流れ、振込みが遅れる原因と対処法、そして弁護士に依頼するメリットについて詳しく解説してきました。
記事のポイントまとめ
- 示談金振込みまでの期間: 通常、示談成立後、示談書が保険会社に到着してから1~2週間程度。
- 振込みが遅れる原因: 示談書の不備、保険会社の内部処理の遅延、振込先口座情報の誤り、加害者が任意保険未加入、など。
- 振込みが遅れた場合の対処法: 保険会社の担当者に連絡、示談書や口座情報の確認、弁護士に相談。
- 受け取りが弁護士の口座の場合、弁護士費用や実費を清算して、依頼者の口座に支払われることもあるので、時間がかかることもある。
- 弁護士に依頼するメリット: 示談交渉の迅速化、示談書の不備防止、保険会社へのプレッシャー、慰謝料増額の可能性、法的手続きのサポート、精神的な負担の軽減。
- 弁護士費用特約: 弁護士費用を保険会社が負担してくれる特約。自己負担なしで弁護士に依頼できる場合がある。
- 慰謝料の算定基準: 自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)があり、弁護士基準が最も高額。
- 示談金が増額されるケース: 弁護士に依頼した場合、後遺障害等級が認定された場合、過失割合が有利になった場合、など。
- 10対0の事故: 被害者側の保険会社は示談交渉を代行できないため、注意が必要。
- 通院終了後: 示談交渉が始まり、示談成立後に示談金が振り込まれる。
- 症状固定: これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態。後遺障害等級認定に関わる。
結論
交通事故の示談金振込みは、様々な要因によって遅れる可能性があります。
しかし、弁護士に依頼することで、スムーズな示談交渉、適切な示談金獲得、そして早期の振込みが期待できます。
特に、以下のような場合は、弁護士に相談することを強くおすすめします。
- 示談金がなかなか振り込まれない
- 保険会社の対応に不満がある
- 示談金額に納得できない
- 後遺障害が残った
- 過失割合に争いがある
- 加害者が任意保険に未加入
弁護士費用特約に加入していれば、自己負担なしで弁護士に依頼できる可能性があります。
まずは、加入している保険の契約内容を確認し、弁護士費用特約が利用できるかどうか確認しましょう。
交通事故の被害に遭われた方が、この記事を参考に、適切な示談金を受け取り、一日も早く平穏な生活を取り戻せることを願っています。














