
はじめに ~交通事故、その過失割合、本当に適正ですか?~
交通事故は、ある日突然、誰の身にも起こりうるものです。
もし、あなたが交通事故の被害者になってしまったら…
- 突然の出来事に、どうすれば良いのか分からない…
- 怪我の痛みや、精神的なショックで、冷静な判断ができない…
- 保険会社から提示された過失割合に、納得がいかない…
このような状況に陥ってしまうのは、決して珍しいことではありません。
特に、「過失割合」は、多くの方がつまずきやすいポイントです。
保険会社から提示された過失割合を、よく理解しないまま受け入れてしまい、後々後悔するケースも少なくありません。
なぜ、過失割合が重要なのか?
それは、過失割合が、最終的に受け取れる賠償金額と、相手へのお支払額を大きく左右するからです。
たとえ10%の違いでも、賠償金額が数十万円、数百万円と変わってくることもあります。
しかし、保険会社が提示する過失割合は、必ずしも被害者にとって有利なものとは限りません。
必ずしも事故状況を正確に把握していなかったり、事故状況の評価が誤っていることがあるからです。
そこで、この記事では、交通事故の過失割合について解説します。
- 過失割合の基本的な知識から、
- 保険会社との交渉術、
- 弁護士に依頼するメリット、
- 事故状況、過失割合の立証方法、
- そして、実際に過失割合が修正された事例まで、
余すところなくお伝えします。
この記事を読んで、過失割合で泣き寝入りすることが少しでも少なくなれば幸いです。
適正な賠償金を受け取るための知識と戦略を身につけ、自信を持って保険会社と交渉できるようになりましょう。
目次
- 1. 交通事故の過失割合とは? 知っておくべき基本と賠償金への影響
- 2. 過失割合は誰が決めるのか? 示談交渉のプロセスと注意点
- 3. 保険会社提示の過失割合は本当に正しい? 問題点と反論のポイント
- 4. 過失割合を有利に変える! 弁護士の交渉術と証拠収集の具体的手法
- 5. 弁護士費用特約とは? 費用負担を軽減する賢い選択
- 6. 過失割合の立証を変える! トレンドと活用事例
- 7. 過失割合の修正に成功した事例集 ~弁護士の力で勝ち取った逆転劇~
- 8. 交通事故の過失割合 よくある質問(Q&A)
- 9. まとめ 弁護士に相談して、適正な過失割合と納得のいく解決を!
1. 交通事故の過失割合とは? 知っておくべき基本と賠償金への影響
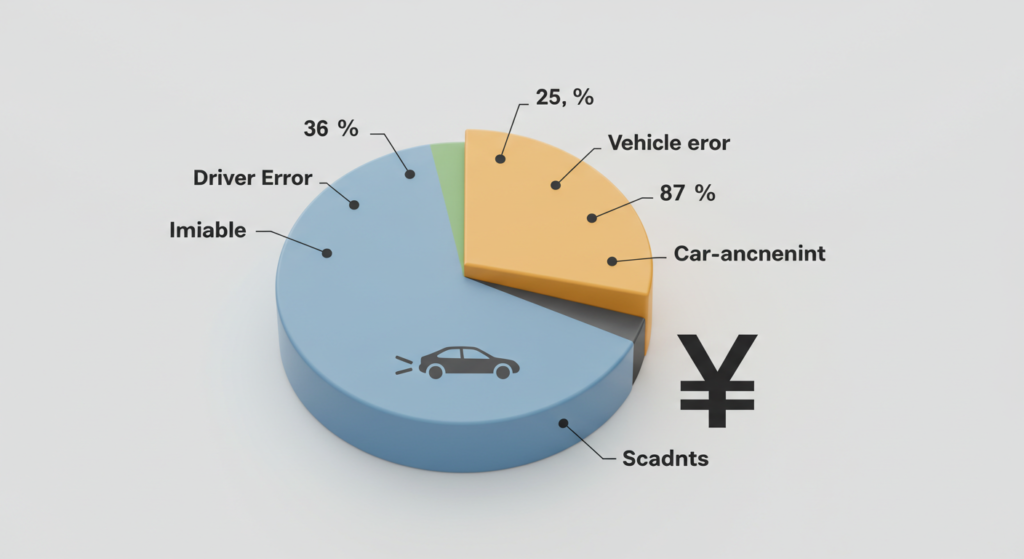
1.1 過失割合とは? 定義と重要性
過失割合とは、交通事故が発生した原因について、加害者と被害者双方の責任の度合いを割合(%)で示したものです。
例えば、過失割合が「加害者80%:被害者20%」の場合、事故の原因の80%は加害者にあり、20%は被害者にも責任があるという意味になります。「責任割合」という言葉を使うこともあります。
なぜ過失割合が重要なのか?
過失割合は、最終的な賠償金額に大きく影響します。
被害者にも過失があると判断された場合、「過失相殺」といって、その過失割合に応じて賠償金が減額されてしまうからです。
1.2 過失割合はどのように決まるのか? 基準と修正要素
過失割合は、以下の要素を総合的に考慮して判断されます。
- 基本過失割合:
過去の裁判例(判例)を基にした「別冊判例タイムズ38号」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)などの基準によって、事故の類型ごとに、基本的な過失割合が定められています。 - 修正要素:
個々の事故の具体的な状況に応じて、基本過失割合は修正されます。

1.3 過失割合と賠償金の関係 具体的な計算例
過失割合が賠償金にどのように影響するのか、具体的な計算例を見てみましょう。
例:損害額1000万円の事故
| 過失割合(被害者:加害者) | 被害者の過失による減額 | 過失相殺後の損害額 |
|---|---|---|
| 0%:100% | 0円 | 1000万円 |
| 10%:90% | 100万円(1000万円 × 10%) | 900万円 |
| 20%:80% | 200万円(1000万円 × 20%) | 800万円 |
| 30%:70% | 300万円(1000万円 × 30%) | 700万円 |
| 50%:50% | 500万円(1000万円 × 50%) | 500万円 |
このように、被害者の過失割合が大きくなるほど、受け取れる賠償金は減ってしまいます。また、相手にも損害が発生している場合、相手から、自分の過失割合分の請求を受けることになります(自分の加入する任意保険に対人保険・対物保険が付帯されているのであれば、賠償額にもよりますが、対人保険・対物保険を使用してお支払いをすることになります)。

1.4 過失割合の種類 代表的な事故類型と基本割合
交通事故には、さまざまな類型があります。ここでは、四輪車同士の代表的な事故類型と、その基本的な過失割合を紹介します。これに、個別の修正要素が考慮され、加算ないし減算されることになります。
(注:下記は、あくまでも参考です。実際の事故の状況によって、過失割合は異なってきます。)
| 事故類型 | 基本的な過失割合 |
|---|---|
| 信号無視(赤信号無視) | 0%:100% |
| 追突事故(後方からの追突) | 0%:100% |
| 右直事故(右折車と対向直進車の事故) | 20%(直進車):80%(右折車) |
| 道路外出入車と直進車との事故 | 20%(直進車):80%(道路外出入車) |
| 進路変更車と後続直進車との事故 | 30%(後続直進車):70%(進路変更車) |
| センターオーバー(対向車同士) | 0%:100% |
2. 過失割合は誰が決めるのか? 示談交渉のプロセスと注意点

2.1 示談交渉の流れ 事故発生から解決までのステップ
交通事故の過失割合は、通常、加害者側の保険会社との示談交渉によって決まります。
示談交渉の流れは、以下のようになります。
- 事故発生・警察への届け出:
まずは、必ず警察に届け出をしましょう。人身事故の場合は、必ず病院で診察を受け、診断書をもらってください。 - 保険会社への連絡:
自分が加入している保険会社に、事故の連絡をします。 - 治療・通院:
怪我の治療に専念しましょう。通院の際は、領収書や診断書などをきちんと保管しておきましょう。過失割合にもよりますが、相手保険会社が治療費の対応をします。 - 保険会社からの連絡・過失割合の提示:
加害者側の保険会社から連絡があり、過失割合が提示されます。こちらにも過失が発生する場合、保険会社の物損担当者同士の過失割合の交渉になります。 - 示談交渉:
保険会社が提示した過失割合や賠償金額に納得できない場合は、交渉を行います。 - 示談成立・示談不成立:
過失割合や賠償金額に合意できれば示談成立、合意できなければ示談不成立となり、裁判手続きに進むこともあります。

2.2 保険会社との交渉における注意点 知っておくべきポイント
保険会社との示談交渉では、以下の点に注意しましょう。
- 安易に示談に応じない:
保険会社が提示した過失割合や賠償金額に納得できない場合は、安易に示談に応じないようにしましょう。一度示談が成立してしまうと、後から覆すことは非常に困難です。また、物損示談時の過失割合で、人損についても賠償提示がなされます。 - 不利な発言をしない:
保険会社との会話は、録音されていると考えていいです。不用意な発言や、自分に不利になるような発言はしないようにしましょう。 - わからないことは質問する:
保険会社の説明で分からないことや、疑問に思うことは、遠慮せずに質問しましょう。 - 必要書類をきちんと保管する:
事故に関する書類(事故証明書、診断書、領収書など)は、きちんと保管しておきましょう。

2.3 示談交渉が決裂した場合の対応 裁判手続きの流れ
示談交渉が決裂した場合、以下の方法で解決を図ることになります。
- 調停:
裁判所の調停委員会が間に入り、話し合いによる解決を目指します。 - ADR(裁判外紛争解決手続):
公益財団法人交通事故紛争処理センター、公益財団法人日弁連交通事故相談センターなどの紛争解決機関が間に入り、話し合いによる解決を目指します。公益財団法人交通事故紛争処理センターの裁定には、片面的拘束力があります(保険会社は事実上応じなければならないが、被害者は受諾するか自由)。 - 裁判:
裁判所に訴訟を提起し、裁判官の判決によって解決を図ります。
3. 保険会社提示の過失割合は本当に正しい? 問題点と反論のポイント
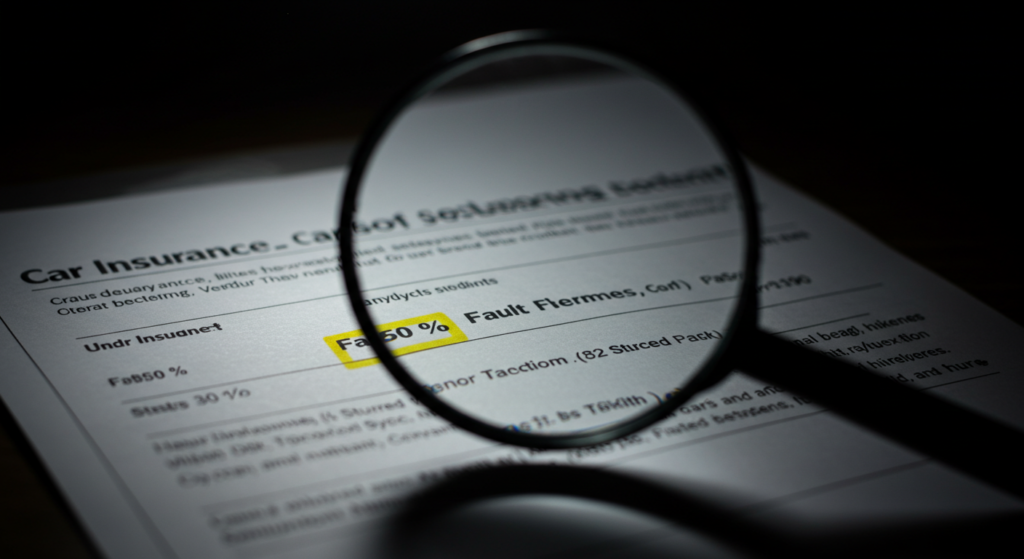
3.1 なぜ保険会社は被害者に不利な過失割合を提示するのか?
相手方の保険会社の顧客は、相手方です。すなわち、相手方の保険会社は、相手方の意向に沿って、示談交渉もしなければなりません。また、必ずしも事故状況を正確に把握していなかったり、事故状況の評価が誤っていることがあります。
そのため、被害者の過失を大きく見積もり、被害者に不利な過失割合を提示することもあります。
3.2 保険会社が主張する過失割合の問題点 具体例と反論のポイント
保険会社が主張する過失割合には、以下のような問題点がある場合があります。
- 事故状況の誤った解釈:
保険会社は、事故現場の状況や当事者の証言などを十分に調査せず、一方的な解釈で過失割合を判断することがあります。 - 過去の裁判例の誤った適用:
保険会社は、過去の裁判例を参考に過失割合を判断しますが、個々の事故の状況を正確に反映していないことがあります。 - 被害者の過失の過大評価:
保険会社は、被害者のちょっとした不注意を、修正要素として大きく評価することがあります。

具体的な反論のポイント
- ドライブレコーダーの映像:
ドライブレコーダーの映像は、事故状況を客観的に示す証拠となります。映像を分析し、保険会社の主張の矛盾点を指摘しましょう。 - 実況見分調書:
警察が作成する実況見分調書は、事故現場の状況を詳細に記録したものです。実況見分調書の内容と保険会社の主張が異なる場合は、その点を指摘しましょう。弁護士に依頼すれば、弁護士会照会という手続きにより取得してもらうことが可能です。 - 目撃者の証言:
目撃者の証言は、事故状況を裏付ける有力な証拠となります。目撃者がいる場合は、その証言を保険会社に伝えましょう。 - 専門家の意見:
必要に応じて、交通事故鑑定人などの専門家の意見を求め、保険会社の主張の誤りを指摘しましょう。例えば、車両の損傷から、車両の動静が判明することもあります。また、調査会社に依頼して、現場の正確な図面を作成してもらうことも有用です。
3.3 過失割合の不当性を判断するためのチェックリスト
保険会社が提示した過失割合が不当かどうかを判断するためのチェックリストを以下に示します。
- 保険会社の説明に納得できない点がある
- 事故状況と保険会社の主張に矛盾がある
- ドライブレコーダーの映像や実況見分調書などの証拠がある
- 目撃者の証言がある
- 弁護士に相談して、意見を聞いた
4. 過失割合を有利に変える! 弁護士の交渉術と証拠収集の具体的手法

4.1 弁護士に依頼するメリット 交渉力、専門知識、そして…
交通事故の過失割合で悩んでいるなら、弁護士に依頼することを強くおすすめします。
弁護士に依頼するメリットは、以下の通りです。
- 交渉力:
弁護士は、法律の専門知識と豊富な交渉経験を活かして、保険会社と対等に交渉します。 - 専門知識:
弁護士は、交通事故に関する書籍や裁判例のデータベースを持っており、被害者に有利な過失割合を主張するための法的根拠を示します。 - 証拠収集力:
弁護士は、ドライブレコーダーの映像解析、実況見分調書の入手など、さまざまな方法で証拠を収集し、被害者の主張を裏付けます。 - 精神的サポート:
弁護士は、被害者の精神的な負担を軽減し、安心して交渉を進められるようにサポートします。

4.2 弁護士の交渉術 具体的な交渉テクニックと成功事例
弁護士は、以下のような交渉テクニックを駆使して、過失割合を有利に変えていきます。
- 法的根拠に基づいた主張:
弁護士は、法律や有利な裁判例に基づいて、被害者に有利な過失割合を主張します。 - 証拠に基づいた反論:
弁護士は、収集した証拠に基づいて、保険会社の主張の矛盾点や誤りを指摘します。 - 粘り強い交渉:
弁護士は、保険会社が容易に譲歩しない場合でも、粘り強く交渉を続け、被害者の利益を最大限に守ります。
成功事例
- どちらが車線変更したか争いになった事件で、被害者の過失割合を50%から20%に修正
- 右直事故で、被害者の過失割合を20%から10%に修正
- 駐車場内の事故で、防犯カメラの開示を行い、被害者の過失割合を50%から30%に修正
4.3 証拠収集の具体的手法 ドライブレコーダー、実況見分調書、目撃者…
弁護士は、以下のような方法で証拠を収集します。
- ドライブレコーダーの映像解析:
ドライブレコーダーの映像は、事故状況を客観的に示す重要な証拠となります。弁護士は、映像を詳細に分析し、速度や位置関係などを明らかにします。搭載していない場合は、搭載しておくことをお勧めします(衝撃が加わったときのみ作動するものではなく、24時間撮影してくれるものが良いです)。 - 実況見分調書、刑事記録の入手:
警察が作成する実況見分調書や刑事記録は、事故状況を把握するための重要な資料です。弁護士は、これらの資料を取り寄せ、事故原因を分析します。なお、物損事故の場合は物件事故報告書という図面が作成されていることが多いですが、実況見分調書よりも簡略な記載にとどまります。 - 目撃者の証言:
目撃者の証言は、事故状況を裏付ける有力な証拠となります。ただ、現実的に目撃者を見つけることは困難です。 - 防犯カメラ映像の確認:
事故現場付近に設置されている防犯カメラの映像を確認し、事故状況の証拠となる映像がないか調べます。特に、コンビニ・ドラッグストア・ホームセンター等に設置されていることがありますが、保存期間が限られており、注意が必要です。
4.4 弁護士が活用する専門家 交通事故鑑定人、医師…
弁護士は、必要に応じて、以下のような専門家の協力を得て、過失割合の立証を強化します。
- 交通事故鑑定人:
交通事故鑑定人は、事故現場の状況や車両の損傷状況などを分析し、事故原因や過失割合について専門的な意見を述べます(鑑定会社の方は、過去に保険会社のアジャスタ―であった人も多くいます)。 - 医師:
医師は、被害者の怪我の状況や治療経過などを診断し、後遺障害の有無や程度について意見を述べます。 - 保険会社のアジャスター:
保険会社のアジャスタ―に、自動車工学に関する知識を応用して、事故時の損傷の発生機序や、衝撃メカニズムを分析してもらいます。
5. 弁護士費用特約とは? 費用負担を軽減する賢い選択

5.1 弁護士費用特約とは? 仕組みとメリット
弁護士費用特約とは、自動車保険や火災保険などに付帯できる特約で、交通事故の被害に遭った際に、弁護士に相談・依頼する費用を保険会社が負担してくれるものです。
弁護士費用特約の仕組み
弁護士費用特約に加入している場合、交通事故の被害者は、保険会社が定める範囲内で、弁護士費用(相談料、着手金、報酬金など)の支払いを受けることができます。
弁護士費用特約のメリット
- 自己負担なしで弁護士に依頼できる:
多くの弁護士費用特約では、相談料や着手金、報酬金などの弁護士費用が保険金で支払われるため、自己負担なしで弁護士に依頼できます。(保険会社や契約内容によって異なります。) - 過失割合の交渉を安心して任せられる:
弁護士費用を気にすることなく、過失割合の交渉を弁護士に任せることができます。 - 賠償金の増額が期待できる:
弁護士が交渉することで、過失割合が有利になり、賠償金が増額される可能性があります。ただし、必ずしもご希望の過失割合や、ご希望の解決内容となるとは限りません。

5.2 弁護士費用特約の注意点 加入状況の確認と利用条件
弁護士費用特約を利用する際には、以下の点に注意しましょう。
- 加入状況の確認:
自分が加入している保険に弁護士費用特約が付帯しているかどうかを確認しましょう。家族の加入している保険も要確認です。 - 利用条件の確認:
弁護士費用特約を利用できる条件を確認しましょう。 - 保険会社の承認:
弁護士に依頼する前に、保険会社に弁護士費用特約を利用することを伝え、承認を得ましょう。 - 保険金の限度額:
弁護士費用特約には、保険金の限度額が定められています。限度額を超える費用は、自己負担となる場合があります。
5.3 弁護士費用特約がない場合の対処法
弁護士費用特約がない場合でも、弁護士に依頼することは可能です。
その場合、弁護士費用は自己負担となりますが、以下の方法で費用負担を軽減できる場合があります。
- 法テラスの利用:
法テラス(日本司法支援センター)は、経済的に余裕がない方を対象に、無料法律相談や弁護士費用の立て替えを行っています。 - 分割払い:
弁護士によっては、弁護士費用の分割払いに対応している場合があります。 - 着手金無料の弁護士:
着手金無料の弁護士に依頼することで、初期費用を抑えることができます。
6. 過失割合の立証を変える! トレンドと活用事例

6.1 ドライブレコーダー映像解析
ドライブレコーダー映像の解析が高度化しています。
映像内の車両や歩行者を認識し、速度、位置関係、進行方向などを算出する助けとなります。
これにより、人間の目では見落としがちな情報を捉え、より客観的で正確な過失割合の判断が可能になります。また、EDR(イベントデータレコーダー)というブラックボックスの解析をしてくれる調査会社もあります。
具体的な活用事例
- 車両の速度推定:
現場での距離を測定するとともに、映像内の車両の動きを分析し、衝突時の速度を推定します。 - 車両の位置関係の特定:
ドライブレコーダーの映像から、実際の車両位置を特定し、事故発生時の車両の位置関係を特定します。 - 衝突角度の算出:
映像内の車両の動きを分析し、衝突角度を算出します。
6.2 事故現場の再現動画
事故現場の画像や映像から実際に車両を運転して、再現した証拠を作成することがあります(裁判所に提出することもあります)。
これにより、事故現場の状況をより正確に把握し、過失割合の判断に役立てることができます。
具体的な活用事例
- 事故現場の見取り図作成:
事故現場の画像や映像から、道路の幅、交差点の形状、信号機の位置などを認識し、実際に現場に足を運び、見取り図を作成します。 - 車両の損傷状況の再現:
車両の損傷状況の画像から、損傷の程度や衝突の方向などを再現します。 - 事故発生時の視界の再現:
事故現場の画像や映像から、事故発生時の運転者の視界を再現します。ドライブレコーダーの映像と、実際に運転者が見ているものは、若干違います(目線とドライブレコーダーの設置位置が異なるため)。
6.3 過去の裁判例分析
過去の交通事故の裁判例の膨大なデータを分析し、類似の事故の過失割合を抽出することができます。 これにより、より客観的な過失割合の判断が可能になります。
具体的な活用事例
- 類似事故の検索:
事故の類型、道路状況、当事者の属性などの条件に基づいて、類似の事故の裁判例を検索します。 - 過失割合の傾向分析:
類似の事故の裁判例における過失割合の傾向を分析します。
6.4 今後の展望
AI技術の進歩もあり、過失割合の立証において、以下のような傾向はますます大きくなるでしょう。
- 客観性の向上:
人間の主観や偏見を排除し、より客観的な過失割合の判断を可能にすること。 - 正確性の向上:
人間の目では見落としがちな細かな情報を分析し、より正確な過失割合の判断を可能にすること。 - 迅速性の向上:
大量のデータを高速で処理し過失割合の判断を迅速に行うこと。
AI技術は、今後さらに発展し、交通事故の過失割合の立証において、ますます重要な役割を果たすようになるでしょう。
将来的には、AIが自動的に過失割合を判断するシステムが開発される可能性もあります。
7. 過失割合の修正に成功した事例集 ~弁護士の力で勝ち取った逆転劇~

(いずれも監修者の事例)
7.1 事例1:自転車と車の事故 過失割合10%→0%に
事故状況:
自転車と車の事故。過失割合が争点。
当初の過失割合:
相手保険会社は、被害者にも10%の過失が発生すると主張。
弁護士の対応:
受任後、刑事記録を取り付け、現場の状況を調査し、事故態様・当事者の認識などを分析し、過失0が相当との見解を作成。
結果:
交渉により相手方保険会社に過失ゼロを認めさせ、慰謝料も裁判基準満額にて示談した。
7.2 事例2:信号の色が争点(ドライブレコーダーなし)過失割合100%→5%に
事故状況:
交差点における出会い頭事故で、双方とも青進入を主張(ドライブレコーダー等の客観証拠はなし)。
当初の過失割合:
相手保険会社は、当方の赤進入で全面的な過失と主張(100%)。
弁護士の対応:
交渉での解決は難しいので、受任後、訴訟を提起し、審理を重ねて丁寧な証人尋問を行った。
結果:
裁判所も当方車両の青進入を認め、当方青進入の内容で和解した(和解限り譲歩して、5:95)。
7.3 事例3:事故態様に争いはなかったが、過失割合の評価が問題となった事例
事故状況:
ドライブレコーダーの存在により、事故態様自体は争いなし。
当初の過失割合:
相手保険会社は、被害者20%:加害者80%の過失割合を提示した。
弁護士の対応:
判例タイムズの基準・裁判例を分析し、示談交渉。
結果:
結果、当方の過失ゼロを認めさせ、修理費と休車損害を満額回収することができた。
7.4 事例4:防犯カメラの早急な保存が功を奏した事例
事故状況:
当て逃げ。
当初の過失割合:
相手方を特定するも、交渉に応じず。
弁護士の対応:
防犯カメラの映像が残っていることが判明し、早急に証拠保全の上、弁護士会照会にて取り付けを行った。また、証拠収集を経て提訴。
結果:
修理費全額を支払う内容にて和解が成立。
7.5 事例5:事故態様の主張が全く異なっていた事例
事故状況:
相手は当方のセンターオーバー、当方は相手のセンターオーバーを主張。
当初の過失割合:
相手保険会社は、当方のセンターオーバーとして、90%:10%を提示
弁護士の対応:
鑑定事務所のアジャスター(車両損害調査の専門家)に、車両の損傷状況からは相手方がセンターオーバーしたものと考えるのが相当との意見書を作成してもらった。
結果:
訴訟にて当方の主張がいれられ、当方主張の修理費を全額支払う内容にて和解終結。
8. 交通事故の過失割合 よくある質問(Q&A)

Q1. 過失割合はどのように決まるのですか?
A. 過失割合は、過去の裁判例を基にした基準や、事故の具体的な状況(道路状況、運転状況、車両の種類、当事者の属性など)を総合的に考慮して判断されます。交渉では合意による形成を目指します。訴訟では最終的には裁判所が判断します。
Q2. 保険会社が提示した過失割合に納得できない場合はどうすればよいですか?
A. 弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、あなたの代わりに保険会社と交渉し、より有利な過失割合を獲得するために尽力します。また、法的なアドバイスやサポートを受けることができます。また、判例タイムズ38号や、赤い本(殆ど判例タイムズと同じ表が載っています)を購入して、どの事故類型に該当するか、基本過失割合はどれくらいか、修正要素は何か、自分でしらべてみても良いでしょう。
Q3. 弁護士費用特約がない場合でも、弁護士に依頼できますか?
A. はい、可能です。弁護士費用特約がない場合は、自己負担で弁護士に依頼することになります。しかし、弁護士に依頼することで賠償金が増額される可能性が高いため、結果的に費用を上回るメリットが得られることもあります。また、法テラスの利用や、分割払いに対応している弁護士、着手金無料の弁護士などを検討することもできます。
Q4. 弁護士に相談するタイミングはいつが良いですか?
A. 早ければ早いほど良いです。事故直後から弁護士に相談することで、証拠収集や保険会社との交渉など、適切な対応を早期に行うことができます。これにより、後々の交渉を有利に進めることができ、精神的な負担も軽減されます。
Q5. 示談交渉の期間はどれくらいですか?
A. 示談交渉の期間は、事故の状況や争点、保険会社の対応などによって異なります。数ヶ月で解決する場合もあれば、1年以上かかる場合もあります。弁護士に依頼することで、交渉がスムーズに進み、早期解決につながる可能性があります。
Q6. 裁判になった場合、費用や期間はどれくらいかかりますか?
A. 裁判になった場合の費用や期間は、争点や証拠の量などによって大きく異なります。一般的には、弁護士費用(着手金、報酬金、実費など)がかかり、期間は1年以上に及ぶこともあります。弁護士に依頼する際に、費用や期間の見通しについて詳しく説明を受けることをおすすめします。
9. まとめ 弁護士に相談して、適正な過失割合と納得のいく解決を!

交通事故の過失割合は、賠償金額を大きく左右する非常に重要な要素です。
しかし、保険会社が提示する過失割合は、必ずしも被害者にとって有利なものとは限りません。
もし、保険会社が提示した過失割合に納得できない場合は、泣き寝入りせず、弁護士に相談することを強くおすすめします。
弁護士は、あなたの強い味方となり、
- 専門知識と交渉力で、保険会社と対等に交渉
- 証拠収集力で、あなたの主張を裏付け
- 精神的なサポートで、あなたを支え
適正な過失割合と、納得のいく解決を実現するために、全力を尽くします。

交通事故は、人生を大きく変えてしまう出来事です。
しかし、適切な対応をすれば、必ず乗り越えられます。
一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。
きっと、あなたの力になれるはずです。














