
交通事故は、誰もが巻き込まれる可能性のある出来事であり、特に物損事故は、示談交渉が決裂した場合、その後の訴訟対応について不安を感じる方も少なくありません。今回の記事では、交通事故の物損事故において、訴訟を起こした場合の流れについて、原告側の視点から詳しく解説していきます。訴状の送達から和解、そして判決に至るまでの各プロセス、注意点、解決方法を分かりやすく説明します。
目次
- 訴訟提起から訴状送達へ
- 期日指定と第1回期日
- 第2回期日以降の訴訟プロセス
- 期日後と書面のやり取り
- 依頼者の注意点
- 和解による解決
- 物損における具体的な解決方法
- 証人尋問と判決
- 解決までの期間
- 専門家への相談
1.訴訟提起から訴状送達へ
交通事故で示談交渉がまとまらず、訴訟を提起した場合、まず被告(相手方)に訴状が送達されます。被告とは、単に訴えを起こされた側のことを指します。示談段階で弁護士が代理人に就任していた場合でも、被告が裁判所に委任状を提出していない限り、訴状は被告本人に直接届きます。

2.期日指定と第1回期日
訴訟提起から通常1~2か月程度の間に、裁判所によって第1回期日が指定されます。裁判所は、原告側の代理人の都合は考慮しますが、被告の都合は聞きません。これは、被告に準備期間を与えるためです。通常、第1回期日では被告代理人は出廷せず、答弁書を提出します(「追って主張する」などと記載)。
第1回期日は当方が訴状を陳述し、せいぜい数分で終了し、第2回期日が指定されます(期日は、第2回、第3回・・と1か月から1か月半に1回の間隔で開かれます)。
依頼者様の出頭の必要はありません(出頭を要する場合につきましては、後述致します)。もちろん、時間の都合がつくようであれば、裁判所に来て頂いてもOKです。
最近では、簡易裁判所も含めて、ウェブ会議で手続きが進行することが多いです。

3.第2回期日以降の訴訟プロセス
第2回期日以降、被告の本格的な主張立証がなされます。こちらの主張に反論を加えてきます。被告の反論書面は、期日の1週間程度前に、当方の弁護士に届きます。
なお、当方の主張に対して、被告が準備書面に認否する方法は「認める」「不知」「否認」の3つがあります。そして、被告の反論に対して、当方も、さらに反論を加えていきます。
物損の場合、主な争点は過失割合(原告:被告=○:○)と損害額(修理費用等)になります。
過失割合と損害額に絞って主張立証をしますので、争点に関係がない部分は、準備書面に書かないことがあります(期日におきましては、周辺事情として口頭で裁判官にお伝えすることもあります。)。

4.期日後と書面のやり取り
第2回、第3回…と、双方の主張と立証がある程度出尽くすまで、書面のやり取りが続きます。期日後には、裁判所でのやり取りや今後の見通しについて、期日報告書などが依頼している弁護士から送付されます。
裁判所に提出する書面と証拠は、基本的に期日の1週間前に裁判所と相手方に提出する必要があります。提出する準備書面と証拠は、依頼者が事前に確認しておきます。
5.依頼者の注意点
被告が提出する書面には、原告側の主張と異なる内容や、気分を害するような記載があることもあります。しかし、これらはあくまで争点に関するものなので、感情的になったり、動揺する必要はありません。一つ一つ丁寧に反論していくことが重要です。
6.和解による解決
ある程度原告及び被告の主張が揃った段階で(交通事故の場合、第3回ないし第4回期日の比較的早い段階のこともあります)で、裁判所は原告と被告に、「本件の過失割合は○:○、損害額は○円・・と考えているが、和解を検討して頂けないか」などといって和解を勧めてきます。
双方が検討の上、和解を応諾できるとなれば、和解調書を作成して訴訟は終了となります(この段階で終わってしまうこともあります)。
しかしながら、和解は原告と被告の双方の応諾が必要となりますので、被告が強硬に自己の主張を続けている場合や、こちらが過失割合・損害額について納得できない場合等は、証人尋問及び判決の手続きに進むことになります。
そこで、早期に解決できなくなって解決までに長期間かかるリスク・過失割合について判決まで行ってしまうとより不利な認定をされるリスク・平日の昼間に証人尋問のために裁判所に出頭しなければならなくなるリスク等を踏まえ、ある程度の落としどころを探り、和解によって早期に穏便な解決ができるかを検討することになります。

7.物損における具体的な解決方法
次に、具体的にどのような解決方法がとられるかについて説明します。
過失割合の決定
交通事故では、双方に過失があることが少なくありません。損害賠償額を決定する際に重要になるのが過失割合です。この過失割合は、双方が負担すべき責任の割合のことをいいます。
そして、交通事故では過去の膨大な判例が蓄積されているとともに、同種の事案を公平に解決するため、事故態様及びそれに基づく過失割合がある程度定型化されております。
そこで、具体的な過失割合の判断にあたっては、「別冊判例タイムズ38号民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」が参照され、裁判においても指標とされております。
なお、実際の裁判においては、裁判官は別冊判例タイムズ38号を参照しますが、判決文には「基本的過失割合」「修正要素」という枠組の記載はせず、各事情を総合考慮した結果過失割合を判断するという表現になっており、ある事情が修正要素とされたか否か、及びその程度は、判例の過失割合と基本的過失割合の差の有無、程度によって推し測ることになります。

損害額の確定
次に、具体的な請求額につきましては、損害額を確定させた上で、民法722条2項により、損害の公平な分担の見地から、上記の自己の過失割合分だけ損害賠償額を差し引いたものを、それぞれ相手方に請求できることとなります。
(損害賠償の方法及び過失相殺)
民法第722条2項
被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
例:
- ア 原告の物的損害及び請求額
- (ア)修理費等 ●円
- (イ)過失相殺(▲%) -(●×▲%)円
- (ウ)原告が請求できる金額 ■円((ア)から(イ)を引いた金額)
- イ 被告の物的損害及び請求額
- (ア)修理費等 ●円
- (イ)過失相殺(▲%) -(●×▲%)円
- (ウ)被告が請求できる金額 ■円((ア)から(イ)を引いた金額)
支払方法
双方に過失があるとされた場合、上記のように、原告も被告もそれぞれ、自己の損害額から自己の過失割合分を引いたものを相手方に請求できることになります。
原告は被告から支払いを受け、被告は原告から支払を受けます(こちらに支払いが生じ、その金額が大きい場合は、対物保険があれば、対物保険を使って払うことも可能です。)。
このような解決方法も可能ですが、このような迂遠な金銭のやり取りを避けるため、双方の賠償額を相殺の上、差し引き計算する方法を用いることもあります。

8.証人尋問と判決
話し合いによって和解による解決が難しいとなりますと、証人尋問(当事者尋問)、引き続いて判決の手続きに進むことになります。
当事者の方に裁判所に行っていただくのは、当事者が直接、裁判所に対し話をする尋問の期日くらいですので、1回だけがほとんどです(逆に言うと、当事者に対する尋問が実施されないケースでは、当事者が一度も裁判所に行かないケースもあります)。
尋問をすることになった場合、期日調整・リハーサル等の準備が必要になります。

9.解決までの期間
通常、物損の交通事故訴訟におきましては、簡易裁判所の訴訟手続による和解による解決を前提にした場合、ケースバイケースとなりますが、期日の回数は5~6回程度、約1年以内で終わることが多いと思われます。
しかしながら、争点が多い場合、証人尋問・判決まで至る場合などは、解決までにより長期間かかり、それよりも長い期間をる必要がある事件も少なくありません。
10.専門家への相談
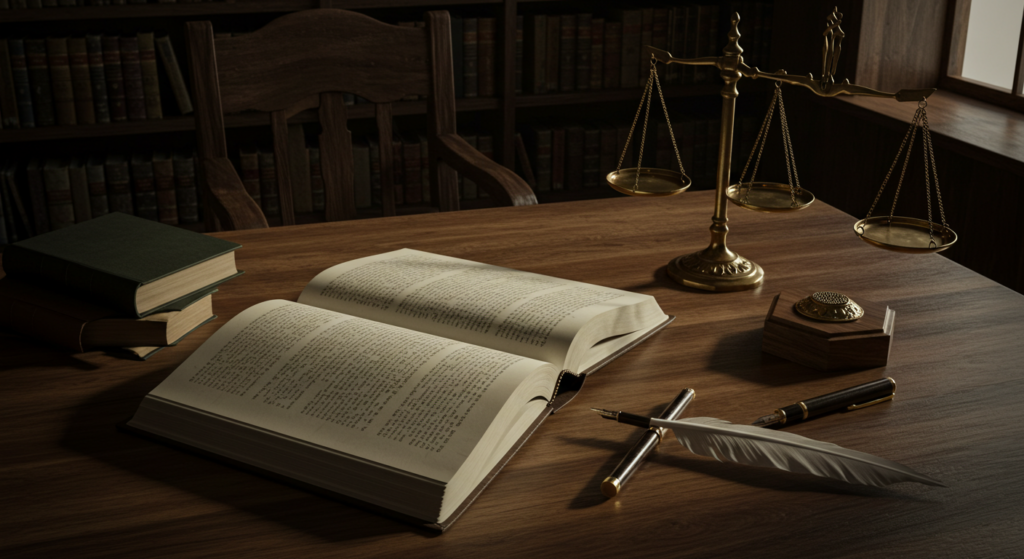
交通事故の物損訴訟は、専門的な知識と経験が必要となる場合があります。疑問点や不安がある場合は、弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。














