
交通事故は、どんなに注意していても、誰もが加害者になってしまう可能性があります。事故を起こしてしまった直後は、気が動転し、パニックになり、どうすれば良いのか分からなくなるかもしれません。
「被害者の方に怪我をさせてしまった…どうしよう…」
「逮捕されてしまうのだろうか…?」
「保険会社に任せておけば大丈夫…?」
「今後の手続きはどうなる…?」
「弁護士に相談した方がいいの…?費用は…?」
この記事は、交通事故の加害者となってしまった方に向けて、事故直後からその後の対応、刑事手続き、民事手続き、そして弁護士に依頼するメリットと弁護士の選び方まで、網羅的に解説するものです。
この記事を読むことで、あなたは、交通事故の加害者として取るべき行動を理解し、今後の見通しを立て、不安を解消するための具体的な 一歩を踏み出すことができるようになるでしょう。ぜひ最後までお読みいただき、あなたの置かれている状況を打開するための一助としてください。
目次
- 交通事故の加害者が直面する法的責任|刑事・民事・行政上の責任
- 交通事故発生直後、加害者が取るべき行動|初動対応の重要性
- 交通事故加害者のための刑事手続きの流れ|逮捕・勾留、起訴・不起訴、裁判
- 交通事故加害者のための民事手続きの流れ|示談交渉、調停、訴訟
- 交通事故加害者が弁護士に依頼するメリット|弁護士は何をしてくれるのか?
- 交通事故加害者のための弁護士の選び方|弁護士選びのポイント
- 交通事故加害者のための弁護士費用|弁護士費用の内訳
- 交通事故加害者のためのQ&A|よくある質問
- まとめ|交通事故の加害者になってしまったら、すぐに弁護士に相談を
1. 交通事故の加害者が直面する法的責任|刑事・民事・行政上の責任

1-1. 交通事故における3つの法的責任
1-1-1. 刑事責任|逮捕・起訴・刑罰の可能性
交通事故を起こし、人に怪我をさせたり、死亡させたりした場合、刑事責任を問われる可能性があります。
交通事故における刑事責任は、主に以下の罪によって問われます。
- 過失運転致死傷罪(「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」。いわゆる自動車運転処罰法5条)
- 危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法2条、3条)
- 道路交通法違反(信号無視、速度超過など)
これらの罪に問われた場合、逮捕・勾留され、捜査機関(警察・検察)による取り調べを受け、最終的には検察官によって起訴されるか不起訴されるかが決定されます。起訴された場合は、刑事裁判が開かれ、有罪判決が下されれば、懲役刑、禁錮刑、罰金刑などの刑罰が科せられます(略式起訴となることもあります)。
1-1-2. 民事責任|損害賠償責任
交通事故の加害者は、被害者に対して、事故によって生じた損害を賠償する民事責任を負います。民事責任とは、個人間の損害賠償に関する責任のことです。
交通事故における損害賠償の費目としては、以下のようなものがあります。
- 治療費
- 休業損害
- 慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)
- 逸失利益(後遺障害が残った場合や死亡した場合)
- 物的損害(車両の修理費用など)
これらの損害賠償は、通常、加害者が加入している自動車保険(任意保険)を通じて、被害者に支払われます。しかし、保険でカバーしきれない損害については、加害者自身が負担する必要があります。
任意保険に加入していない、または任意保険の契約期間がきれていたことが判明したという場合、任意保険は使えません。したがいまして、自賠責保険以上の損害賠償分は、自分で支払うことになります(なお、自賠責保険は物損をカバーしません)。
自賠責保険もない完全な無保険車であった場合は、自賠責保険分も自分で支払わなければなりません。
1-1-3. 行政上の責任|免許停止・免許取消
交通事故の加害者は、刑事責任や民事責任とは別に、行政上の責任を負うことがあります。行政上の責任とは、公安委員会(都道府県警察)によって、運転免許の停止や取消などの処分を受けることです。
交通事故の態様や結果、違反点数などに応じて、免許停止(免停)や免許取消の処分が下されます。
1-2. 交通事故の加害者が問われる罪名|過失運転致死傷罪、危険運転致死傷罪など
交通事故の加害者が問われる可能性のある主な罪名は、以下の通りです。
- 過失運転致死傷罪(自動車運転処罰法5条):「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」
- 危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法2条、3条):「第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為 二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為 三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為 四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為 五 車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為 六 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為 七 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為 八 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」「第三条 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。2 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。」
- 道路交通法違反: 信号無視、速度超過、一時不停止、酒気帯び運転、無免許運転など。
1-3. 交通事故の加害者が負う損害賠償責任|慰謝料、治療費、休業損害など
交通事故の加害者が負う損害賠償責任は、多岐にわたります。主な損害項目は以下の通りです。
- 治療関係費: 治療費、入院費、通院費、付添看護費、将来の介護費など
- 通院交通費
- 休業損害: 事故による怪我で仕事を休んだことによる収入の減少分
- 慰謝料:
- 入通院慰謝料: 入院や通院を余儀なくされたことによる精神的苦痛に対する慰謝料
- 後遺障害慰謝料: 後遺障害が残ってしまったことによる精神的苦痛に対する慰謝料
- 死亡慰謝料: 被害者が死亡した場合の、被害者本人および遺族に対する慰謝料
- 逸失利益:
- 後遺障害逸失利益: 後遺障害によって労働能力が低下し、将来得られるはずだった収入が減少することに対する補償
- 死亡逸失利益: 被害者が死亡した場合に、将来得られるはずだった収入の減少に対する補償
- 物的損害: 車両の修理費用、代車費用、レッカー費用、評価損など
1-4. 交通事故加害者の過失割合|過失割合が与える影響
交通事故においては、加害者と被害者の双方に過失がある場合があります。過失割合とは、事故発生に対する責任の度合いを割合で示したものです。
過失割合は、損害賠償額の算定に大きく影響します。例えば、被害者の過失割合が20%の場合、被害者の損害額は、過失相殺前の損害から20%減額されます。
2. 交通事故発生直後、加害者が取るべき行動|初動対応の重要性

2-1. 負傷者の救護義務|最優先に行うべきこと
交通事故を起こした場合、まず第一に行わなければならないのは、負傷者の救護です。これは、道路交通法72条1項前段で定められている義務であり、怠ると「救護義務違反」として罰せられる可能性があります。
負傷者がいる場合は、
- 安全な場所に移動させる
- 119番通報して救急車を呼ぶ
- 可能であれば、応急処置を行う
など、できる限りの救護措置を講じましょう。
2-2. 危険防止措置義務|二次的な事故を防ぐ
負傷者の救護と並行して、二次的な事故を防ぐための措置を講じる必要があります。これも、道路交通法72条1項前段で定められている義務です。
具体的には、
- ハザードランプを点灯させる
- 発炎筒や停止表示板を設置する
- 後続車に事故発生を知らせる
など、周囲の車両に注意を促す措置を取りましょう。
2-3. 警察への報告義務|怠ると罰則も
交通事故を起こした場合は、警察に報告する義務があります。これは、道路交通法72条1項後段で定められており、怠ると「報告義務違反」として罰せられる可能性があります。
警察には、
- 事故発生の日時と場所
- 死傷者の数と負傷の程度
- 損壊した物と損壊の程度
- 事故車両の積載物
- 事故について講じた措置
を報告する必要があります。
2-4. 保険会社への連絡|事故状況の報告
加入している自動車保険会社(任意保険)に連絡し、事故の状況を報告しましょう。保険会社は、今後の示談交渉などをサポートしてくれます。ご自分が加入されている保険会社の代理店を通じてでも構いません。
2-5. 証拠の保全|事故現場の記録、目撃者の確保
可能であれば、事故現場の状況を記録しておきましょう。
- スマートフォンなどで、事故車両の損傷状況、道路状況、信号や標識などを撮影する
- 目撃者がいる場合は、連絡先を聞いておく
- ドライブレコーダーの記録が消えないようにしておく
- 防犯カメラの有無を確認しておく(保存期間があります)
これらの証拠は、後々の示談交渉や裁判において、重要な証拠となる可能性があります。
2-6. やってはいけないこと|現場からの逃走、証拠隠滅、虚偽申告
絶対にやってはいけないことは、以下の3点です。
- 現場からの逃走(ひき逃げ): 救護義務違反、報告義務違反となり、重い罪に問われます。
- 虚偽申告: 警察や保険会社に対し、嘘の報告をすることは、絶対にやめましょう。
3. 交通事故加害者のための刑事手続きの流れ|逮捕・勾留、起訴・不起訴、裁判
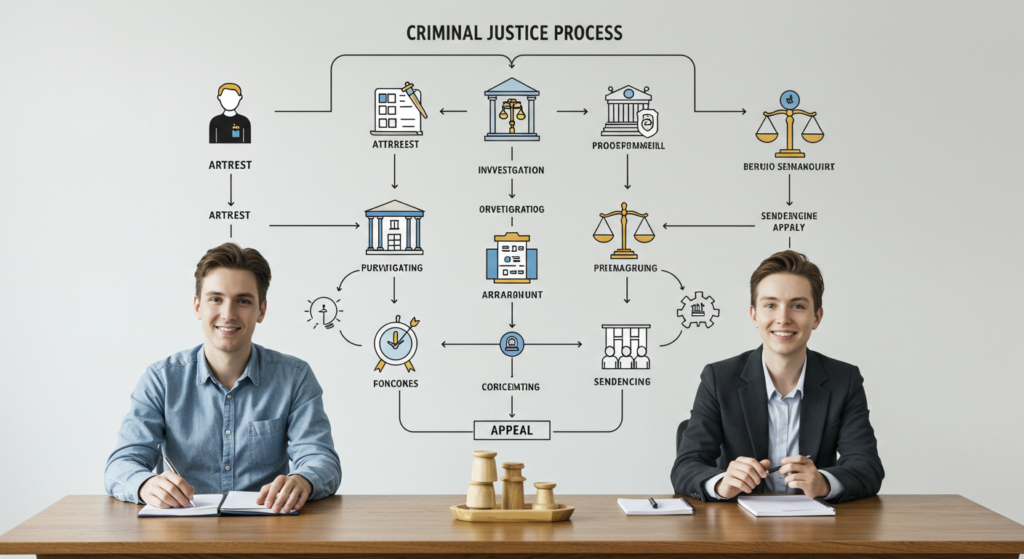
3-1. 逮捕・勾留されるケースとは?
交通事故で人を死傷させた場合、必ず逮捕・勾留されるわけではありません。逮捕・勾留されるかどうかは、
- 事故の重大性(死傷者の数、怪我の程度)
- 加害者の過失の程度(飲酒運転、ひき逃げなど)
- 証拠隠滅や逃亡の恐れ
などを総合的に考慮して判断されます。
一般的に、死亡事故や重傷事故、ひき逃げ、飲酒運転などの悪質なケースでは、逮捕・勾留される可能性が高くなります。
3-2. 取り調べへの対応|供述の重要性
逮捕・勾留されると、警察や検察による取り調べが行われます。取り調べでの供述は、その後の起訴・不起訴の判断や、裁判における証拠として非常に重要な意味を持ちます。
- 黙秘権: 取り調べに対して、黙秘する権利があります。
- 供述調書: 取り調べでの供述は、供述調書として記録されます。供述調書は、後で覆すことが非常に困難であるため、慎重に対応する必要があります。
- 弁護士への相談: 取り調べを受ける前に、弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。自動車保険によっては、私選の刑事の弁護士費用を保険会社が負担する特約が付いていることがあります。
3-3. 起訴・不起訴の判断基準
検察官は、捜査の結果を踏まえ、被疑者を起訴するか不起訴にするかを決定します。
- 起訴: 検察官が、被疑者を刑事裁判にかけること。
- 不起訴: 検察官が、被疑者を刑事裁判にかけないこと。不起訴には、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予などの種類があります。
起訴・不起訴の判断は、
- 事故の重大性
- 加害者の過失の程度
- 被害者の処罰感情
- 任意保険契約の有無
- 示談の成否ないしその見込み
- 加害者の反省の有無
などを総合的に考慮して行われます。
3-4. 刑事裁判の流れと弁護士の役割
起訴された場合、略式請求とならない限り、刑事裁判が開かれます。刑事裁判では、
- 冒頭手続き(人定質問、起訴状朗読、黙秘権告知など)
- 証拠調べ手続き(検察官・弁護人による証拠の提出、証人尋問など)
- 弁論手続き(検察官の論告求刑、弁護人の最終弁論)
- 判決
という流れで審理が進められます。
弁護士は、被告人の弁護人として、
- 証拠の収集・分析
- 法廷での弁論活動
- 被告人に有利な情状の主張
などを行い、被告人のために最善の弁護活動を行います。
3-5. 交通事故における刑罰の種類と量刑
交通事故における刑罰には、主に以下のものがあります。
- 懲役刑: 刑務所に収容され、刑務作業を行う刑罰。
- 禁錮刑: 刑務所に収容されるが、刑務作業は行わない刑罰。
- 罰金刑: 金銭を納付する刑罰。
量刑(刑の重さ)は、事故の状況、被害の程度、加害者の過失の程度、前科の有無などを総合的に考慮して決定されます。
4. 交通事故加害者のための民事手続きの流れ|示談交渉、調停、訴訟

4-1. 示談交渉とは?|メリットとデメリット
示談交渉とは、裁判外で、当事者間の話し合いによって損害賠償問題を解決する方法です。加害者に任意保険があり、加害者に保険使用の意思がある場合(対物保険・対人の保険への請求がある場合)、まず、保険会社の担当者が賠償の交渉にあたります。
メリット
- 早期解決が期待できる
- 任意保険がある場合、加害者の負担としては、等級ダウンによる保険料の増額にとどまる
- 当事者間の合意に基づく解決ができる
デメリット
- 必ずしも適切な賠償額で合意できるとは限らない
- 当事者間の感情的な対立が激しい場合などは、交渉が難航する可能性がある(この場合、任意保険会社は、契約者=加害者保護の目的の下、加害者に弁護士を選任させることがあります。委任状は加害者から取得しますが、実質は保険会社の代理人ともいえるでしょう)。
4-2. 保険会社との示談交渉の進め方
上記のとおり、通常、交通事故の損害賠償問題は、加害者が加入している自動車保険会社(任意保険)が、加害者に代わり、被害者と示談交渉を行います(任意保険がない場合は、自分で賠償交渉するか、自腹で弁護士を雇う必要があります)。
保険会社は、過去の裁判例や独自の基準に基づいて、損害賠償額を算定し、被害者に提示します。被害者が提示額に納得すれば示談成立となりますが、納得できない場合は、交渉を継続することになります。
4-3. 示談交渉で揉めるケースと対処法
示談交渉で揉めるケースとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 過失割合: 事故の責任がどちらにあるのか、その割合について争いになるケース(ただ、加害者が自分の物損については車両保険、人損については人身傷害保険で対応し、相手方の損害については対物・対人で対応する場合、もはやあまり過失割合に興味がない場合もあります)
- 損害額: 治療費、休業損害、慰謝料などの損害額について争いになるケース
- 後遺障害: 後遺障害の有無や程度について争いになるケース
示談交渉で揉めた場合は、加害者の任意保険会社は、弁護士に加害者の代理人として介入してもらうことを検討するようになります(保険会社の顧問の弁護士などが選ばれることが多いです。)。
4-4. 示談交渉が決裂した場合|調停、訴訟
示談交渉が決裂した場合は、主に、加害者側からのアクションとしては、以下の方法で解決を図ることになります。
- 調停: 裁判所に申立てて、当事者間の話し合いを仲介し、和解による解決を目指す手続きです。加害者側から申し立てる場合を、「賠償調停」などと言ったりしました。
- 訴訟: 裁判所に訴えを提起し、裁判官に判断を求める手続きです。加害者側からは、「債務不存在確認請求訴訟」という訴訟を提起することになります。賠償債務が全く存在しない、一定額以上は存在しないと主張して、賠償債務を裁判所に確認してもらうという、やや特殊な訴訟類型です。仮に加害者の過失が100%であっても、加害者からこのような訴訟を提起することができます。
5. 交通事故加害者が弁護士に依頼するメリット|弁護士は何をしてくれるのか?

5-1. 刑事弁護|逮捕・勾留からの早期釈放、不起訴処分の獲得、刑の減軽
弁護士は、逮捕・勾留された場合、早期釈放に向けて活動します。また、検察官に対して、不起訴処分を求める意見書を提出したり、裁判で刑の減軽を求める弁論活動を行ったりします(自動車保険によっては、私選で弁護士を雇う場合の弁護士費用が補償される弁護士費用特約があります。いわゆる刑事の弁護士費用特約です。)。
5-2. 示談交渉の代行|適正な賠償額での示談成立
弁護士は、加害者の代理人として、被害者や保険会社との示談交渉を全て代行します。弁護士は、過去の裁判例や法的知識に基づいて、適正な賠償額を算定し、交渉を行うため、より有利な条件で示談を成立させることができます。また、裁判所に訴訟や調停の申立てをすることによって、被害者側から加害者への直接の連絡を事実上抑えることができるというメリットもあります。
5-3. 被害者感情への配慮|円満な解決を目指す
弁護士は、被害者の心情に配慮しながら、示談交渉を進めます。被害者への謝罪や、示談条件の調整など、円満な解決に向けて尽力します。
5-4. 精神的なサポート|不安の解消
交通事故の加害者は、精神的に大きな不安を抱えています。弁護士は、法的なサポートだけでなく、精神的なサポートも行い、加害者の不安を解消します。
5-5. 煩雑な手続きからの解放|時間と労力の節約
交通事故に関する手続きは、非常に煩雑です。弁護士に依頼することで、これらの手続きを全て任せることができ、時間と労力を節約することができます。
6. 交通事故加害者のための弁護士の選び方|弁護士選びのポイント

6-1. 交通事故問題の解決実績が豊富か
交通事故問題は、専門的な知識や経験が必要となる分野です。交通事故の解決実績が豊富な弁護士を選ぶことが重要です。
6-2. 加害者側の弁護経験があるか
交通事故の加害者側の弁護経験がある弁護士を選ぶことも重要です(ただ、任意保険が付帯されている場合、通常は任意保険会社が案内してくれるでしょう。ただ、その場合でも自分で選んだ弁護士にお願いしたい旨を任意保険会社にお伝えすれば、自分で選ぶことができるでしょう。)。加害者側の事情や立場を理解し、適切な弁護活動を行ってくれます。
6-3. 親身になって相談に乗ってくれるか
弁護士との相性も重要です。親身になって相談に乗ってくれ、信頼できる弁護士を選びましょう。
6-4. 費用体系が明確か
弁護士費用は、賠償側の弁護士の場合、任意保険会社の内部で報酬規程が定められています。任意保険会社から弁護士に直接支払われますので、心配はいらないでしょう。仮に弁護士費用特約がなくとも、弁護士費用については対物・対人の付帯費用などとして支払われますので、弁護士費用を加害者が負担することはありません。
任意保険がない場合は、費用体系が明確で、事前に費用の説明をしてくれる弁護士を選びましょう。
6-5. 無料相談を活用する
多くの弁護士事務所では、無料相談を実施しています。無料相談を活用して、複数の弁護士に相談し、比較検討することをおすすめします。
7. 交通事故加害者のための弁護士費用|弁護士費用の相場と内訳

7-1. 弁護士費用の種類|相談料、着手金、報酬金、実費など
弁護士費用は、主に以下の種類があります。
- 相談料: 弁護士に相談する際にかかる費用です。無料相談を実施している弁護士事務所も多くあります。
- 着手金: 弁護士に事件を依頼する際に支払う費用です。事件の結果に関わらず、原則として返金されません。
- 報酬金: 事件が成功した場合に、弁護士に支払う費用です。成功の程度に応じて、金額が変動します。
- 実費: 交通費、通信費、書類のコピー代、裁判所に納める費用など、事件処理のために実際にかかる費用です。
- 日当: 弁護士が遠方に出張した場合などに発生する費用です。
7-2. 弁護士費用の相場
賠償側としての加害者の弁護士費用は、任意保険会社の内部で報酬規程が定められています。弁護士費用特約の約款とは別です。一般的に、交通事故の加害者側の弁護費用は、数十万円から数百万円程度となることが多いです。任意保険会社から弁護士に直接支払われます。
7-3. 弁護士費用特約の利用
仮にもし、加害者側であるとしても、被害者にも過失の発生が見込めるのであれば、加入している自動車保険に弁護士費用特約が付帯している場合は、弁護士費用特約の弁護士費用として、保険会社に負担してもらうことができます。
弁護士費用特約は、「被害事故」などと約款に書かれているように、自分の損害を相手に請求するものであるからです(自分の過失が100%であることが明らかな場合は、弁護士費用特約は使えない、ということになろうと思います)。
8. 交通事故加害者のためのQ&A|よくある質問

8-1. 事故を起こしたら必ず逮捕されますか?
交通事故を起こしたからといって、必ず逮捕されるわけではありません。逮捕されるかどうかは、事故の状況や結果、加害者の過失の程度、逃亡・罪証隠滅の恐れなどによって判断されます。
8-2. 示談交渉はいつから始められますか?
示談交渉は、事故発生後、いつでも始めることができます。ただし、被害者の怪我の治療が終了し、症状固定の診断が出てから、損害額が確定するため、本格的な示談交渉は症状固定後に行われることが一般的です。ただし、加害者は、症状固定の時期を争ったり、裁判所に債務不存在確認訴訟を提起することもできます。
8-3. 被害者に謝罪したいのですが、どうすればいいですか?
被害者に謝罪したい場合は、弁護士か、自分の任意保険を通じて行うことをおすすめします。いきなり謝罪に行くのではなく、必ず任意保険か弁護士に事前に連絡してください。被害者の感情を逆なでする可能性もありますし、示談交渉に不利な発言をしてしまうリスクもあります。
8-4. 罰金と反則金の違いは何ですか?
- 罰金: 刑事罰の一種であり、裁判を経て科せられます。前科がつきます。
- 反則金: 比較的軽微な交通違反に対して科せられる行政処分です。前科はつきません。
8-5. 免許停止・免許取消になりますか?
交通事故の態様や結果、違反点数などに応じて、免許停止(免停)や免許取消の処分が下される可能性があります。
9. まとめ|交通事故の加害者になってしまったら、すぐに弁護士に相談を

交通事故の加害者になってしまった場合、直面する法的責任は重く、その後の手続きも複雑です。一人で悩まず、自分の任意保険会社の担当者とも連絡を取り、できるだけ早く弁護士に相談すると安心でしょう。
弁護士は、あなたの状況を詳しく分析し、最善の解決策を提案してくれます。刑事弁護、示談交渉、被害者対応、精神的サポートなど、様々な面であなたを支え、不安を解消するために尽力してくれます。
交通事故は、誰もが加害者になる可能性があります。万が一の事態に備え、弁護士費用特約の加入状況を確認しておくとともに、信頼できる弁護士を見つけておくことも重要です。














