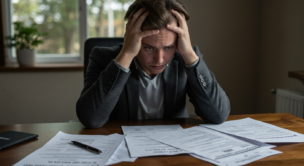
交通事故に遭い、全治1週間と診断された場合、「軽い怪我だから…」と慰謝料請求を諦めてしまったり、保険会社から提示された金額が適切なのかどうか分からず、不安に感じたりする方もいらっしゃるかもしれません。しかし、たとえ全治1週間であっても、交通事故によって精神的な苦痛を受けたことに変わりはなく、適切な慰謝料を請求する権利があります。
この記事では、交通事故の被害者の方が、全治1週間の怪我で適切な慰謝料を受け取るために知っておくべき知識を、分かりやすく解説します。慰謝料の計算方法、自賠責基準と弁護士基準の違い、そして、より多くの慰謝料を受け取るためのポイントについて、詳しく見ていきましょう。
目次
- 全治1週間の交通事故慰謝料|請求できる権利と金額の基礎知識
- 慰謝料の計算方法|自賠責基準と弁護士基準の違い
- 全治1週間の交通事故における慰謝料の支払い目安
- 全治1週間を超えて治療を継続する場合
- 慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット
- まとめ|全治1週間の交通事故でも、諦めずに適切な慰謝料請求を
1. 全治1週間の交通事故慰謝料|請求できる権利と金額の基礎知識

1-1. 全治1週間でも慰謝料は請求できる
交通事故で怪我を負った場合、その怪我が全治1週間と診断されたとしても、慰謝料を請求する権利があります。交通事故後、最初の医療機関で診断書が発行されますが、そこには、傷病名と、全治何週間、全治何か月といった記載があります。ただし、これは主に警察に提出するためのもので、相手方の刑事処分に影響するものであり、「全治1週間」という診断は、あくまで治療期間の目安や見込みに過ぎません。したがって、実際に生じた怪我の程度や精神的苦痛の大きさを正確に表すものではありません。
そして、「全治1週間」との診断書が発行されても、治療の必要性がある限り、実際の通院期間はこれに限定されません。
1-2. 慰謝料の金額はどう決まる?
慰謝料の金額は、いくつかの要素によって決まります。主な要素としては、以下のものが挙げられます。
- 怪我の程度: 怪我の程度が重いほど、慰謝料は高額になります。
- 通院期間・通院日数: 通院期間が長いほど、また、通院日数が多くなるほど、慰謝料は高額になる傾向があります。
- 入通院の有無: 入院した場合、通院のみの場合よりも慰謝料は高額になります。
- 後遺障害の有無: 後遺障害が残った場合、後遺障害慰謝料が別途請求できます。
- 事故の状況: 事故の状況が悪質である場合(ひき逃げ、飲酒運転など)、慰謝料が増額されることがあります。
1-3. 慰謝料請求の注意点
慰謝料請求の際には、以下の点に注意が必要です。
- 証拠の確保: 事故状況や怪我の程度を証明する証拠(車両の損傷写真、診断書、診療報酬明細書など)を確保しておくことが重要です。
- 保険会社との交渉: 保険会社から提示された慰謝料額が、必ずしも適切であるとは限りません。
- 時効: 慰謝料請求には時効があります。
2. 慰謝料の計算方法|自賠責基準と弁護士基準の違い

2-1. 自賠責基準による慰謝料計算
自賠責基準は、自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づいて定められた、最低限の補償基準です。
基本計算式: 1日あたり4,300円 × 通院日数
通院日数は、以下のいずれか少ない方が採用されます。
- 実際の通院日数 × 2
- 総治療期間の日数
例えば、総治療期間1週間で、そのうち3日通院した場合の慰謝料は、以下のようになります。
4,300円 × 7日 = 30,100円
2-2. 弁護士基準による慰謝料計算
弁護士基準(裁判基準とも呼ばれます)は、過去の裁判例などを参考に、弁護士が慰謝料を請求する際に用いる基準です。自賠責基準よりも高額な慰謝料が認められる可能性があります。
弁護士基準では、むち打ち症で他覚所見がない場合等(軽い打撲・軽い挫創(傷))は、別表Ⅱを使うことになりますが、1か月の通院慰謝料は19万円とされており、1か月以内で治療を終了した場合、それを基準に総治療期間に応じて日割り計算を行います。
計算式: 19万円 ÷ 30日 × 総治療期間(1か月以内)
総治療期間が1週間の場合の慰謝料は、以下のようになります。
19万円 ÷ 30日 × 7日 = 約44,333円
2-3. 【表で比較】自賠責基準と弁護士基準の慰謝料
| 基準 | 計算式 | 1週間(7日)通院の場合の慰謝料 |
|---|---|---|
| 自賠責基準 | 4,300円 × 通院日数(実通院日数×2 または 総治療期間のいずれか少ない方) | 30,100円 |
| 弁護士基準 | 19万円 ÷ 30日 ×総治療期間 | 約44,333円 |
3. 全治1週間の交通事故における慰謝料の支払い目安
3-1. 通院日数別の慰謝料支払い目安
| 通院日数 | 慰謝料(自賠責基準) |
|---|---|
| 1日 | 8,600円 |
| 2日 | 17,200円 |
| 3日 | 25,800円 |
| 4日 | 30,100円 |
3-2. 通院日数が少ない場合の注意点
上記の表は、あくまで自賠責基準による目安です。弁護士基準で請求する場合は、これよりも高額な慰謝料を受け取れる可能性があります。
しかし、通院日数が極端に少ない場合(例えば1日のみなど)は、弁護士基準で請求しても、結局、自賠責基準の方が高くなる、ということがあります(自賠責基準=8600円、弁護士基準=約6333円)。特に、過失が発生することが見込まれる場合、自賠責基準での示談が、結局お受け取りが一番高くなることがあります。
4. 全治1週間を超えて治療を継続する場合

4-1. 治療継続の必要性と医師の診断
全治1週間と診断された場合でも、症状が改善せず、治療が必要な場合は、医師の指示に従って治療を継続することができます。一番してはいけないのは、治療の必要性があるにもかかわらず、当初の「全治一週間」の診断があるからといって、治療をやめてしまうことです。
ただし、保険会社は、警察提出用の診断書に記載された「全治1週間」という期間を根拠に、治療費の支払いを打ち切ろうとすることがあります(また、訴訟においても、これを根拠に、相当な治療期間は1週間である、と主張してくることがあります)。
4-2. 診断書記載の重要性
治療を継続する場合は、医師にその旨を伝え、診断書に「治療継続が必要である」という内容を記載してもらうことが重要です。
医師の診断書があれば、保険会社に対して、治療継続の必要性を主張することができます。
5. 慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

5-1. 弁護士基準での請求による増額
弁護士に依頼することで、自賠責基準ではなく、弁護士基準で慰謝料を請求することができます。治療期間や実通院日数にもよりますが、一般的に弁護士基準は自賠責基準よりも高額となるため、慰謝料が増額される可能性が高まります。
5-2. 保険会社との交渉を代行
弁護士は、被害者の代理人として、保険会社との交渉を全て代行します。被害者自身が保険会社と交渉する必要がなくなるため、精神的な負担が軽減されます。交渉の窓口を弁護士に任せることができるのは大きいでしょう。
5-3. 精神的・時間的負担の軽減
弁護士に依頼することで、保険会社との交渉だけでなく、書類の作成や手続きなども任せることができます。これにより、被害者は治療に専念でき、精神的・時間的な負担が軽減されます。
6. まとめ|全治1週間の交通事故でも、諦めずに適切な慰謝料請求を

全治1週間の交通事故であっても、治療の必要性がある限り治療を継続し、また、慰謝料を請求する権利はあります。自賠責基準だけでなく、弁護士基準での請求を検討することで、より多くの慰謝料を受け取れる可能性があります。
保険会社との交渉や手続きに不安を感じる場合は、弁護士に相談することを強くおすすめします。弁護士は、あなたの強い味方となり、適切な治療期間のもと、適切な慰謝料の獲得に向けて、全力でサポートしてくれます。














