
交通事故に遭われて、心身ともに大変な状況だと思います。お見舞い申し上げます。
「交通事故 弁護士 示談交渉 流れ」で検索されたということは、保険会社との示談交渉に不安を感じていたり、少しでも有利に進めたいと考えていらっしゃるのではないでしょうか。交通事故の示談交渉では、弁護士が介入することで賠償金が増額できることがあります。さらに、「弁護士費用特約」を使えば、実質無料で弁護士に依頼できる場合が多いのです。
このページでは、示談交渉の全プロセスをステップごとに詳しく解説します。保険会社が絶対に教えてくれない交渉テクニックや、弁護士費用特約を最大限に活用する方法もお伝えしますので、ぜひ最後まで読んで、納得のいく解決につなげて頂けたら幸いです。
目次:
- 交通事故発生 示談成立までの8ステップ 複雑そうに見えて、実はシンプル!
- 事故直後の初動対応 24時間以内にすべきこと
- 治療段階で知っておくべきこと 戦略的通院が、その後の賠償額を左右する!
- 後遺障害認定を勝ち取るための3つのポイント これを知らないと損をする!
- 弁護士費用特約 完全活用術 見逃しがちな適用範囲と注意点、特約は使わなきゃ損!
- 保険会社との交渉術 プロが明かす5つの秘訣、これであなたも交渉上手!
- 慰謝料・休業損害を最大化 具体的な計算方法と驚きの増額事例、諦めないで!
- よくある質問と回答(Q&A) あなたの疑問、ここでスッキリ解決!
- 無料相談の活用方法 まずは、お気軽に弁護士にご相談
1. 交通事故発生 示談成立までの8ステップ 複雑そうに見えて、実はシンプル!

交通事故が発生してから示談が成立するまでの流れは、一見複雑に見えますが、大きく分けると8つのステップに整理できます。それぞれのステップで何をするべきか、具体的に見ていきましょう。
| ステップ | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 1 | 事故発生・警察への連絡 | どんなに小さな事故でも、必ず警察に連絡してください。これは法律で義務付けられていますし、後々のトラブルを防ぐためにも重要です。 |
| 2 | 事故現場の証拠保全 | スマートフォンで事故現場の写真をたくさん撮っておきましょう。車両の位置関係、道路の状況、相手の車のナンバー、損傷箇所など、様々な角度や距離から撮影することがポイントです。 |
| 3 | 加害者側との初動 | 物損については、こちらにも過失が発生する場合は保険会社同士の損害確認と過失割合の交渉、おけがについては、過失割合にもよりますが、相手保険の治療費の一括対応となります。一括対応されない場合、人身傷害保険・労災保険などとを使用して治療することが考えられます。 |
| 4 | 治療開始・通院 | 事故のケガは、必ず整形外科で診てもらいましょう。整骨院だけに通っていると、後で「治療とは認められない」と言われてしまう可能性があります。整骨院・接骨院に通院するのであれば、医師の同意を得ましょう。 |
| 5 | 症状固定 | 治療を続けても、これ以上良くならない状態を「症状固定」と言います。良くもならないし、悪くもならない一進一退の状態です。要するに、治療の効果が薄く、その後に残った症状については後遺障害としてまとめて評価されることになります。 |
| 6 | 後遺障害等級認定申請 | 症状固定後、後遺症が残った場合は、「後遺障害等級認定」の申請をします。この等級によって、受け取れる賠償金が大きく変わってきます。等級が付かないことももちろん多くあります。 |
| 7 | 示談交渉 | 保険会社との示談交渉は、弁護士に依頼するのがおすすめです。特に、弁護士費用特約に入っていれば、費用を気にせず依頼できます。また、慰謝料などの増額が期待できます。 |
| 8 | 示談成立・示談書作成/保険金支払い | 示談内容に納得できたら、示談書を作成します(免責証書・承諾書という名前が付いていることもあります。)。その後、保険会社から保険金が支払われて、一件落着となります。 |
2. 事故直後の初動対応 24時間以内にすべきこと

事故直後の対応は、その後の示談交渉を大きく左右する、非常に重要なポイントです。落ち着いて、以下の3つのことを必ず実行してください。
- 警察への連絡:
- どんなに小さな事故でも、必ず110番通報しましょう。
- 警察への連絡は、道路交通法で義務付けられています。
- 警察が作成する「事故証明書」は、後々の保険金請求などに必要になります。
- 事故現場の証拠保全:
- スマートフォンで、事故現場の写真をできるだけたくさん撮影しましょう。
- 以下の点を意識して撮影すると、証拠としての価値が高まります。
- 車両の位置関係: 相手の車と自分の車の位置関係、道路の幅などがわかるように。
- 路面のスキッドマーク(タイヤ痕): ブレーキ痕の有無や長さは、事故状況を把握する上で重要な手がかりになります。
- 周囲の標識や信号: 信号の色、一時停止の標識など、事故現場の状況を記録します。
- 車両の損傷箇所: 損傷の程度や場所を、様々な角度から撮影します。
- 相手の車のナンバー: 念のため、相手の車のナンバーも撮影しておきましょう。
- 防犯カメラの有無に注意し、ドライブレコーダーの記録があれば保存してください。
- 自分の加入する保険会社への連絡
- 自分の加入する保険会社に事故発生の連絡をしましょう。
- 車両のレッカーの手配などもしてくれます。
- 自分の加入する保険の代理店にも連絡しておくと良いでしょう。
3. 治療段階で知っておくべきこと 戦略的通院が、その後の賠償額を左右する!

交通事故のケガの治療は、単に痛みを取り除くだけでなく、その後の賠償額にも大きく影響することを覚えておきましょう。
- 整形外科への通院:
- 整骨院や接骨院だけでなく、必ず整形外科を受診しましょう。治療費、治療期間などが争いになると、不利です。
- 医師の診断書は、後遺障害の認定や、保険会社との交渉において、非常に重要な証拠となります。
- 整骨院や接骨院に通う場合も、医師の指示のもとで通うようにしましょう。
- 通院頻度:
- 医師の指示に従うことが大前提ですが、あまり頻繁に通院しても意味がありません。
- 通院頻度が少ないと、保険会社から「本当に治療が必要だったのか?」と疑われてしまう可能性もあります。ある程度通院期間が空いてしまいますと、治療費の対応が終了となることもあります。
- 症状固定のタイミング:
- 「症状固定」とは、治療を続けても、これ以上症状が良くならない状態のことです。
- 症状固定の時期は、医師とよく相談して、慎重に決める必要があります。
- 症状固定の時期が早すぎると、本来受け取れるはずの賠償金が減ってしまう可能性があります。
- MRIやCTスキャンなどの客観的な検査結果も、症状固定の判断材料となります。
- 保険会社からの治療打ち切り:
- 保険会社から治療の打ち切りを打診されることがあります。
- しかし、まだ治療が必要な場合は、安易に同意してはいけません。
- 治療費を打ち切られた後も、健保を使ったりして通院可能です。いつまでが正当な治療期間かは、最終的には裁判所が判断することです。
4. 後遺障害認定を勝ち取るための3つのポイント これを知らないと損をする!

事故によって後遺症が残ってしまった場合、「後遺障害等級認定」を受けることで、賠償金が大きく変わってきます。適切な等級認定を受けるためには、以下の3つのポイントを押さえておくことが重要です。
- 症状の一貫性:
- 事故直後から、症状が一貫して継続していることを示す必要があります。
- そのためには、事故直後からきちんと病院に通い、医師に症状を正確に伝えることが大切です。
- 痛みの部位や程度、日常生活への支障などを、具体的に記録しておきましょう。
- 治療の継続性:
- 適切な頻度で、継続的に治療を受けていることが必要です。
- 医師の指示に従い、リハビリなどもきちんと行いましょう。
- 自己判断で通院を中断したり、治療内容を変更したりしないようにしましょう。
- 医学的客観性:
- MRIやCTスキャンなどの画像所見、神経学的検査結果など、客観的な医学的証拠が必要です。
- 医師に、後遺障害診断書を詳しく作成してもらいましょう。
- 後遺障害診断書には、症状の経過、検査結果、今後の見通しなどを具体的に記載してもらうことが重要です。
さらに、日常生活への支障(就労状況、家事能力、睡眠障害など)を詳細に記録しておくことも、認定率を上げるために非常に重要です。例えば、「事故前は毎日できていた料理が、事故後は痛みでできなくなった」「夜中に何度も目が覚めてしまい、熟睡できない」といった具体的な状況を記録しておきましょう。
5. 弁護士費用特約 完全活用術 見逃しがちな適用範囲と注意点、特約は使わなきゃ損!

「弁護士費用特約」とは、交通事故の示談交渉などを弁護士に依頼する際の費用を、保険会社が負担してくれる制度です。
- 適用範囲:
- 多くの場合、契約者本人だけでなく、以下の人も対象になります。
- 配偶者
- 同居の親族
- 別居の未婚の子
- 事故車両に同乗していた人
- 自分の保険だけでなく、家族の保険に付帯している場合もあります。
- まずは、ご自身の加入している自動車保険の内容を確認してみましょう。
- 多くの場合、契約者本人だけでなく、以下の人も対象になります。
- 適用除外:
- 飲酒運転や無免許運転など、重大な過失がある場合は、弁護士費用特約が使えないことがあります。
- しかし、被害者側の過失がゼロの場合や、被害者自身は飲酒運転をしていなかった同乗者の場合は、弁護士費用特約が使えることがほとんどです。
- この点は、多くの人が誤解しているポイントなので、注意が必要です。
- 費用負担:
- 多くの保険会社では、以下の費用が補償されます(上限300万円程度)。
- 相談料(別枠で10万円であることが多いです)
- 着手金
- 報酬金
- 訴訟費用
- その他実費(交通費、通信費など)
- 弁護士費用特約を使えば、自己負担なしで弁護士に依頼できる場合がほとんどです。
- 多くの保険会社では、以下の費用が補償されます(上限300万円程度)。
6. 保険会社との交渉術 プロが明かす5つの秘訣、これであなたも交渉上手!

保険会社との示談交渉は、専門知識や経験がないと、不利な条件をそうと知らないまま、のまされてしまう可能性があります。ここでは、実際に使用可能な交渉テクニックを若干ご紹介します。
- 裁判基準での慰謝料算定:
- 保険会社は、独自の基準(任意保険基準)で慰謝料を提示してくることがありますが、これは裁判所の基準(裁判基準)よりも低い金額です。
- 弁護士は、裁判基準(赤い本など)に基づいて慰謝料を算定し、請求します。
- 裁判基準で慰謝料を請求することで、大幅な増額が見込めます。
- なお、本人で訴訟提起や紛争処理センター申立てをすれば、弁護士に依頼していなくとも裁判基準(弁護士基準)で計算されることになります。
- 休業損害の最大化:
- 休業損害とは、事故によって仕事を休んだことによる収入の減少のことです。
- 弁護士は、以下の方法で、休業損害の最大化を目指します。
- 会社員: 事故前3ヶ月の給与明細などを基に、1日あたりの収入を算出し、休業日数を乗じて計算します。有給休暇を取得した場合も、休業損害として請求できます。90で割るのではなく、実稼働日数で日額を算出すると、日額が多くなることが多いです。
- 自営業者: 事故前年の確定申告書などを基に、1日あたりの収入を算出します。
- 主婦(主夫): 賃金センサスの女子労働者の平均賃金を基に、1日あたりの収入を算出します。主婦の家事労働も、経済的な価値があると認められています。請求漏れが多いので注意が必要です。
- 過失割合の交渉:
- 過失割合とは、事故の責任が、加害者と被害者のそれぞれにどれだけあるかを示す割合です。
- 保険会社は、過失割合を被害者に不利なように提示してくることがあります。
- 弁護士は、事故現場の状況、ドライブレコーダーの映像、防犯カメラの取り付け、裁判例データベースから類似の裁判例の検出など、様々な証拠を基に、過失割合の交渉を行います。
7. 慰謝料・休業損害を最大化 具体的な計算方法
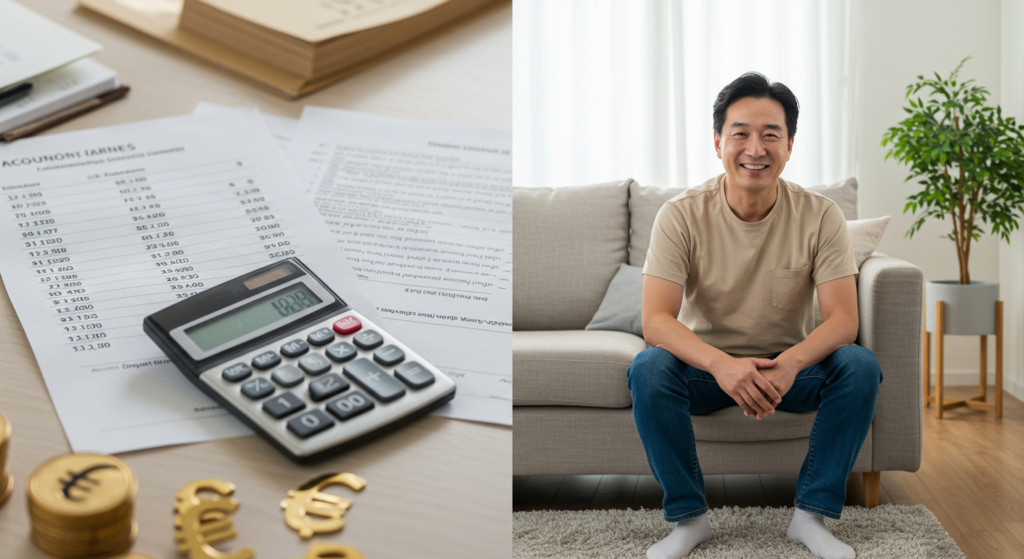
ここでは、慰謝料と休業損害の具体的な計算方法と、弁護士が介入することで実際に増額できた事例をご紹介します。
慰謝料の計算方法
- 入通院慰謝料:
- 裁判基準では、入通院期間に応じて、1日あたりの慰謝料額が定められています。
- 例えば、むちうちで3ヶ月通院した場合、裁判基準では約53万円の慰謝料が認められます(赤い本の別表Ⅱ基準)。
- しかし、保険会社は、自社の基準(任意保険基準)で計算するため、これよりも低い金額を提示してくることがほとんどです。
- 後遺障害慰謝料:
- 後遺障害慰謝料は、後遺障害の等級(1級~14級)に応じて、裁判基準で金額が定められています。
- 例えば、むちうちで後遺障害14級が認定された場合、裁判基準では110万円の慰謝料が認められます。
- しかし、保険会社は、後遺障害の等級を低く認定したり、後遺障害自体を認めなかったりすることがあります。また、逸失利益も少なく計算されていることがあります。
休業損害の計算方法
- 会社員:
- 事故前3ヶ月の給与明細などを基に、1日あたりの基礎収入を算出します。
- 基礎収入 × 休業日数 = 休業損害
- 有給休暇を取得した場合も、休業損害として請求できます。
- 自営業者:
- 事故前年の確定申告書などを基に、1日あたりの基礎収入を算出します。
- 通常、(所得+固定費)÷365日で日額を算出します。
- その上で、休業割合、休業日数をかけて、休業損害額を算出します。
- 主婦:
- 賃金センサスの女子労働者の平均賃金を基に、1日あたりの基礎収入を算出します。毎年増額傾向ですが、ざっくりと一日1万円強と考えておけば良いでしょう。
- 日額約1万円
- 1万円 × 休業割合(一日何%など)×休業日数 = 休業損害
8. よくある質問と回答(Q&A) あなたの疑問、ここでスッキリ解決!

ここでは、交通事故の示談交渉について、よくある質問にお答えします。
Q. 弁護士費用特約を使っても、保険料は上がりませんか?
A. ご安心ください。弁護士費用特約を使用しても、保険料が上がることはありません。ただし、弁護士費用特約と併せて、対物保険・対人保険・車両保険を使ったことによって、保険料が上がることはあります。
Q. 示談交渉には、どれくらいの期間がかかりますか?
A. 示談交渉の期間は、事故の状況や、治療中か、争点の多さ、後遺障害の有無などによって異なります。 単純な物損事故であれば、短期間で解決することもありますが、後遺障害が残る場合は、治療が終わってから、半年程度はみておいた方が良いかもしれません。
場合によっては、1年以上かかることもあります。訴訟になれば、提訴から1年くらいはかかると考えた方が良いでしょう。
弁護士にご依頼いただければ、示談交渉をスムーズに進めることができます。
Q. 他の弁護士事務所で断られた案件でも、依頼できますか?
A. 現在、多くの事務所では、他の事務所で断られた案件でも、事情を詳しくお伺いし、解決の可能性を探っていると思われます。
諦めずに、まずはご相談ください。
Q. 遠方に住んでいても、相談できますか?
A. 多くの事務所では、オンライン相談にも対応しております。 ズーム、グーグルミートなどのビデオ通話システムを利用してご相談いただけます。
Q. 加害者が無保険の場合は、どうすればよいですか?
A. 加害者が無保険の場合でも、諦める必要はありません。以下の方法で、損害賠償を請求できる可能性があります。
- 政府保障事業: 加害者が自賠責保険にも加入していない場合は、政府保障事業に損害賠償を請求できます(ただ、かなり時間がかかります)。
- 加害者個人の資産調査: 弁護士が、加害者の資産状況を調査し、債務名義(判決、和解調書など)に基づいて差し押さえなどの手続きを行います。
- ご自身の保険の利用: ご自身の保険に、車両保険や人身傷害保険が付帯している場合は、車両保険で車を修理し、人身傷害保険で治療をすることができます。
9. 無料相談の活用方法 まずは、お気軽に弁護士に相談

多くの事務所では、交通事故被害者の方を対象に、初回60分間の無料相談を実施しています。
無料相談の流れ:
- 事故状況の分析: 事故の状況を詳しくお伺いし、事故の原因や過失割合などを分析します。
- 証拠の評価: 事故現場の写真、診断書、警察の捜査記録など、証拠となる資料を拝見し、証拠の価値を評価します。
- 賠償見込み額の算出: 慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料など、受け取れる可能性のある賠償金の概算額を算出します。
- 最適な解決戦略の提案: 示談交渉、ADR、訴訟など、様々な解決方法の中から、お客様にとって最適な解決戦略を提案します。
どのような点に注意すべきか:
- 交通事故案件が得意か: 交通事故案件の豊富な経験と専門知識があるか。
- 解決実績: これまでに、数多くの交通事故案件を解決してきた実績があるか。
- 親身な対応: お客様の立場に立って、親身になってご相談に応じているか。
- 明朗会計: 弁護士費用は、事前に明確に説明されているか。
- 相性: 弁護士との相性はどうか。
今すぐアクション
- 保険会社に確認: まずは、ご自身の保険に「弁護士費用特約」が付いているかどうかを確認しましょう。
- 必要書類を準備: 交通事故証明書、診断書、保険会社からの連絡メモなど、お手元にある資料をご用意ください。
- 相談を予約: 相談日の日程調整をします。
交通事故の示談交渉は、ある程度、知識や経験がないと、不利な条件をのまされてしまう可能性があります。
弁護士に依頼することで、精神的な負担を軽減し、より良い解決を目指すことができます。
この記事が、少しでも役に立てば幸いです。














