
交通事故で怪我を負い、治療を続けたにもかかわらず、残念ながら後遺症が残ってしまうことがあります。その後遺症が「後遺障害」として認定されるかどうかは、その後の賠償金請求に大きな影響を与えます。特に、後遺障害14級9号の「局部に神経症状を残すもの」は、弁護士も扱う件数が最も多い等級であり、適切な対応が求められます。
「後遺障害14級ってどんな症状?認定される基準は?」
「14級の認定を受けたら、いくら賠償金をもらえるの?」
「保険会社から提示された金額に納得できない…」
「弁護士に相談すべきか迷っている…」
この記事は、交通事故で後遺症を負ってしまった方、特に後遺障害14級の認定について詳しく知りたい方に向けて解説するものです。
後遺障害14級の認定基準、具体的な症状例、賠償金請求のポイント、異議申立ての方法、そして弁護士に依頼するメリットと解決事例まで、幅広く網羅的に解説いたします。この記事を読むことで、あなたは後遺障害14級に関する疑問や不安を解消し、適切な賠償金を受け取るための具体的な行動を起こせるようになるでしょう。ぜひ最後までお読みいただき、あなたの権利を守るための一助としてください。
目次
- 後遺障害とは?交通事故における後遺障害の基礎知識
- 後遺障害14級の認定基準と具体的な症状例
- 後遺障害14級の認定を受けるためのポイントと注意点
- 後遺障害14級の賠償金|慰謝料、逸失利益、その他の損害
- 後遺障害14級の認定結果に納得できない場合の対処法|異議申立て
- 後遺障害14級の賠償金請求で弁護士に依頼するメリット
- 弁護士による後遺障害14級の解決事例
- 後遺障害14級の認定と賠償金請求に関するQ&A
- まとめ|後遺障害14級でお悩みの方は、まずは弁護士にご相談を
1. 後遺障害とは?交通事故における後遺障害の基礎知識

1-1. 後遺障害とは?症状固定との関係
後遺障害とは、交通事故による怪我が、適切な治療を続けたにもかかわらず、これ以上改善の見込みがない状態(症状固定)になった後も、身体に残ってしまった障害のことです。
「症状固定」とは、医学上一般的に認められた治療を継続しても、その効果が期待できなくなり、症状が一進一退(良くもならないし、悪くもならない状態)になったことを指します。けがが元通りに治った時点ではありません。症状固定の時期は、まず医師が判断しますが、最終的には裁判所の判断に委ねられることになります。
後遺障害は、症状固定後に残存する障害であり、その存在と程度は、医師が作成する「後遺障害診断書」によって証明されます(通常、A3の大きい紙で作成されます)。
1-2. 後遺障害等級とは?1級から14級までの分類と認定基準
後遺障害は、その障害の程度に応じて、1級から14級までの等級に分類されます(数字が小さいほど重い障害)。この等級は、労働能力の喪失の程度に基づいて定められており、後遺障害の等級によって、受け取れる賠償金の額が大きく変わってきます。
1-3. 後遺障害14級の位置づけ|最も多い認定件数と特徴
後遺障害14級は、後遺障害等級の中で最も軽度な等級であり、認定される件数が最も多い等級です。
後遺障害14級の各号は、
- 14級1号 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
- 14級2号 3歯以上に歯科補綴を加えたもの
- 14級3号 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
- 14級4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
- 14級5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
- 14級6号 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
- 14級7号 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
- 14級8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
- 14級9号 局部に神経症状を残すもの
とされています。
後遺障害14級に認定されることで、後遺障害慰謝料や逸失利益などの賠償金を請求することができます(ただし、「てのひらの大きさの醜いあとを残すもの」などについては、逸失利益が生じないなどと相手方から主張され、争われる場合があります)。

2. 後遺障害14級9号の認定基準と具体的な症状例

2-1. 後遺障害14級9号「局部に神経症状を残すもの」とは?
後遺障害14級の多くは、14級9号「局部に神経症状を残すもの」に該当します。
この「局部に神経症状を残すもの」とは、具体的には、神経系統の損傷によって生じる痛み、しびれ、麻痺などの症状が残存している状態を指します。
そして、労働能力喪失率としては一般的に5%、労働能力喪失期間としては、5年程度と評価されることが多いです(相手方保険会社からは、労働能力喪失率2~3%、労働能力喪失期間2~3年などと主張されることもあります)。

2-2. むちうち(頸椎捻挫、外傷性頸部症候群)と後遺障害14級
交通事故による後遺症として最も多いのが、むちうち(頸椎捻挫、外傷性頸部症候群)です。むちうちは、首(頸椎)が過度に伸展・屈曲することで、首の筋肉や靭帯、神経などが損傷する外傷です。
むちうちの症状は、首の痛み、肩こり、頭痛、めまい、吐き気、腕や手のしびれなど、多岐にわたります。これらの症状が、治療を続けても改善せず、症状固定後に残存した場合、後遺障害14級9号に認定される可能性があります。
ただし、むちうちの場合、レントゲンやMRIなどの画像検査で異常が見つからないことも多く、客観的な証拠が得られにくいという特徴があります。そのため、後遺障害14級の認定を受けるためには、医師による適切な診断と検査結果、症状の一貫性・継続性を証明することが重要となります。

2-3. その他の後遺障害14級に該当する可能性のある症状
むちうち以外にも、以下のような症状が後遺障害14級に該当する可能性があります。
- 腰椎捻挫後の腰痛、下肢のしびれ
- 打撲、挫創後の神経症状(痛み、しびれなど)
- 骨折後の関節可動域制限(神経症状があるもの)
これらの症状も、医師による適切な診断と、症状の一貫性・継続性を証明することで、後遺障害14級に認定される可能性があります。
2-4. 14級と12級の違い|「局部に神経症状を残すもの」と「局部に頑固な神経症状を残すもの」
後遺障害14級9号とよく比較されるのが、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」です。
- 14級9号「局部に神経症状を残すもの」: 神経学的検査(画像検査や各種テスト)で、客観的な異常所見が認められないものの、自覚症状(痛み、しびれなど)が残存し、その症状が医学的に説明可能な場合
- 12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」: 障害の存在が医学的(ないし他覚的)に証明できる場合
つまり、12級13号は、14級9号よりも症状が重く、医学的・他覚的に証明できる場合に認定される等級です。

3. 後遺障害14級の認定を受けるためのポイントと注意点

3-1. 医師による適切な診断と後遺障害診断書の作成
後遺障害14級の認定を受けるためには、まず、医師による適切な診断を受けることが不可欠です。
交通事故後、症状が改善しない場合は、自己判断せず、必ず医師の診察を受けましょう。そして、症状固定と判断されたら、医師に「後遺障害診断書」の作成を依頼します。
後遺障害診断書は、後遺障害の存在と程度を証明するための最も重要な書類です。後遺障害診断書には、以下の内容が記載されている必要があります。
- 傷病名
- 自覚症状
- 他覚的所見(神経学的検査の結果など)
- 可動域制限
- 障害の内容と程度
- 今後の見通し
- 日常生活への支障
後遺障害診断書は、医師が作成する書類ですが、記載内容が不十分であったり、誤りがあったりすると、適切な後遺障害等級が認定されない可能性があります。そのため、後遺障害診断書を受け取ったら、必ず内容を確認し、不明な点や疑問点があれば、医師に確認するようにしましょう(不十分な記載の場合、追記をお願いすることもあります。)。

3-2. 症状の一貫性と継続性を示す|通院頻度と治療内容の重要性
後遺障害14級の認定においては、症状の一貫性と継続性が非常に重視されます。
- 症状の一貫性: 交通事故直後から症状固定まで、症状に大きな変化がないこと
- 症状の継続性: 症状固定まで、継続的に治療を受けていること
これらの点を証明するためには、適切な頻度で通院し、適切な治療を受けることが重要です。また、ある程度の期間にわたって、通院する必要があります。
通院頻度があまりにも少なかったり、通院期間があまりに短かったり、治療内容が不適切であったりすると、症状の一貫性や継続性が認められず、後遺障害の認定が難しくなる可能性があります。

3-3. 神経学的検査(画像検査、各種テスト)の実施と結果の記録
後遺障害14級の認定においては、神経学的検査の結果も重要な判断材料となります。
神経学的検査には、以下のようなものがあります。
- 画像検査: レントゲン、MRI、CTなど
- 各種テスト: ジャクソンテスト、スパーリングテスト、筋力テスト、知覚テスト、深部腱反射テストなど
これらの検査によって、客観的な異常所見が認められれば、後遺障害12級13号に認定される可能性があります。
しかし、むちうちなどの場合、画像検査で異常が見つからないことも少なくありません。むしろ、頚部軟部組織の損傷にとどまり、特段の画像所見がないことが通常です。そのため、神経学的検査の結果だけでなく、自覚症状や日常生活への支障などを総合的に考慮して、後遺障害の等級が判断されます。

3-4. 日常生活への支障を具体的に伝える
後遺障害14級の認定においては、日常生活への支障も考慮されます。
- 仕事や家事が以前のようにできなくなった
- 趣味やスポーツができなくなった
- 睡眠障害や集中力低下がある
など、具体的な支障の内容を、医師に伝えるようにしましょう。
4. 後遺障害14級の賠償金|慰謝料、逸失利益、その他の損害

4-1. 後遺障害慰謝料|自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)
後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ってしまったことに対する精神的苦痛に対する補償です。後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害の等級によって異なり、14級の場合は、以下の3つの基準によって金額が大きく異なります。
- 自賠責基準: 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の基準。最低限の補償であり、金額は最も低い。
- 任意保険基準: 各保険会社が独自に設定している基準。自賠責基準よりは高いが、弁護士基準よりは低い。
- 弁護士基準(裁判基準): 過去の裁判例に基づいて算定される基準。3つの基準の中で最も高額。
後遺障害14級の場合、自賠責基準では後遺傷害慰謝料としては32万円ですが、弁護士基準では110万円程度が相場となります。
ただし、弁護士に依頼したとしても、示談交渉時においては、任意保険会社は、弁護士基準の8~9割程度の後遺障害慰謝料しか認定しないこともあります。

4-2. 後遺障害逸失利益|労働能力喪失率と喪失期間
後遺障害逸失利益とは、後遺障害によって労働能力が低下し、将来得られるはずだった収入が減少することに対する補償です。もちろん、後遺障害慰謝料とは別の費目です。
後遺障害逸失利益は、以下の計算式で算定されます。
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
- 基礎収入: 原則として、事故前年の年収
- 労働能力喪失率: 後遺障害の等級に応じて定められており、14級の場合は5%
- 労働能力喪失期間: 原則として、症状固定時の年齢から67歳までの期間(ただし、14級の場合は、5年程度に制限されることが多い)
- ライプニッツ係数: 労働能力喪失期間に応じた係数(中間利息を控除するための係数)
逸失利益の例:年収400万円(事故前年度の年収)×5%(労働能力喪失率)×4.5797(5年ライプニッツ係数)=91万5940円。
これに後遺傷害慰謝料110万円を加算すると、後遺障害分の損害としては、110万円+91万5940円=201万5940円となります。
4-3. その他の損害|治療費、通院交通費、装具費など
後遺障害慰謝料や逸失利益以外にも、以下のような損害を請求することができます。こちらは、基本的に症状固定前の損害となります。
- 治療費: 交通事故による怪我の治療にかかった費用
- 通院交通費: 通院にかかった交通費(公共交通機関の運賃、自家用車のガソリン代(キロ15円が相場です)、駐車場代など)
- 装具費: コルセットなどの装具を購入した費用
- 入院雑費: 入院中の日用品費など(赤い本基準で、日額1500円)
- 休業損害: 仕事を休業したことによる損害
- 入通院慰謝料: 症状固定前の入通院分の慰謝料
4-4. 【表で比較】後遺障害14級の賠償金相場(自賠責基準、弁護士基準)
| 損害項目 | 自賠責基準 | 弁護士基準(裁判基準) |
|---|---|---|
| 後遺障害慰謝料 | 32万円 | 110万円程度 |
※上記は個別の事案によって金額が異なることがあります。
5. 後遺障害14級の認定結果に納得できない場合の対処法|異議申立て
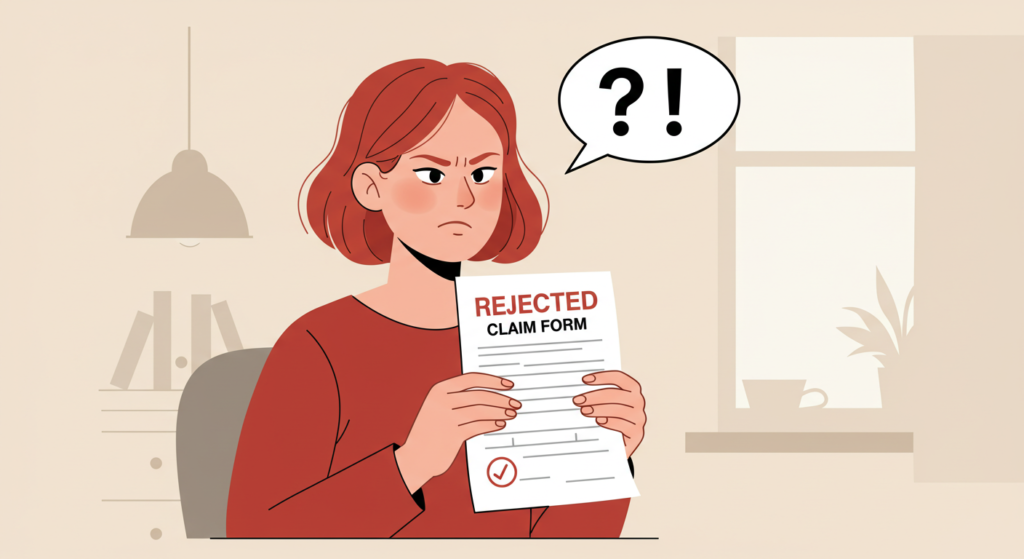
5-1. 異議申立てとは?制度の概要と手続きの流れ
異議申立てとは、自賠責保険会社(または損害保険料率算出機構)が行った後遺障害等級認定の結果に不服がある場合に、再度審査を求める手続きです。
異議申立ては、書面で行います。異議申立書に、認定結果に納得できない理由や、新たな証拠(医師の意見書、検査結果など)を添付して、自賠責保険会社、または任意保険会社に提出します。
5-2. 異議申立ての成功率を高めるためのポイント|新たな証拠の提出
異議申立ての成功率を高めるためには、新たな証拠を提出することが重要です(正直、異議申立てで非該当を覆すことは簡単ではありません)。
- 医師の意見書: 認定された等級よりも上位の等級に該当する、または非該当から14級に該当するという内容の意見書
- 新たな検査結果: 症状固定後に新たに実施した検査の結果(MRI、CT、神経学的検査など)
- 日常生活への支障に関する資料: 仕事や家事への支障を具体的に示す資料(診断書、業務日報など)
- 医療機関のカルテ
- 医師に対する医療照会・回答書
- 刑事記録
これらの新たな証拠を提出することで、認定結果が見直される可能性があります(逆に言えば、新たな医証が提出されない限り、等級認定が覆る可能性は低いです)。

6. 後遺障害14級の賠償金請求で弁護士に依頼するメリット

6-1. 適正な後遺障害等級認定のサポート|医学的証拠の収集と分析
弁護士は、後遺障害等級認定の手続きに精通しており、適切な後遺障害等級の認定を受けるためのサポートを行います。
具体的には、
- 後遺障害診断書の記載内容のチェック
- 必要な検査の提案
- 医師との連携
- 医学的証拠の収集と分析
などを行い、後遺障害等級認定の可能性を高めます。

6-2. 弁護士基準(裁判基準)による賠償金請求|大幅な増額の可能性
弁護士に依頼することで、弁護士基準(裁判基準)による賠償金請求が可能となります。弁護士基準は、自賠責基準や任意保険基準よりも高額であるため、賠償金が大幅に増額する可能性があります。
6-3. 保険会社との示談交渉を全面的に代行|精神的負担の軽減
弁護士は、保険会社との示談交渉を全面的に代行します。被害者は、保険会社との交渉による精神的なストレスから解放され、治療やリハビリに専念することができます。
6-4. 煩雑な手続きからの解放|時間と労力の節約
後遺障害等級認定の申請や、保険会社との示談交渉、異議申立てなど、交通事故後の手続きは非常に煩雑です。弁護士に依頼することで、これらの手続きをすべて任せることができ、時間と労力を節約することができます。平日の昼間に、保険会社からの電話対応をしたり、自分で書類の準備をしたりすることは難しい方も多いでしょう。
7. 弁護士による後遺障害14級の解決事例

(ただし、以下は監修した弁護士が扱った実際の事例)
7-1. むちうちで非該当から14級9号に認定され、賠償金が大幅に増額した事例
【事例概要】
後遺障害非該当であったが、異議申立てにより14級9号を獲得し、紛争処理センターへの申立てを行い、賠償金約360万円を獲得した事例
【弁護士の活動・結果】
被害者は後遺障害非該当であったものの、頸椎捻挫・腰椎捻挫の症状を訴えていました。新たな医証を収集し、被害者請求にて異議申立てを行ったところ、14級9号「局部に神経症状を残すもの」を獲得し、紛争処理センターへの申立ても行い、裁判基準満額での示談に成功しました。
7-2. 異議申立てで12級が認められ、示談交渉で増額した事例
【事例概要】
事前認定で後遺障害非該当も、異議申立てにより12級を獲得した事例
【弁護士の活動・結果】
任意保険会社の事前認定では、後遺障害非該当でしたが、医師面談・医療照会等により被害者の症状を裏付ける医証を取り揃え、被害者請求による異議申立てを行った結果、後遺傷害12級を獲得しました。
7-3. 裁判で後遺障害14級が認められ、適切な賠償金を獲得した事例
【事例概要】
被害者請求にて後遺障害非該当も、訴訟において後遺障害の存在を裁判所が認定し、和解終結となった事例
【弁護士の活動・結果】
頚椎捻挫及び腰椎捻挫にて治療後、被害者請求にて自賠責保険会社に後遺障害申請を行いましたが、以前の事故で後遺障害の等級が付いているとして、非該当の判断でした(自賠責保険会社は、今でも後遺障害の永久残存性を主張し、再度の14級の認定を認めません)。異議申立てや紛争処理機構では等級が付くことは無いため、訴訟提起しましたが、以前の事故での後遺障害は消滅していることを粘り強く主張し、裁判所も後遺障害の発生を認め、和解終結となりました。
8. 後遺障害14級の認定と賠償金請求に関するQ&A
8-1. 後遺障害診断書はいつ書いてもらえばいいですか?
後遺障害診断書は、医師に症状固定と判断されるようでしたら、こちらから医師に書式をお渡しし、医師に作成してもらいます。症状固定の時期は、医師が判断します。
後遺障害診断書の書式は、事前認定の場合、任意保険会社から送付されます。被害者請求の場合は、自分で用意する必要があります。
また、後遺障害診断書作成料がかかります(安くて5500円、高ければ数万円のことも。)が、任意保険会社の事前認定であっても、自分で負担を求められることがあります。
8-2. 症状固定後も治療を続けてもいいですか?
症状固定後も、症状の緩和や悪化防止のために、治療を続けることは自由です。ただし、症状固定後の治療費は、原則として自己負担となります(健康保険を使用して、負担を減らしてください)。なお、症状固定後も自費にて治療を継続していたことが、異議申立てに当たって有利な資料となることもあります。
8-3. 異議申立ては何度でもできますか?
異議申立ての回数に制限はありません。ただし、新たな医証を準備できない限り、異議申立てで等級認定が覆る可能性は低いでしょう。
8-4. 弁護士費用特約とは何ですか?
弁護士費用特約とは、自動車保険の特約の一つで、交通事故の被害者が弁護士に依頼した際の弁護士費用を、保険会社が一定額まで負担してくれるというものです。弁護士費用特約を利用すれば、基本的に自己負担なく、弁護士に依頼することができます。
弁護士費用特約の有無につきましては、自分の自動車保険や、家族の自動車保険を確認してみましょう。代理店や、保険会社に電話して確認してみるのが早いです。

9. まとめ|後遺障害14級でお悩みの方は、まずは弁護士にご相談を
この記事では、交通事故における後遺障害14級について、認定基準、賠償金請求、異議申立て、弁護士に依頼するメリットなど、幅広く解説しました。
後遺障害14級は、認定される件数が最も多い等級であり、適切な対応が求められます。後遺障害14級の認定や賠償金請求でお悩みの方は、まずは弁護士にご相談ください。
弁護士は、あなたの味方となり、適正な後遺障害等級の認定と、適切な賠償金の獲得に向けて、全力でサポートいたします。














