
自転車って、本当に便利ですよね。通勤・通学、お買い物、ちょっとしたお出かけ…、私たちの生活に欠かせない存在です。でも、便利で身近な乗り物だからこそ、事故のリスクも常に隣り合わせ。
「もしも自転車事故に遭ってしまったら…」
「もしも自転車で人に怪我をさせてしまったら…」
考えたくないことですが、誰にでも起こりうるのが自転車事故です。
事故に遭ってしまったら、パニックになってどうすればいいかわからない…という方も多いでしょう。また、加害者になってしまったら、「どう責任を取ればいいんだろう…」と不安でいっぱいになるかもしれません。
でも、安心してください!この記事では、交通事故問題に詳しい弁護士が、自転車事故に関するあらゆる疑問にお答えします。
- 被害者になった場合: どのように損害賠償を請求すればいいのか?
- 加害者になった場合: どう対応すれば、被害者の方に誠意を尽くし、自身の負担を最小限に抑えられるのか?
自転車事故の「もしも」に備えるための、そして、不幸にして事故に遭ってしまった、または起こしてしまった時のための、完全ガイドです。
専門用語はできるだけ避けて、わかりやすく解説していきますので、ぜひ最後まで読んで、あなたの不安や疑問を解消してください。
目次
- 【他人事じゃない!】自転車事故の現状と知っておくべきこと
- 【重要】自転車事故の過失割合|あなたの責任はどれくらい?
- 【知っておきたい】自転車事故の損害賠償|請求できるお金と計算方法
- 【備えあれば憂いなし】自転車事故と保険|入っておくべき?保険の種類と活用法
- 【加害者になったら…】自転車事故の刑事責任と行政処分
- 【困ったときは】自転車事故で弁護士に相談するメリット
- 【解決事例】弁護士が介入して、こんなに変わった!
- 【気になる疑問を解決!】自転車事故に関するQ&A
- まとめ|自転車事故は弁護士に相談し、適切な解決を!
1. 【他人事じゃない!】自転車事故の現状と知っておくべきこと
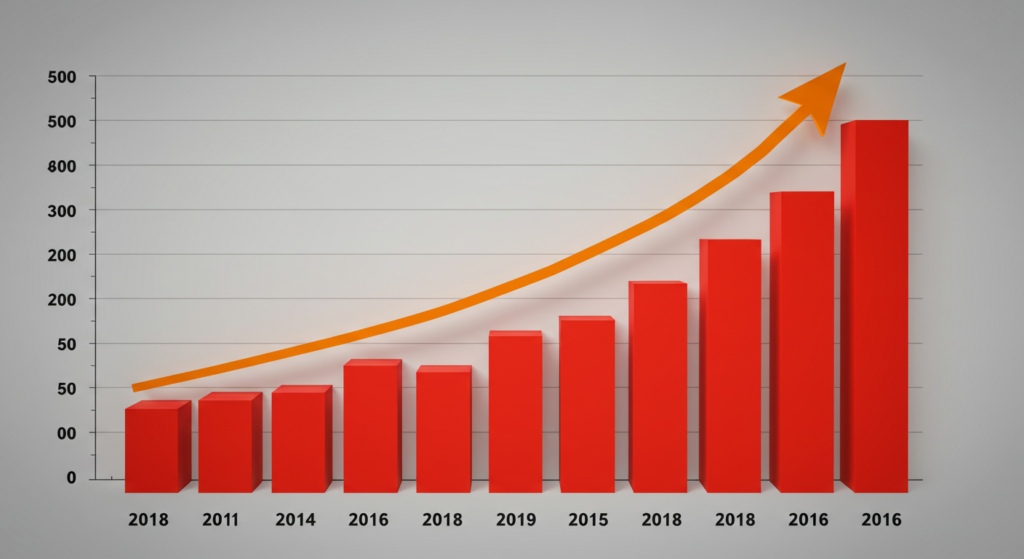
1-1. えっ、こんなに多いの!?自転車事故の発生件数
警察庁の統計によると…
- 自転車事故の件数は、近年、減少か横ばい傾向にはあるものの…
- 交通事故全体に占める自転車関与事故の割合を示す「自転車関与率」は、都内の令和6年度のデータでは、45.8パーセントとなります。すなわち、事故の約半分は自転車の事故です。
- 特に、65歳以上の事故が多い傾向にあります。
- 死亡事故や重傷事故も、決して少なくありません。

1-2. なぜ事故は起こる?自転車事故の主な原因
自転車事故の原因は、さまざまですが、主なものとしては、以下のようなものが挙げられます。
1-2-1. 運転者の不注意(ながらスマホ、イヤホンなど)
「ちょっとだけなら…」という油断が、重大な事故につながります。スマートフォンを操作しながら、イヤホンで音楽を聴きながらの運転は、周囲の状況への注意が散漫になり、非常に危険です。道路交通法でも禁止されています。
1-2-2. 交通ルール違反(信号無視、一時停止無視、無灯火など)
「車も来てないし、大丈夫だろう」「みんなやってるし…」という安易な気持ちが、事故を招きます。自転車も、車両の一種です(「軽車両」といいます)。交通ルールを守りましょう。

1-2-3. 道路環境の問題(見通しの悪い交差点、狭い道など)
道路の構造や、交通量なども、事故の原因となることがあります。見通しの悪い交差点では、特に注意が必要です。
1-3. 自転車事故、被害者はつらい… でも加害者も大変!
自転車事故は、被害者にとってつらいものです。怪我の痛み、治療の苦しみ、後遺症の不安…。しかし、加害者になってしまった場合も、その責任は重大です。
- 民事上の責任: 被害者への損害賠償
- 刑事上の責任: 罰金や懲役
- 行政上の責任: (自動車の場合)免許停止、免許取消

1-4. 車の事故とはココが違う!自転車事故の特殊性
自転車事故は、自動車事故とは異なる、いくつかの特殊性があります。
1-4-1. 強制保険(自賠責保険)がない!
自動車には、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)という強制保険がありますが、自転車には、このような強制保険がありません(一部の自治体では、自転車保険への加入が義務化されています。ただし、加入しなくても罰則はなし。)。
そのため、加害者が任意保険に加入していない場合、被害者は、加害者本人に損害賠償を請求しなければならず、十分な賠償を受けられない可能性があります。

1-4-2. 過失割合ってどう決まるの?
自転車事故の過失割合は、自動車事故と同様に、事故の状況によって判断されます。しかし、自転車は、自動車に比べて速度が遅く、車体が小さいため、自動車よりも過失割合が小さくなることもあります。
ただし、自転車側の交通ルール違反(信号無視、一時停止無視など)がある場合は、自転車側の過失割合が大きくなることもあります。
別冊判例タイムズ38号、赤い本(民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準)には、自転車事故の類型に応じ、過失割合の基準が定められています。
1-4-3. 後遺障害って、自転車事故でも認定されるの?
相手が自転車で、怪我を負い後遺症が残った場合でも、自動車事故と同様には、後遺障害等級認定を受けることができません。自転車には自動車のように、自賠責の調査事務所などありません。後遺障害は、自転車を運転する加害者が任意保険に加入していれば任意保険会社の自社認定、被害者が人身傷害保険を使うことができる場合、人傷社の自社認定がなされることがあります。
しかし、自転車事故の場合、自動車事故に比べて、後遺障害の認定が難しい場合があります。争いがある場合、最終的には、やはり裁判所に認定してもらうほかはありません。

1-4-4. 損害賠償って、どこまで請求できるの?
自転車事故の損害賠償は、自動車事故と同様に、治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益などを請求することができます。
ただし、自転車事故には自賠責保険の適用がなく、また、任意保険に加入している方も未だに多いとはいえませんので、最終的な回収額が低くなる傾向があります(自転車を運転する相手方が無保険の場合、取りはぐれる危険があります。)
2. 【重要】自転車事故の過失割合|あなたの責任はどれくらい?

2-1. 過失割合って何? 損害賠償額にどう影響する?
過失割合とは、事故の発生原因について、加害者と被害者のどちらにどれだけの責任(過失)があるのかを割合で示したものです。
例えば、
- 加害者の過失割合が100%、被害者の過失割合が0%の場合、被害者は損害の全額を加害者に請求できます。
- 加害者の過失割合が70%、被害者の過失割合が30%の場合、被害者は損害額の70%を加害者に請求できます(自分の損害のうち、30%は自己負担。また、相手に損害が生じている場合、相手の損害の30%を負担することになります。)。
このように、過失割合は、損害賠償額を大きく左右します。

2-2. 自転車事故の過失割合、基本的な考え方
自転車事故の過失割合は、自動車事故と同様に、道路交通法などの法令違反の有無、事故現場の状況、当事者の注意義務違反の程度などを総合的に考慮して判断されます。
ただし、自転車は自動車に比べて交通弱者として扱われることもあり、同じような事故状況でも、自動車事故とは異なる過失割合が適用されることがあります。
2-3. よくあるケース別!過失割合の具体例
以下に、自転車事故の典型的なケースにおける過失割合の目安を示します。
| 事故状況 | 自転車の基本過失割合 | 備考 |
|---|---|---|
| 自転車と四輪車、信号なし交差点(同副員)、交差道路同士 | 20% | 判例タイムズ【240図】 |
| 自転車道路直進、四輪車路外から道路進入 | 10% | 判例タイムズ【299図】 |
| 同一方向進行、四輪車進路変更(四輪車の幅寄せ)) | 10% | 判例タイムズ【305図】 |
| 自転車と歩行者 | 65%~100% | ケースバイケースだが、圧倒的に自転車の過失が大きくなることが多い |
| 対向方向に進行する自転車同士の事故 | 50% | 双方に同程度の過失があると判断されることが多い |
※注意: 上記はあくまで目安であり、実際の過失割合は、個別の事故状況によって異なります。

2-4. 過失割合が変わることも!加算要素と減算要素
過失割合は、基本的な過失割合をベースに、事故状況に応じて修正されることがあります。
2-4-1. 加算要素(自転車側の過失を重くする事情)
- 酒酔い運転: 重大な過失とみなされます。
- 携帯電話等使用: 著しい過失と判断されます。
- 二人乗り、並進、無灯火、片手運転: こちらも著しい過失と判断されます。
2-4-2. 減算要素(自転車側の過失を軽くする事情)
- 自転車の運転者が児童等や高齢者の場合: 児童等(おおむね13歳未満)や高齢者(おおむね65歳以上)は、交通弱者として保護されます。
- 自転車の自転車横断帯通行
3. 【知っておきたい】自転車事故の損害賠償|請求できるお金と計算方法

自転車事故の被害者は、加害者に対して、どのような損害賠償を請求できるのでしょうか?ここでは、請求できる損害項目と、その計算方法について解説します。
3-1. 誰に請求すればいいの?損害賠償請求の相手方
自転車事故の損害賠償請求の相手方は、以下のようになります。
3-1-1. 加害者本人・親権者
加害者が自転車保険に加入していない場合は、加害者本人に対して損害賠償を請求します。親権者に監督者責任を追及することも考えられます。
3-1-2. 保険会社(加害者が加入している場合)
加害者が自転車保険や個人賠償責任保険(自動車保険や、火災保険の特約として付いていることもあります)などに加入している場合は、保険会社に対して損害賠償を請求します。

3-1-3. 勤務先の会社(業務中の事故の場合)
加害者が業務中に自転車事故を起こした場合、加害者の勤務先の会社に対して損害賠償を請求できる場合があります。
3-1-4. 自治体(道路の管理に問題があった場合など)
道路の管理に瑕疵(欠陥)があったことが事故の原因である場合、道路管理者である国や自治体に対して損害賠償を請求できる場合があります。
3-2. どんなお金が請求できる?損害賠償請求の項目
自転車事故の被害者が請求できる損害賠償項目は、大きく分けて、積極損害、消極損害、慰謝料の3つがあります。
3-2-1. 積極損害(治療費、付添看護費、通院交通費など)
積極損害とは、交通事故によって実際に出費した費用のことです。
- 治療関係費: 治療費、入院費、手術費、投薬費、診断書作成費用など
- 付添看護費: 入院または通院に付添が必要な場合の費用(医師の指示や、被害者の年齢・症状などから判断)
- 通院交通費: 通院にかかった交通費(公共交通機関の運賃、自家用車のガソリン代・駐車場代など。タクシー代は必要性が認められる場合に限る)
- 装具・器具購入費: コルセット、松葉杖、義肢、車椅子などの購入費用
- 家屋・自動車改造費: 自宅や自動車をバリアフリー化するための費用(後遺障害が残った場合など)
- 葬儀関係費: 死亡事故の場合の葬儀費用
3-2-2. 消極損害(休業損害、逸失利益)
消極損害とは、交通事故によって得られなくなった利益のことです。
- 休業損害: 事故による怪我で仕事を休んだことによる収入の減少分。
- 会社員(給与所得者): 事故前3ヶ月間の給与を基に、1日あたりの収入額を算出し、休業日数に応じて計算。
- 自営業者: 事故前年の確定申告書の所得額を基に、1日あたりの収入額を算出し、休業日数に応じて計算。
- 家事従事者(主婦・主夫): 女性労働者の平均賃金(賃金センサス)を基に、1日あたりの収入額を算出し、休業日数に応じて計算。
- 学生・生徒: 原則として休業損害は認められないが、アルバイトなどで収入を得ていた場合は、その収入の減少分が認められる。
- 無職者: 原則として休業損害は認められないが、就労の蓋然性がある場合は、認められる可能性あり。
- 逸失利益:
- 後遺障害逸失利益: 後遺障害が残ったことによって、労働能力が低下し、将来得られるはずだった収入が減少することに対する補償。
- 計算式: 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
- 死亡逸失利益: 被害者が死亡した場合に、将来得られるはずだった収入の減少に対する補償。
- 計算式: 基礎収入 × (1 – 生活費控除率) × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
- 後遺障害逸失利益: 後遺障害が残ったことによって、労働能力が低下し、将来得られるはずだった収入が減少することに対する補償。

3-2-3. 慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)
慰謝料とは、交通事故によって受けた精神的苦痛に対する補償です。
- 入通院慰謝料: 入院や通院を余儀なくされたことによる精神的苦痛に対する慰謝料。
- 入通院期間、通院頻度、怪我の程度などを考慮して金額が決定される。
- 自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準によって金額が大きく異なる。
- 後遺障害慰謝料: 後遺障害が残ってしまったことによる精神的苦痛に対する慰謝料。
- 後遺障害の等級に応じて、金額が定められている。
- 自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準によって金額が大きく異なる。
- 死亡慰謝料: 被害者が死亡した場合の、被害者本人および遺族に対する慰謝料。
- 被害者の年齢、家族構成などを考慮して金額が決定される。

3-2-4. 物的損害(自転車の修理費用など)
自転車事故によって、自転車や衣服、持ち物などが壊れた場合、物的損害に対する賠償を請求することができます。
- 自転車の修理費用: 修理が可能な場合は、修理費用を請求できます。
- 自転車の時価額: 自転車の時価が修理費よりも低い場合(経済的全損)は、事故当時の自転車の時価額の認定にとどまります。
- 衣服、持ち物などの損害: 事故によって破損した衣服や持ち物の損害を請求できます。

3-2-5. その他の損害
上記の他にも、訴訟では、以下のような損害が認められます。判決まで行かず、和解で終結する場合は調整金という名目で、加算されることがあります。
- 遅延損害金(事故日から年3%)
- 弁護士費用(認容額の1割)
3-3. どうやって計算する?損害賠償額の算定基準
損害賠償額の計算方法には、以下の3つの基準があります。
3-3-1. 自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)の違い
- 自賠責基準: 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の基準。法令で定められた最低限の補償であり、金額は最も低いことが多い。なお、自転車には自賠責保険は付帯していません。
- 任意保険基準: 各保険会社が独自に設定している基準。自賠責基準よりは高いが、弁護士基準よりは低い。具体的な金額や計算方法は非公開。
- 弁護士基準(裁判基準): 過去の裁判例に基づいて算定される基準。3つの基準の中で基本的に最も高額。

3-3-2. 保険会社はどの基準で計算する?
保険会社は、通常、任意保険基準に基づいて損害賠償額を算定し、被害者に提示します。任意保険基準は、各保険会社が非公開で設定しているため、具体的な計算方法や金額は、被害者には知らされません。
3-3-3. 弁護士に依頼すると、なぜ賠償額が増えるの?
弁護士に依頼することで、弁護士基準(裁判基準)で損害賠償額を請求することが可能となり、大幅な増額が期待できます。
弁護士基準は、過去の裁判例を参考にしているため、法的にも正当性が高く、保険会社も無視することはできません。また、弁護士は、被害者の個別の事情(怪我の程度、後遺障害の内容、収入、家族構成など)を丁寧に検討し、最大限の賠償額を獲得できるよう、尽力します。
3-4. 【具体例で解説】損害賠償額の計算シミュレーション
| 損害項目 | 自賠責基準 | 任意保険基準(例) | 弁護士基準 |
|---|---|---|---|
| 治療関係費 | 実費 | 実費 | 実費 |
| 休業損害 | 原則1日6,100円 ※上限あり | 保険会社基準 | 基礎収入 × 休業日数 |
| 入通院慰謝料 | 1日あたり4,300円 × 対象日数 | 保険会社基準 | 通院期間に応じた金額(例:通院3ヶ月で73万円。別表Ⅰ) |
| 後遺障害慰謝料 | 等級に応じた金額(例:14級で32万円) | 保険会社基準 | 等級に応じた金額(例:14級で110万円) |
| 後遺障害逸失利益 | 計算式は弁護士基準に準じるが、金額は低い | 保険会社基準 | 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 |
※上記はあくまで一例であり、実際の金額は、個別の状況によって異なります。
4. 【備えあれば憂いなし】自転車事故と保険|入っておくべき?保険の種類と活用法

4-1. 自転車保険ってどんなもの?
自転車事故に関連する保険には、様々な種類があります。
4-1-1. 個人賠償責任保険
自転車事故で相手に怪我をさせたり、物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金を補償する保険です。
自分が自転車を運転しているときに交通事故に遭った場合、まず真っ先に、自分の自転車保険・個人賠償責任保険の有無を確認すべきです。
- 特徴:
- 自転車事故以外の日常生活における賠償事故も補償対象となっていることもあります
- 保険料が比較的安い(月数百円程度から)
- 自動車保険、火災保険、クレジットカードなどに特約として付帯している場合がある
- 賃貸の場合でも、火災保険に個人賠が付帯されている場合があります。
4-1-2. TSマーク付帯保険
自転車安全整備士が点検・整備した自転車に貼付されるTSマークに付帯する保険です。
- 特徴:
- 賠償責任保険と傷害保険がセットになっている
- TSマークの有効期間は1年間
- 賠償責任の補償額は、TSマークの種類によって異なる
4-1-3. 自転車保険(傷害保険、賠償責任保険)
自転車事故による自身の怪我や、相手への損害賠償に備える保険です。
- 特徴:
- 保険会社によって、補償内容や保険料が異なる
- 示談交渉サービスが付帯している場合がある
4-2. 自動車保険の特約もチェック!
自動車保険に付帯する特約の中には、自転車事故を補償対象とするものがあります。
- 個人賠償責任特約: 被保険者やその家族が、日常生活で他人に怪我をさせたり、物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金を補償する特約です。自転車事故も補償対象となることが多いです。
- 人身傷害保険: 被保険者が、交通事故(自動車事故だけでなく、自転車事故も含む)で怪我をした場合に、治療費や休業損害、慰謝料などが支払われる保険です。
4-3. 自転車保険、入るべき?義務化の動きも
近年、自転車事故による高額賠償事例が発生していることなどから、自転車保険への加入を義務化する自治体が増えています。
- 義務化の背景:
- 自転車事故による高額賠償事例の発生(数千万円の賠償命令が出たケースも)
- 被害者救済の必要性
- 自転車利用者の安全意識向上
- 義務化の内容:
- 自転車利用者に対して、自転車保険(または個人賠償責任保険)への加入を義務付ける
- 条例で義務化されている場合でも、罰則があるかは別
お住まいの自治体で自転車保険の加入が義務化されているかどうか、確認しておきましょう。また、義務化されていない地域でも、万が一の事故に備えて、安心のため、自転車保険への加入を強くおすすめします。
4-4. 保険会社との示談交渉、ここがポイント!
自転車事故で怪我をした場合、または怪我をさせてしまった場合、加害者側の保険会社と示談交渉を行うことになります。
示談交渉のポイント:
- 保険会社から提示された示談内容(過失割合、損害賠償額など)を十分に確認する
- 納得できない場合は、安易に示談に応じない
- わからないことや疑問点があれば、保険会社に質問する
- 必要に応じて、弁護士に相談する

4-5. もしも相手が無保険だったら…?
加害者が自転車保険に加入していない場合、被害者は、加害者本人に対して損害賠償を請求することになります。
加害者が無保険の場合の対応:
- 加害者本人との交渉(直接交渉、または弁護士を通じて交渉)
- 加害者の親権者など監督義務者との交渉
- 内容証明郵便の送付
- 支払督促、少額訴訟、通常訴訟などの法的手段
加害者が無保険の場合、損害賠償金の回収が困難になる可能性があります。このような場合は、弁護士に相談し、適切な対応を取ることが重要です。

5.【加害者になったら…】自転車事故の刑事責任と行政処分

5-1. 自転車事故で問われる罪って?
- 5-1-1. 過失致死傷罪・重過失致死傷罪 自転車事故で、人に怪我をさせたり、死亡させたりした場合、過失運転致死傷罪や重過失致死傷罪に問われる可能性があります。
- 過失致傷罪: 過失によって人を傷害した場合。
- 30万円以下の罰金または科料
- 5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金
- 過失致傷罪: 過失によって人を傷害した場合。
- 5-1-2. 道路交通法違反 信号無視、一時停止違反、無灯火、二人乗り、並進、酒酔い・酒気帯び運転、携帯電話等使用など、道路交通法に違反する行為があった場合。
5-2. 逮捕されることもあるの?
自転車事故でも、以下のような場合は、逮捕・勾留される可能性があります。
- 死亡事故や重傷事故
- ひき逃げ
- 酒酔い運転、酒気帯び運転
- 証拠隠滅や逃亡の恐れがある場合
5-3. 刑事手続きの流れ(警察の捜査、検察庁への送致、起訴・不起訴、裁判)
自転車事故で刑事責任を問われる場合、以下のような流れで手続きが進められます。
- 警察による捜査: 事故現場の検証、当事者や目撃者からの事情聴取、証拠収集などが行われます。
- 逮捕・勾留: 必要に応じて、逮捕・勾留されることがあります。
- 検察庁送致: 警察での捜査が終了すると、事件が検察庁に送られます。
- 検察官による捜査: 検察官が、被疑者(加害者)の取り調べや、証拠の検討などを行います。
- 起訴・不起訴の決定: 検察官が、被疑者を起訴するか不起訴にするかを決定します。
- 起訴: 裁判所に訴えを提起すること。
- 不起訴: 刑事裁判にかけないこと。不起訴には、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予などの種類があります。
- 裁判: 起訴された場合、裁判所で審理が行われます。
- 判決: 裁判官が、有罪または無罪の判決を言い渡します。有罪の場合、刑罰(懲役、禁錮、罰金など)が科せられます。
5-4. 罰金と反則金、どう違う?
- 罰金: 刑事罰の一種であり、裁判を経て科せられます。前科がつきます。
- 反則金: 比較的軽微な交通違反に対して科せられる行政処分です。前科はつきません。
5-5. 自転車には免許がないけど…行政処分は?
自転車には、自動車のような運転免許制度はありません。そのため、自転車事故で行政処分として免許停止や免許取消になることはありません。
ただし、自転車運転中に交通違反を繰り返すと、「自転車運転者講習」の受講が義務付けられることがあります。また、悪質な違反行為に対しては、反則金が科せられる場合があります。
6. 【困ったときは】自転車事故で弁護士に相談するメリット

自転車事故に遭った場合、または起こしてしまった場合、弁護士に相談することで、様々なメリットが得られます。
6-1. 事故状況を分析し、適切な過失割合を判断
弁護士は、事故状況を詳しく分析し、過去の裁判例や法的知識に基づいて、適切な過失割合を判断します。保険会社から提示された過失割合に納得できない場合は、弁護士に相談することで、過失割合が修正される可能性があります。
6-2. 損害賠償額を正しく計算
弁護士は、被害者の損害を漏れなく把握し、適切な損害賠償額を算定します。弁護士基準(裁判基準)で請求することで、保険会社からの提示額よりも高額な賠償金を得られる可能性があります。
6-3. 保険会社との交渉を全てお任せ!
弁護士は、被害者または加害者の代理人として、保険会社との示談交渉を全て代行します。被害者自身が保険会社と交渉する必要がなくなるため、精神的な負担が軽減され、交渉を有利に進めることができます。
6-4. 後遺障害が残ったら…等級認定をサポート
後遺障害が残った場合、弁護士は、後遺障害等級が認定されるようサポートします。特に相手が自転車の場合、自賠責の等級認定制度がそもそも存在しません。
争いがある場合、最終的には裁判所による適切な等級認定を受けることで、後遺障害慰謝料や逸失利益の賠償を受けることができます。
6-5. 加害者の場合は、刑事弁護も
自転車事故で人を死傷させてしまい、加害者として刑事責任を問われる可能性がある場合、弁護士は、逮捕・勾留からの早期釈放、不起訴処分の獲得、刑の減軽などを目指して、弁護活動を行います。
6-6. 精神的な支え、安心感
交通事故は、被害者にとっても加害者にとっても、精神的に大きな負担となります。弁護士は、法的なサポートだけでなく、精神的なサポートも行い、依頼者の不安を解消します。
7. 【解決事例】弁護士が介入して、こんなに変わった!

(監修者の解決事例となります)
7-1. 過失割合が有利に!
【事例概要】
Aさん(自転車)が生活道路を進行し、右折したところ、対向から進行して来たタクシーと衝突。Aさんは怪我を負い、通院治療を余儀なくされました。相手のタクシー会社は過失割合を40%と主張してきましたが、Aさんは納得できませんでした。また、治療費の一括対応も3ヶ月で打ち切りとなりました。
【弁護士の活動】
警察から、物件事故報告書の取り付けを行いました。また、実際に現場に足を運び、現場調査を行いました。また、相手タクシー会社に、ドライブレコーダー映像の開示を要求。そうしたところ、現場では時間帯によって通行方法が指定されており、わずかの時間でしたが、タクシーはそれに違反していることが判明しました。その上で、相手タクシー会社に対して、Aさんの過失割合は0%であるか、あるとしてもごくわずかであると主張しました。
また、一括対応終了後は、健保を使用しての自費での通院を勧め、症状固定後は後遺障害診断書を作成の上、被害者請求を行いました。
【結果】
被害者請求の結果、自費で立て替えた分の治療費は全額回収(ただし、後遺障害は非該当)。その上で粘り強い交渉をした結果、タクシー会社はAさんの過失割合を10%と認め、また、全治療期間の相当因果関係を認め、慰謝料も増額できAさんは満足のいく賠償を受けることができました。

7-2. 相手自転車の任意保険加入が判明し、早期に賠償を受けることができた!
【事例概要】
Aさんは道路の左側に駐車していたところ、スマホを見ながら自転車を運転していたBさんが、Aさんの自転車の後方に追突しました。幸いAさんにけがはありませんでしたが、車両の修理費用が発生しました。しかし、Bさんは任意保険がなく、支払い能力もないと主張し、逃げ回っているような状態で示談交渉は全く進みませんでした。
【弁護士の活動】
弁護士費用特約でAさんから依頼を受け、相手方に改めて、自転車保険、個人賠償責任保険、ご家族の保険、賃貸の火災保険に確認してもらうようお願いしました。
【結果】
そうしたところ、相手方の賃貸の火災保険に個人賠償責任保険が付帯されており、この事故の賠償も補償の範囲に入ることが判明しました。そして、相手の保険会社が出てきて、相手保険会社と交渉することとなり、早期に修理費の全額を回収することができました。

7-3. 後遺障害が認定された!
【事例概要】
Aさん(自転車)が自動車と衝突し、転倒。首や腰に痛みが残り、治療を続けましたが、症状が改善しませんでした。しかし、相手保険会社は、事前認定の結果(非該当)をもとに、Aさんの症状は後遺障害に該当しないと主張しました。
【弁護士の活動】
Aさんから依頼を受け、症状を詳しく聞き取るとともに、各医療機関に対し、カルテと画像の開示請求をしました。その上で、読影・カルテの分析を行い、Aさんの症状は後遺障害に該当する可能性があると判断し、被害者請求にて、後遺障害非該当に異議申立てをしました。
【結果】
被害者請求の結果、Aさんの後遺障害は14級9号「局部に神経症状を残すもの」に認定され、残額を任意保険会社に請求。後遺障害慰謝料110万円(弁護士基準)と逸失利益(労働能力喪失率5%、期間5年分)を獲得することができました。

7-4. 相手方が自転車で、訴訟で後遺障害が認定された!
【事例概要】
Aさんが自動車に乗車中、坂道を高速度で進行して来たBさん(自転車)がAさんの車の側面に衝突。Aさんは肩を受傷し、可動域制限が生じました。相手保険はAさんのけがの対応をすることは無く、Aさんは自費で治療。症状固定後は後遺障害が残存しましたが、相手は自転車のため、自賠責保険もなく、損害保険料率算出機構・自賠責調査事務所のような後遺障害の認定機関もありませんでした。
【弁護士の活動】
相手自転車の場合、後遺障害については、基本的に裁判所に認定してもらうほかありません。弁護士費用特約でAさんから依頼を受け、訴訟提起し、主治医の意見書も取り付け、後遺障害の残存を主張しました。
【結果】
主張立証を重ね、裁判所和解案、判決とも12級の後遺障害が認められました(裁判所和解案は相手方が受諾拒否)。

8. 【気になる疑問を解決!】自転車事故に関するQ&A

8-1. 警察への届け出は必要?
自転車事故でも、必ず警察に届け出ることをおすすめします。警察が事故を把握していないと、交通事故証明書も発行されませんし、防犯カメラなどの客観的証拠がない場合、事故態様・過失割合の立証に困難を来します。
物損事故扱いの場合、物件事故報告書の開示請求、人身事故扱いの場合であれば、刑事記録の開示請求を行っています。
8-2. 相手が保険に入っていない場合は?
加害者が自転車保険に加入していない場合は、加害者本人に対して損害賠償を請求することになります。
- 加害者が未成年の場合: 親権者などの監督義務者に請求します。
- 加害者が支払いに応じない場合: 内容証明郵便を送付したり、支払督促、少額訴訟、通常訴訟などの法的手段を検討します。
- 回収:財産調査の上、強制執行を検討。ここまでやると、弁護士費用特約がない場合、回収額にもよりますが、費用倒れになることも多いです。
8-3. 自転車同士の事故でも慰謝料は請求できる?
自転車同士の事故でも、相手に過失があり、怪我を負った場合は、慰謝料を請求することができます。
8-4. 事故後、時間が経ってから症状が出たら?
事故直後は症状がなくても、後から痛みやしびれなどの症状が出てくることがあります。事故現場では気を張っていたり、興奮状態であったりして、自分で気づかないこともあります。このような場合でも、事故との因果関係が認められれば、損害賠償を請求することができます。
- 重要なこと:
- 事故後、できるだけ早く医師の診察を受けること。特に初診は重要です。
- 症状の変化を記録しておくこと
- 医師に、症状と事故との因果関係について、診断書に記載してもらうこと
8-5. 弁護士費用特約って何?
弁護士費用特約とは、自動車保険や火災保険などに付帯している特約で、弁護士に依頼した際の費用を保険会社が負担してくれるものです。弁護士費用特約を利用すれば、自己負担を大幅に軽減することができます。
- メリット:
- 自己負担を大幅に軽減できる、またはゼロにできる
- 費用を気にせず、弁護士に依頼できる
- 自分が矢面になって交渉することがなく、精神的に負担が軽減できる
- 使っても自分の保険料が上がることは無い(ノーカウント事故)
- 注意点:
- 保険会社によって、補償内容や利用条件が異なる
- 弁護士を使ったからといって、必ずしも良い結果や、自分の希望する解決内容になるとは限らない

ご自身の加入している保険に弁護士費用特約が付帯しているかどうか、確認してみましょう。また、家族の保険に付帯している特約を利用できる場合もあります。使えるなら、使わないと損です。
9. まとめ|自転車事故は弁護士に相談し、適切な解決を!

自転車事故は、誰もが被害者にも加害者にもなり得る身近な事故です。しかし、その法的責任や賠償問題は複雑であり、専門的な知識がなければ、適切な対応を取ることは困難です。
自転車事故に遭われた方、自転車事故を起こしてしまった方は、一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。弁護士は、あなたの状況を詳しく分析し、最善の解決策を提案してくれます。
この記事が、自転車事故に直面した方々にとって、問題解決の一助となり、より良い未来への一歩を踏み出すきっかけとなることを願っています。














